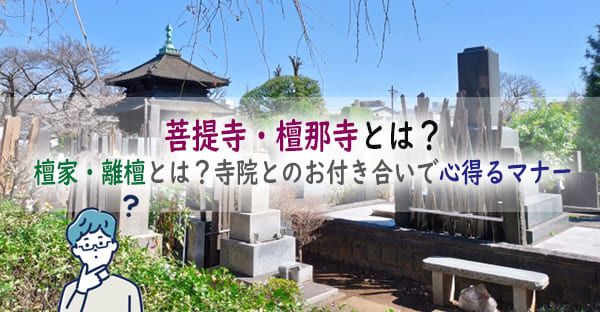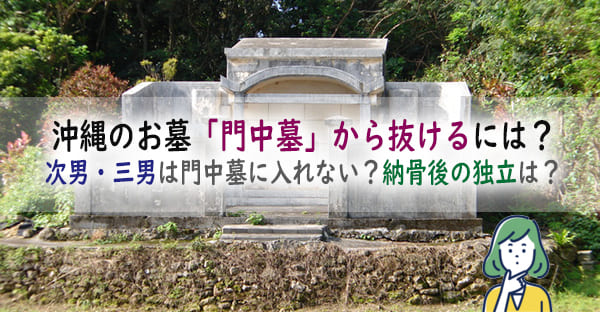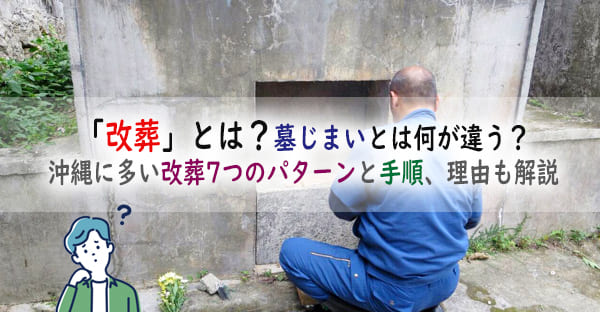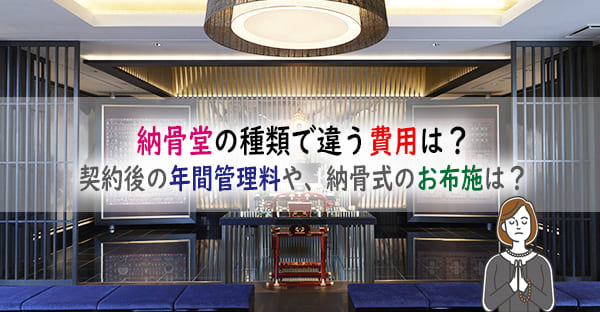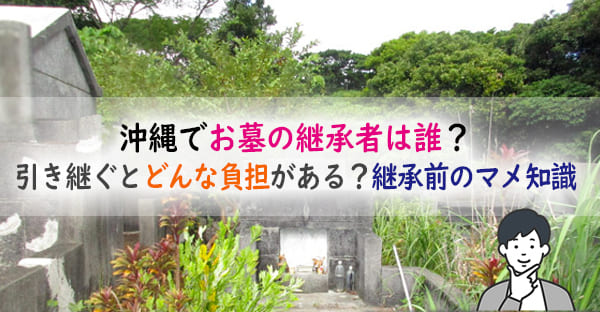・菩提寺・檀那寺とは、どんなお寺?
・檀家になる、離檀するとは、どんなこと?
・寺院とのお付き合いで理解しておくマナーとは?
寺院墓地にお墓を建てると、墓地管理者であるその寺院は菩提寺となり、お墓を建てた家は檀家となります。
菩提寺と檀家にはお付き合いに一定のマナーがあり、そのマナーから外れると、菩提寺との大きなトラブルにもなり兼ねません。
最近の沖縄では個人墓地から墓地管理者がいる霊園や寺院墓地への引っ越し「改葬(かいそう)」が増えました。
本記事を読むことで、菩提寺とはなにか?菩提寺と檀那寺との違いや、菩提寺とのお付き合いにおいて、予め理解しておきたいマナーが分かります。
菩提寺とは

◇「菩提寺」とは、その寺院墓地にお墓が建つお寺です
個人墓地が主流の沖縄では馴染みがありませんが、「菩提寺(ぼだいじ)」とは、墓地に自分達のお墓が建つ寺院を指します。
菩提寺を持つ家では、その寺院の宗旨宗派に倣い通夜や葬儀、法要を執り行い、読経供養は菩提寺のご住職に依頼をするとされてきました。
①菩提寺…寺院墓地に先祖や家族のお墓が建つ寺院
②檀家…菩提寺にとって、寺院墓地にお墓が建つ家
一方、菩提寺にお墓が建つ家は「檀家(だんか)」です。
例えば「我が家は○○寺院の檀家です」、もしくは「○○寺院は家の菩提寺です」などと表現し、この関係性を「檀家制度」と言います。
檀家制度とは
◇檀家制度とは、菩提寺と檀家の関係性を総称した制度です
「檀家制度(だんかせいど)」とは、家が特定の寺院に所属し、菩提寺と檀家の関係性を築く制度を指します。
檀家制度の起源は、江戸時代の「寺請け制度」から始まるでしょう。
この時代には寺院が集落に住む人々を檀家制度により把握し、戸籍に代わる役割を果たしてきました。
江戸時代には全ての人がどこかの寺院の檀家になることを義務とし、現代の戸籍に代わる「寺請証文」を受け取る制度があったためです。
| <菩提寺と檀那寺との違い> | |
| [立場] | [行うこと] |
| (1)寺院 ・菩提寺 ・檀那寺 | ①檀家の葬祭において、仏事を引き受ける ②檀家が建てたお墓を維持管理する |
| (2)家 ・檀家 | ①菩提寺(檀那寺)にお布施をする (寺院存続の経済支援を行う) ②家の葬祭において、仏事を依頼する |
本州ではこれが今も残る地域が多々ありますが、琉球王朝として独自の歴史を歩んできた沖縄では、この檀家制度が根付いていません。
沖縄では個人墓地によるお墓が主流だったため、菩提寺や檀家制度について、あまり知らない人も多いでしょう。
本州に親族ができた(いる)場合、墓地管理者がいる霊園や寺院墓地にお墓を建てる際には、予めこの檀家制度を理解しておくと、行き違いによるトラブルの心配がありません。
菩提寺と檀那寺との違いは?
◇檀那寺は、経済的にその寺院を支える関係性です
基本的に菩提寺も檀那寺も、檀家として行う事柄はほとんど同じですが、特に檀那寺は、その寺院を経済的に支えている檀家が使う言葉となります。
菩提寺とした場合、先祖代々のお墓が建つばかりではなく、その寺院の仏教宗派に帰依し、日常的に信仰している意味合いが強いでしょう。
| <菩提寺と檀那寺との違い> | |
| ①菩提寺 | ・先祖代々墓が建つ ・先祖代々の位牌を預けている ・菩提寺の宗派に帰依している |
| ②檀那寺 | ・檀家となる ・その寺院を経済的に支える(お布施など) |
…などの違いがあり、近年では檀那寺にお墓を持たずに、民間運営の納骨堂など、他の施設で遺骨を納骨している家を「外檀家」とも言います。
「外檀家」は、檀那寺にお墓はないものの、通夜や葬儀、法要などの一切を、檀那寺にのご住職に依頼し、多くは墓じまいでお墓を閉じた家であるケースが増えました。
「離檀」とは?
◇「離檀」とは、その菩提寺の檀家を辞めることです
「離檀(りだん)」とは、寺院墓地のお墓を墓じまいして、菩提寺の檀家を辞める、離れることを指します。
現代では寺院墓地にお墓があっても、その寺院が菩提寺である意識が薄い家が多いですが、寺院墓地にお墓がある場合は、その寺院が菩提寺であり、墓じまいは離檀を意味することが多いです。
| <離檀とは> | |
| [意味] | ・檀家を辞める ・墓じまいをする |
| [離檀料] | ・約5万円~20万円ほど |
現代は菩提寺から離檀する時に、今までお世話になったお礼として「離檀料」をお布施としてお渡しします。
なかには離檀料を請求する菩提寺もありますが、もともと「離檀料」と言う言葉はなく、檀家がお礼の気持ちとして、最後に多めに包んできました。
…弁護士や行政書士、消費者センターなどに相談すると良いでしょう。
「墓じまい」とは、墓地に建つお墓から遺骨を取り出して墓石を撤去し、墓地を整地して墓地管理者である菩提寺に返還することを指します。
菩提寺や寺院の変化

◇琉球王朝の歴史を持つ沖縄では、菩提寺を持つ家がほとんどありません
日本で檀家制度が根付いた江戸時代、沖縄は琉球王朝時代でした。
そのため菩提寺を持つ家はほとんどなく、独自の祖霊信仰を持つことから、特定の仏教宗派をあまり意識しない家が多いでしょう。
けれども全国的にも「檀家制度とは?」「菩提寺ってなに?」と言う声や、「家に菩提寺があるかどうか分からない」と言う人が増えました。
菩提寺があるかの確認方法
◇寺院墓地にお墓が建っていれば、墓地管理者が菩提寺です
現代の日本で菩提寺があるかないかを確認するなら、単純に寺院墓地にお墓がないかどうか?でしょう。
ただ現代では檀家制度の崩壊から、檀家制度自体を廃止する寺院も見受けます。
特に沖縄では墓地を持たない寺院も多いです。
沖縄で遺骨を収蔵する納骨堂を設けた寺院でも「檀家になる必要はない」とする寺院が増えました。
| <檀家を持つ、持たない寺院> | ||
| [寺院の種類] | [檀家] | [主な内容] |
| ①回向寺 (えこうでら) | ・檀家を持つ | ●檀家の供養をする ・先祖の追善供養 ・家の繁栄(守護) |
| ②祈祷寺 (きとうでら) | ・檀家を持たない ・寺院墓地がない | ●現世利益を祈祷する ・商売繁盛 ・無病息災 ・恋愛成就 …など |
回向寺では檀家の先祖代々の供養や、お墓の供養・管理を担い、檀家から定期的にお布施をいただいて成り立っています。
一方で祈祷寺は、個人的な現世利益である無病息災や恋愛成就、学業成就などを目的として祈祷や参拝を受け付けて成り立つ寺院です。
沖縄ではそもそも寺院墓地を持たない寺院が多いため、寺院墓地をそもそも持たない寺院も「祈祷寺」と呼びます。
菩提寺の「宗派」とは

◇仏教には真言宗や臨済宗など、いくつかの宗派に分かれます
沖縄ではそもそも個人墓地にお墓を建てる習慣があったので、この菩提寺とはあまり関わりがないかもしれません。
けれども今では本州の人々とも婚姻関係を結ぶことでしょう。
本州の人で菩提寺がある場合、その菩提寺の宗派を理解しておくと、宗派に倣った作法で供養を進めるため、冠婚葬祭の仕組みが分かりやすいです。
| <菩提寺の宗派> | ||
| [宗派] | [開祖] | [本山] |
| ①天台宗 (てんだいしゅう) | ・最澄 (さいちょう) | ・比叡山延暦寺 |
| ②真言宗 (しんごんしゅう) | ・空海 (くうかい) | ・高野山金剛峰寺 …など |
| ●浄土系 | ||
| ③浄土宗 (じょうどしゅう) | ・法然 (ほうねん) | ・知恩院 …など |
| ④浄土真宗 (じょうどしんしゅう) | ・親鸞 (しんらん) | ・東本願寺(真宗大谷派) ・西本願寺(本願寺派) …など |
| ●禅系 | ||
| ⑤臨済宗 (りんざいしゅう) | ・栄西 (えいさい) | ・鎌倉五山 ・京都五山 …など |
| ⑥曹洞宗 (そうとうしゅう) | ・道元(どうげん) ・瑩山(けいざん) | ・永平寺 ・総持寺 …など |
| ⑦日蓮宗 (にちれんしゅう) | ・日蓮 (にちれん) | ・久遠寺 …など |
| ●奈良仏教系 | ||
| ⑧南都六宗 | ・三論(さんろん) ・成実(じょうじつ) ・倶舎(くしゃ) ・法相(ほっそう) ・華厳(けごん) ・律(りつ) | |
親族の家で菩提寺を持つ場合、その宗派に倣った作法でお焼香をしたり、数珠を用いたりしますので、やはり婚家の菩提寺の仏教宗派は知っておくと安心です。
「開祖・宗祖」とは、その宗教宗派を開いた人、「本山」はその宗派の複数の寺院を統括する存在であり、宗派の最高統括に値する寺院は「総本山」と言います。
ちなみに沖縄では臨済宗のお寺が多い傾向です。
全国的にも地域によって寺院が多い仏教宗派が分かれます。
・文化庁:平成28年度版「宗教年鑑」
・【葬儀マナー】数珠の持ち方は、仏教宗派で違う!便利な略式数珠の扱い方
菩提寺を持つと戒名が必要?
◇菩提寺を持つ家では、家族が亡くなると菩提寺のご住職に戒名をいただきます
「戒名(かいみょう)」とは、仏弟子になった証としていただくお名前で、生前にも付けることはできるものの、一般的には亡くなってから菩提寺のご住職に付けていただくことが多いです。
●菩提寺がある場合、家族が亡くなるとその寺院に帰依し、お釈迦様の弟子となるために、菩提寺の宗派に倣い、ご住職に戒名を依頼します。
また菩提寺はその家の一切の仏事を担うため、戒名だけではなく通夜や葬儀、その後の法要を通して、全ての供養や仏事を行うでしょう。
また戒名には「位」があり、より高い位の戒名をいただきたい場合は、より高いお布施を包んでお願いする風習が産まれました。
ただ本来は、生前の徳行によって決められるものです。
お布施も徳行のひとつなので、多く包むようになったのでしょう。
菩提寺との戒名トラブル
◇菩提寺が戒名を付けていないと、納骨できないことがあります
一般的なイメージとして、戒名は僧侶しか付けられないイメージを持ちますよね。
けれども実は、「戒名」は自分で付けることも可能です。
またインターネットでは格安で戒名を名付けるサービスも見受けるようになりましたが、菩提寺がある家では、菩提寺のご住職に戒名を名付けてもらいます。
ご住職に相談せずに戒名を付けた場合、埋葬をしてもらえないトラブルもあるためです。
| <戒名の名付け方> | |
| ①菩提寺がある | ・寺院墓地 ・ご住職に戒名を依頼 |
| ②菩提寺がない | ・民間霊園 ・公営墓地 ・個人墓地 ・戒名の名付けは自由 |
菩提寺に戒名を依頼せず、納骨できなかったトラブル例では、改めてご住職に戒名を付けていただいた解決策が多く、余計に戒名料が掛かっています。
戒名料はどれくらい?
◇戒名には位によって、料金の幅が広いです
お布施は仏教の教えでは徳行のひとつ「布施行」なので、決まった料金設定はありませんが、ご住職に伺うと、目安として戒名に必要な金額を伝えてくれるでしょう。
| <戒名料の一例> | |
| ①信士、信女 (しんじ、しんにょ) | …約10万円~30万円ほど |
| ②居士、大姉 (こじ、だいし) | …約30万円~80万円ほど |
| ③院号 | …約100万円~ |
けれども誤解を恐れずに言えば「言い値」でもあるので、檀家は菩提寺が管理する寺院墓地に建つお墓に、家族の遺骨を埋葬してもらうため、無理をして戒名のためのお布施を多額に包んだ体験談などもあります。
・沖縄で法要に包むお布施の金額目安。沖縄で戒名まで依頼する?
沖縄の戒名について
◇沖縄では俗名をトートーメー札に記載する風習があります
現代では沖縄でも戒名を付ける例が増えましたが、菩提寺を持たない場合、約3万円~10万円ほどが戒名料の目安です。
●菩提寺がない場合、戒名の有無や付け方は自由です。
…葬儀社や霊園などに相談すると良いでしょう。
仏教への信仰が厚い人々からは、「あの世の名前である戒名を付けていただかないと成仏できない」などの声もありますが、あくまでも仏教の教えによるものです。
(そもそも「戒名」は仏弟子になった証であり、「あの世の名前」ではありません。)
また沖縄に限らず現代の日本では、離檀して無宗教になる家も増え、戒名を持たないケースも増えました。
菩提寺があるメリット、デメリット

◇菩提寺があることで、家の仏事全般を相談できます
トラブルも多い檀家制度ですが、現代に続いてきたのには、それなりのメリットもあるためです。
その昔、日本では人が亡くなると菩提寺の畳間を借りて、法要を執り行ってきました。
そして隣近所の檀家同士が、通夜や葬儀において、喪家の世話役を担う「隣組」制度により、持ちつ持たれつで暮らしてきた歴史があります。
菩提寺があるメリット
◇家の仏事や継承などの困りごとを相談できます
菩提寺は地域に根差した寺院が多く、先祖代々の家の事情を知っているため、昔からあらゆる仏事について相談ができる存在でした。
家族に突然の不幸があったり、継承問題に悩んでいても、まず菩提寺に相談できることは、家長にとってとても心強いです。
①仏事について相談できる
②突然の不幸に対応できる
③手厚い供養が期待できる
またなかには、菩提寺に存続していただき、地域を活性化させることを重視する檀家も見受けます。
古くから地域に根差した菩提寺は、その集落の象徴でもありますが、檀家がいなくなると、経済的な支えもなくなるためです。
菩提寺があるデメリット
◇菩提寺があることで、仏事や供養、宗派の自由がなくなります
菩提寺がある檀家は、その寺院の宗派に帰依するため、故人の供養など仏事において、全てをその宗派に倣わなければなりません。
また檀家は菩提寺を経済的に支える存在でもあります。
菩提寺のご住職とのお付き合いの他、定期的なお布施を包む義務も生じるでしょう。
①宗教の自由がない
②離檀料が掛かる
③ご住職とのお付き合い
④お布施を毎年包む
ただし毎年包むお布施は、民間霊園で毎年支払う「年間管理料」に匹敵します。
民間霊園や公営墓地であっても、公共部分の管理費用として毎年年間管理料を支払わなければなりません。
●年間管理料に匹敵
・約1万円~3万円ほど/年間
檀家としてお布施の支払いに苦慮するならば、寺院が老朽化した時の修理・修繕費用の依頼があった時でしょうか。
仕組みとしては分譲マンションの年間管理料や修理・修繕費用に似ています。
このように菩提寺があることはデメリットとする人も増えましたが、必ずしもデメリットばかりではありません。
まとめ:他県では菩提寺がある家も多いです

沖縄では個人墓地にお墓を建ててきた歴史があり分かりにくいものの、全国的には菩提寺との関係性を長く築いてきました。
菩提寺とはなにか、お付き合いのマナーを知っておくと、他県出身の親族や、他県の葬儀や法要に参列する際、菩提寺を知るからこその気遣いもできるでしょう。
また最近では個人墓地から民間霊園の区画にお墓を改葬(引っ越し)する家も増えましたが、民間霊園は比較的、近代にできたもので、お墓を建てるに当たり特定の宗旨宗派を問わない施設がほとんどです。
そのため沖縄においては読経供養を依頼する際に、僧侶がどの仏教宗派であるかを知り、その宗派に倣った作法を心掛ける以外は、大きな問題はないでしょう。
・【葬儀マナー】お焼香の仕方は仏教宗派で違う!「押しいただく」回数も解説