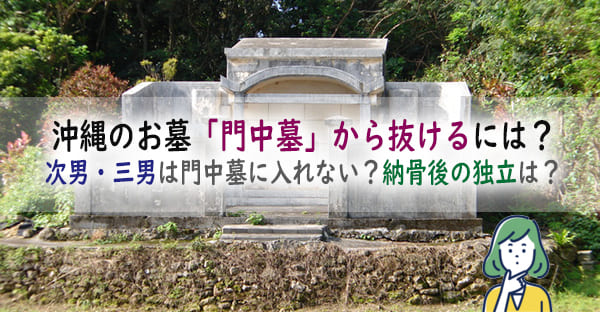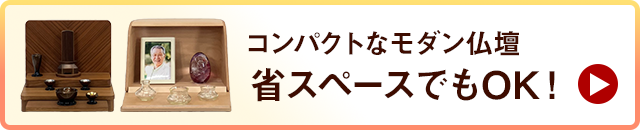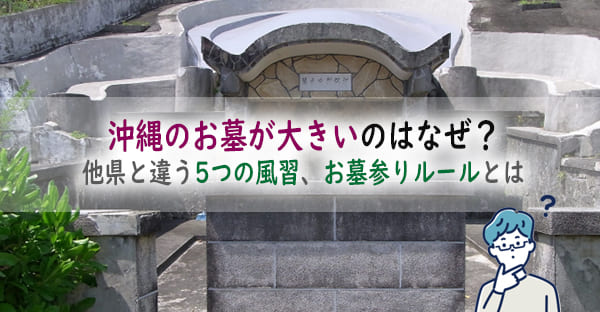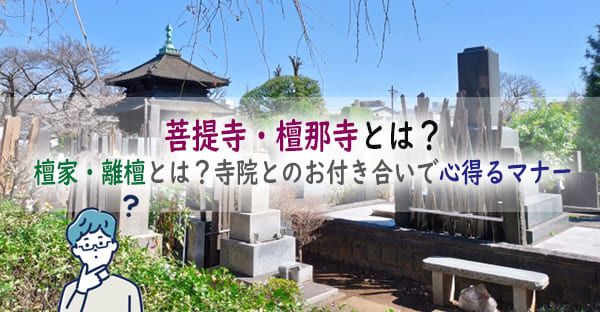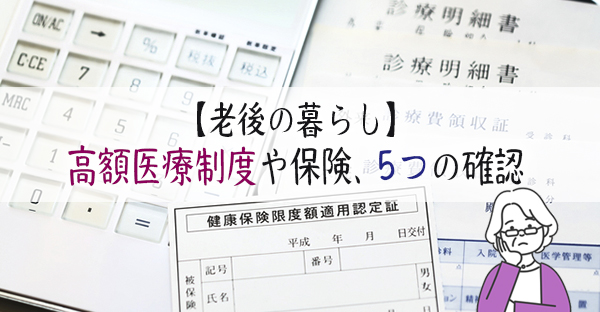・門中墓から抜けるには?
・次男や三男は門中墓に入れない?
・納骨したら門中墓から独立できない?
沖縄のお墓「門中墓」とは、父方の血族で入る始祖を同じくした集まり「門中」のお墓です。
タブーやしきたりがある門中墓は今も多く、抜けるか迷う声も聞こえます。
本記事を読むことで、門中墓に多いしきたりやタブー、門中墓から抜ける手順や注意点が分かります。
門中墓とは?

◇「門中墓」とは、父方の血族「門中」によるお墓です
「門中墓(むんちゅうばか)」とは、父方の血族による始祖を同じくした集まり「門中(むんちゅう)」の人々が入るお墓となり、先祖代々墓とは異なります。
基本的に父方の血で繋がる人々が入るお墓ですが、嫁は入ることが可能です。
下記より昔から伝わる門中墓に入る人を解説しますが、現代では門中によりしきたりへの解釈も違うでしょう。
| <門中墓に入る人> | |
| [門中墓に入る人] | ・代々嫡男 ・その嫁 ・独身の次男・三男 |
| [門中墓に入れない人] | ・養子、養女 ・婿養子 ・独立した次男・三男 ・独身の娘 ・子どもを産んでいない女性 ・幼くして亡くなった子ども |
…などとされ、結婚をして独立した次男以降の男性は、自分を始祖としたお墓を新しく建てるとされます。
一方で継承者がいない独身の娘や、幼くして亡くなった子ども、子どもを産んでいない女性は、本墓には入らず、墓地内の祠に納骨されてきました。
幼い子どもとされる年齢は3歳・7歳などの門中がありますが、現代はこのようなしきたりもなくなりつつあります。
しきたりは門中によりさまざま
◇門中墓に入る人のタブーやしきたりは、門中によりさまざまです
全国的にも、法的に墓主が許可すれば、血縁関係がなくても同じお墓に入れるように、門中墓も現代では、墓主となるムートゥーヤー(本家)の解釈により、判断が分かれます。
| <門中にあったさまざまなしきたり> | |
| [緩い例] | ・娘や子どもでも、誰でも入れる ・門中に貢献した人が本墓に入る |
| [独自のしきたり] | ・兄弟は一緒のお墓に入れない ・1年間は祠に入り、旧暦10月24日に本墓に納骨する |
…などなど、複数の人々に相談をしてみると、所属する門中によって答えは違うかもしれません。
兄弟が一緒のお墓に入れない場合、長男が入れば次男以降は独身でも新しく個人墓を建てることになります。
「1年間は祠に入る」しきたりは、その昔に風葬の歴史があったためでしょう。
数年後に洗骨をしてジーシガーミ(骨壺)に納め、納骨する流れです。
門中墓から抜けるには?

◇門中墓から抜ける場合、ムートゥーヤー(本家)にご相談します
現代の沖縄では、このような門中墓のしきたりも随分緩くなったものの、大きな門中では入っていることで役割も多く、負担になり抜けたい声も増えました。
・定期的に巡る世話役「アタリ」が負担
・旧暦行事のお手伝いや参加ができない
・子どもが祠に入ることに抵抗がある
・独身の娘が入れるお墓を用意してあげたい
・ムートゥーヤーと意見が合わない
…などなど、現代の沖縄では門中墓から抜けることを検討する家が増えていますが、問題はムートゥーヤーとの関係性だけで、法的には問題はありません。
特に沖縄にも民間霊園が登場し、新しいお墓を建てやすくなりました。
・【沖縄のお墓】沖縄で増える「入るお墓がない!」問題、5つの解決方法とは
お墓を建てても継承者がいない
◇継承者がいない人の遺骨を供養するには、永代供養が役立ちます
ただ次男や三男などで門中墓から抜ける人など、「お墓を建てても継承者がいないから、無縁仏になるのでは?」と心配する人が多いです。
けれども民間霊園では、多くが「永代供養」が付いているので、独身者でも個人墓が立てやすいでしょう。
●「永代供養(えいたいくよう)」とは
…家族や子孫に代わり霊園管理側が、永代に渡り遺骨の管理や供養をしてくれるサービスです。
・永代供養付き個人墓
・納骨堂
・合祀墓(他の遺骨とともに納骨)
また樹木葬などの自然葬を選ぶと、土に還るなど自然に還るので、後々無縁仏になることはありません。
納骨したけど門中墓から抜けることはできる?

◇納骨した遺骨を取り出して移動する方法もあります
門中墓から抜ける場合、複雑になるパターンが納骨後の独立です。
家族の遺骨を納骨したものの、後になって門中墓から出したい場合は、行政上では遺骨を引っ越す「改葬(かいそう)」の手続きとなるでしょう。
改葬には遺骨がある自治体へ改葬許可申請をするため、門中墓の墓主(管理者)から、遺骨を埋葬している証明「埋葬証明書」を発行してもらいます。
ただし門中墓の種類によって、改葬できない遺骨もあるので注意をしてください。
●合祀墓
…門中墓が、他の人々の遺骨と一緒に納骨する「合祀(ごうし)」スタイルであれば、家族の遺骨のみを取り出すことはできません。
特に大きな門中墓に多いです。
大きな納骨スペース「カロート」の底面が土になっており、遺骨を骨袋や骨壺から取り出して大きなカロートに、他の門中の人々の遺骨とともに納めるためです。
また埋葬証明をしてもらうにあたり、墓主(墓地管理者)の合意が必要になります。
そして取り出した遺骨は、何らかの形で供養をしなければなりません。
門中墓から抜ける:遺骨の引っ越し5つのステップ

◇ムートゥーヤー(本家)から許可を得たら、まず新しい納骨先を決めます
家族の遺骨を取り出して、門中墓から抜けるためには、墓主であるムートゥーヤー(宗家)協力のもと、自治体で改葬許可証を発行してもらわなければなりません。
改葬許可証を発行してもらうには、埋葬許可証、受入証明が必要です。
| <門中墓から抜ける5つのステップ> | |
| [ステップ] | [行うこと] |
| ①ムートゥーヤー(本家)に相談 | ・遺骨の取り出し許可 |
| ②新しい納骨先を決める | ・受入許可証をもらう |
| ③改葬許可申請 | ・改葬許可証の発行 |
| ④遺骨の取り出し | ・閉眼供養 ・石材業者へ依頼 |
| ⑤遺骨の納骨 | ・納骨式 |
墓地管理者が墓地を管理している霊園や寺院墓地、公営墓地の場合、墓地管理者から埋葬証明をしてもらいますが、個人墓地の場合、墓地を所有する墓主が証明します。
門中墓から抜ける①本家に相談
◇墓主であるムートゥーヤー(本家)に独立の意思を伝えます
門中墓から家族の遺骨を取り出すため、ムートゥーヤー(本家)の許可は不可欠です。
門中墓を取り仕切るムートゥーヤー(本家)は墓主でもあります。
たとえ家族の遺骨であっても、墓地管理者である墓主の許可なく、勝手に遺骨を取り出すことは、行政手続き上できません。
●墓地の名義人である墓主に許可をもらい、取り出す遺骨を証明する「埋葬証明」をしてもらいます。
門中墓から家族の遺骨のみを取り出す場合でも、市町村役場で遺骨を引っ越す許可「改葬許可証」を発行してもらわなければならず、そのためには埋葬証明が不可欠です。
門中墓から抜ける②新しい納骨先
◇門中墓から抜ける前に、新しい納骨先を決めましょう
改葬許可証を発行してもらうためには「受入証明」が必要です。
受入を証明する「受入証明書」は、新しい納骨先から発行されます。
手続きをスムーズに進めるためには、先に取り出した遺骨の新しい納骨先を決めておくと良いでしょう。
・霊園の資料請求
・霊園見学
・納骨先を決める
・契約
・受入証明
現代ではお墓の値段も安くなっていますが、新規で建てるとなると100万円~175万円ほどは掛かるでしょう。
けれども近年では民間霊園を中心に、納骨堂や屋外の集合墓、ワンプレート墓石のガーデニング型樹木葬なども提供されるようになりました。
また近年では家族に代わり遺骨の供養や管理を墓地管理者が担う「永代供養」が広がっていますので、納骨後が楽になります。
新しい遺骨の納骨先も、合祀墓(永代供養墓)であれば5万円ほど/1柱~契約できるので、予算に合わせて選ぶと良いでしょう。
門中墓から抜ける③改葬許可申請
◇自治体から「改葬許可証」が必要です
遺骨が眠るお墓がある自治体の役所窓口で、改葬許可申請を行います。
「改葬(かいそう)」とは遺骨やお墓を引っ越すことを指し、「改葬許可証」は遺骨を取り出す際、石材業者へ提出をする書類です。
改葬許可証は1柱につき1枚必要ですが、門中墓から抜けるケースの改葬なら、1柱で留まることが多いでしょう。
| <門中墓から抜ける:改葬許可申請> | |
| [提出書類] | [発行場所] |
| ①改葬許可申請書 | ・役所 (ホームページ) |
| ②受入許可証 | ・新しい納骨先 |
| ③埋葬証明書 | ・現存の墓地管理者 |
| ●個人墓地の場合 | ・お墓の名義人(墓主) ・墓所の地図 …など |
| ④本人確認書類 | ・マイナンバーカード ・自動車免許証 …など |
改葬許可申請書は、ホームページでダウンロードできる自治体が多いです。
埋葬証明書、受入証明書が一体化している改葬許可申請書の場合、埋葬証明・受入証明の欄が設けられたものもあります。
この場合は、それぞれ署名、捺印をしてもらうと良いでしょう。
沖縄では個人墓地が多く、個人墓地は個人名義なので、署名・捺印とともに、墓所の地図などを印刷して証明するケースが多いでしょう。
自治体によって提出書類は異なるため、まずは自治体ごとに確認をしてください。
・那覇市「改葬許可について」
門中墓から抜ける④遺骨の取り出し
◇遺骨を取り出す前に、読経供養を行います
門中墓から抜けるために遺骨を取り出す場合は、お墓を解体する墓じまいにはあたりませんが、お墓を開ける前の読経供養を行う流れが一般的です。
沖縄には特定の菩提寺がない家が多いため、昔は近隣の寺院に相談しました。
現代では、新しい納骨先の墓地管理者や、石材業者、仏壇仏具店などに相談すると紹介してくれるでしょう。
| <遺骨を取り出す費用目安> | |
| [支払先] | [費用目安] |
| ①石材業者 (遺骨の取り出し) | ・約3万円~5万円/1柱 |
| ②僧侶 (読経供養の依頼) | ・約3万円~5万円/1回 |
その昔はユタさんにお願いしましたが、現代はユタ付きの家も少なく、霊園などで紹介してもらった僧侶へ依頼する流れがスムーズなためでしょう。
近年ではインターネットでも僧侶派遣サービスを見受けます。
なお、僧侶への読経供養のお礼はお布施として、厚手の白封筒に包み「お布施」の表書きで整えてお渡ししてください。
・沖縄の法要でお布施を包む。僧侶へ渡す時の準備やマナーとは
門中墓を抜ける⑤遺骨の納骨
◇遺骨を納骨する際は、納骨式を行います
門中墓から抜けるにあたり、取り出した家族の遺骨は、新しい納骨先へ納骨する時に納骨式を執り行う流れが一般的です。
納骨式も読経供養と参列者によるお線香(お焼香)の流れになるでしょう。
新しいお墓を建てた場合は、開眼供養も一緒に行います。
| <納骨式の費用目安> | |
| [支払先] | [費用目安] |
| ①石材業者 (墓石の開閉を依頼) | ・約3万円~5万円ほど/1柱 |
| ②僧侶 (読経供養の依頼) | ・約3万円~5万円ほど/1回 |
| ●開眼供養を行う場合 | ・約5万円~7万円ほど/2回 |
お布施に決まった金額はありませんが、開眼供養を行う際、2回の読経供養を依頼するならば約5万円~7万円と、2回分の読経供養のお礼として多めにお布施を包むのがマナーです。
また、お墓の開閉は自分達でもできますが、墓石は重く、思わぬ事故のリスクを避けるためにも、石材業者にお墓の開閉を依頼すると良いでしょう。
・開眼供養・閉眼供養とは、いつ行うの?しないとだめ?進め方やお布施、お供え物まで解説
まとめ:門中墓から抜けて、永代供養を選ぶ

門中墓は父方の始祖を同じくする血族の集まり「門中」によるお墓です。
法的にお墓は、墓主の許可があれば血縁の関係なく、誰でも入ることができますが、門中墓は昔からのしきたりを忠実に守る門中もあるでしょう。
門中に入っていれば、お墓を建てる費用が掛からず、継承者の心配もない反面、門中の年中行事のお手伝いやお付き合い、協同資金の模合など、負担もあります。
ただ一方で門中墓のしきたりに悩む人も多く、門中墓から抜ける人も増えました。
その背景には、墓地管理者に遺骨の供養や管理を委ねることができる永代供養の登場もあるでしょう。
この他、夫婦や子どもなど、ごく身内の故人であれば、自宅で毎日遺骨を祀り供養する方法も増えています。
・沖縄で手元供養が広がる3つの理由と3通りの方法
・沖縄で納骨した遺骨を手元供養にしたい!遺骨を取り出す改葬手続きとは