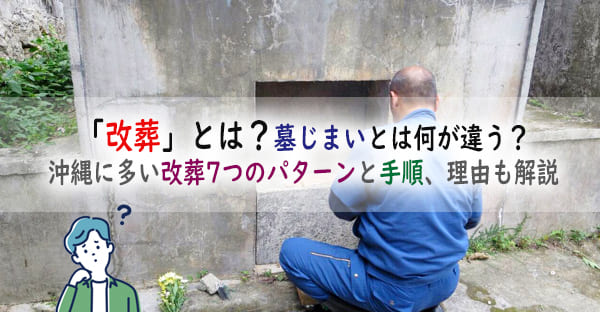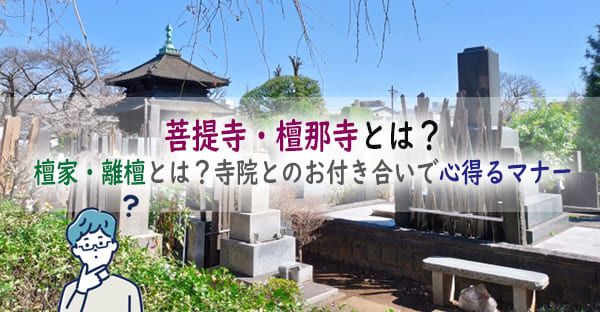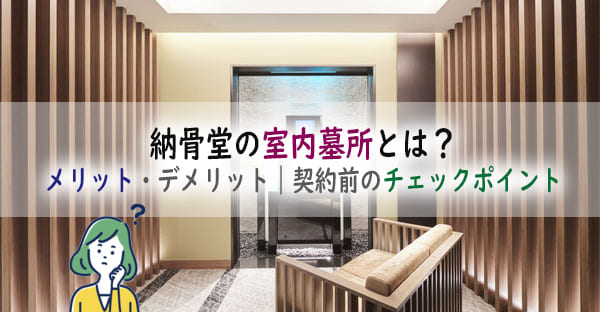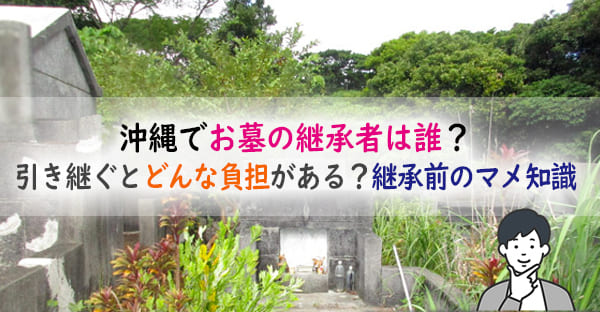・「改葬」とは?
・改葬と墓じまいは違う?
・沖縄に多い改葬の事例とは?
・沖縄で改葬が増えているのはなぜ?
・改葬はどうやってすればいい?
沖縄で増える「改葬(かいそう)」とは、お墓や遺骨を違う場所へ引っ越すことです。
お墓の継承者がいない、墓主がお墓の維持管理ができない、などの理由から、改葬を選びます。
本記事を読むことで、沖縄で急増する「改葬」とはなにか?墓じまいとの違いや、沖縄に多い改葬パターン、5つの事例が分かります。
「改葬」とは?
◇「改葬」とはお墓や埋葬した遺骨を、他の墳墓へ移すことです
「墳墓(ふんぼ)」とは、遺骨を収蔵・納骨する場所を指し、お墓や永代供養墓、納骨堂なども墳墓となります。
沖縄で改葬が急増する背景は、墓主の高齢化、将来的なお墓の継承者のあてがない、個人墓地の維持管理が困難、などです。
・お墓の維持や管理負担が軽減する
・継承者問題を解消する
・無縁墓化を避ける
・老朽化したお墓に対処する
・先祖代々の遺骨を整理する
・個人墓地から霊園へ移動する
沖縄の改葬で最も大きな判断材料は、お墓継承の可否です。
お墓継承は事情により難しいものの、ご先祖様(遺骨)への尊厳性を守りたい場合に、墓じまいの選択をする家が多いでしょう。
改葬と墓じまいの違いは?
◇墓じまいは、墓石を解体し撤去することです
墓じまいは現存するお墓を解体・撤去して更地にすることを指し、改葬はお墓や、お墓から取り出した遺骨を別の場所で供養することを指します。
現実的には墓じまいをすると、遺骨を葬る法律「墓埋法」により、取り出した遺骨は何らかの方法で供養しなければならないため、墓じまいと改葬は同義です。
①改葬
・遺骨を現存の墓所から、新しい墓所へ納骨し直すこと
②墓じまい
・現存の墓石を撤去、墓地を整地した後、使用権を返還すること
ただ「墓じまい」は民間から発生した言葉であり、改葬は行政手続き上の言葉となるため、墓じまいでも役所窓口では「改葬許可申請」を行い、「改葬許可証」を入手します。
ちなみに全国的な墓じまいでは霊園や寺院墓地など、墓地管理者がいるため墓じまいの後には、墓地を使用する「永代使用権」を返還しますが、沖縄の個人墓地では墓地の廃止手続きです。
また墓じまいにより取り出した遺骨は、一般的に他の遺骨とともに合祀・供養される合祀墓(永代供養墓)に埋葬され、永代供養されます。
沖縄に多い改葬、5つのパターンとは
◇お墓の継承を前提とした改葬と、継承しない改葬があります
沖縄の改葬パターンは、お墓の継承者がいらない墓じまいばかりではなく、門中墓から抜けるための改葬や、将来的に継承者が出てくることを見越したパターンも多いです。
| <沖縄に多い改葬:5つのパターン> | |
| ●改葬 (継承を前提とした改葬) | ①お墓の建て替え ②お墓の引っ越し ③お墓から独立 |
| ●墓じまい (継承しない改葬) | ④遺骨を残す ⑤遺骨を残さない |
| ●その他 | ⑥納骨堂 ⑦手元供養 |
現在の墓主がお墓の維持管理をする負担がなくなり、将来的にも継承者を必要としない改葬ならば、墓じまいになるでしょう。
墓じまいであっても、取り出した遺骨を一定期間は個別に安置するか、それとも最初から遺骨を残さない供養方法を選ぶのか、判断が分かれます。
・沖縄で納骨した遺骨を手元供養にしたい!遺骨を取り出す改葬手続きとは
沖縄の改葬①お墓の建て替え
◇お墓の老朽化による建て替えも多いです
沖縄のお墓は大きいことで有名ですが、それ故に古い沖縄のお墓は、コンクリート造りのものも多いです。
沖縄で戦後から増えたコンクリート造りのお墓が、何十年もの築年数となり、現代は丁度、経年劣化による老朽化が深刻になったタイミングとなります。
コンクリート造りのお墓は、一度ヒビが入ると水が浸入しやすいため、どんどん劣化が激しく進み、毎年修理修繕に追われる門中墓も多いです。
お墓の建て替えを行うことで、後々はお墓継承ができるうえ、遺骨の尊厳も守れます。
| <沖縄の改葬①お墓の建て替え> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・お墓、墓所ともに継承 |
| ②新しい墓石 | ・新しく建立 |
| ③墓所 | ・継続する |
| ④古い墓石 | ・撤去(処分)する |
| ⑤遺骨 | ・新しい墓石に納骨 |
そこで「毎年コストを掛けて修理修繕を続けるよりも、思い切って建て替えよう!」と、より長持ちしやすい墓石でのお墓へ建て替えするパターンなどもあります。
・【沖縄のお墓】経年劣化でお墓の建て替え!いくら掛かるの?建て替え6つの手順も解説!
沖縄の改葬②お墓の引っ越し
◇沖縄では、霊園や寺院墓地へのお墓の引っ越しが増えています
沖縄には個人墓地が多いですが、墓地の名義人は墓主、個人の所有です。
自由度は高く墓所も広く取ることができるメリットはありますが、墓主にとっては、最初から最後まで、個人で墓地を維持管理しなければならない負担があります。
一方、墓地管理者がいる寺院墓地や霊園では、公共部分の管理は寺院墓地や霊園が担い、行政手続き上も墓地の名義人は宗教法人や公益財団法人です。
墓地内には法要室やトイレ、掃除用具の貸し出しなどもあり、お墓の管理がぐっと楽になるでしょう。
| <沖縄の改葬②お墓の引っ越し> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・新しいお墓、墓所 |
| ②新しい墓石 | ●2つの選択肢 ・古い墓石の移動 ・新しいお墓を建てる |
| ③墓所 | ・処分する |
| ④古い墓石 | ●2つの選択肢 ・新しい墓所へ移動 ・撤去(処分)する |
| ⑤遺骨 | ・新しい墓所に納骨 |
以前の沖縄でお墓と言えば個人墓地に建てましたが、現代はほとんどの自治体で、新しくお墓を建立する時には、霊園などへのお墓の建立を推奨しています。
そのため新しく墓所を準備する場合、現代では霊園で、区画を永代に渡り使用できる「永代使用権」契約の流れになるでしょう。
沖縄の改葬③お墓から独立
◇お墓から個別の遺骨を取り出して、他の墳墓へ納骨します
沖縄では父方の血族関係者が入る「門中墓(むんちゅうばか)」がありますよね。
全国的な先祖代々墓にあたる沖縄のお墓が、門中墓でしょう。
ただ沖縄には厳格なルールを持つ門中もあるなどの理由から、「門中から独立して、個別にお墓を建てて供養したい」と希望する人も増えました。
このように門中から抜けるにあたり、すでに納骨した家族の遺骨を取り出して、新しい墓所や納骨堂などの墳墓へ納骨し直す改葬も増えています。
| <沖縄の改葬③お墓から独立> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・新しいお墓、墓所 |
| ②新しい墓石 | ・新しい墓所に建立 (納骨堂などもあり) |
| ③墓所 | ・存続 (古い墓所から独立) |
| ④古い墓石 | ・存続 (古い墓所から独立) |
| ⑤遺骨 | ・新しい墓所に納骨 (独立した一部のみ) |
この他、門中墓から家族の遺骨を取り出して改葬するパターンでは、門中から独立はしない家族もいます。
例えば「門中墓はあまりに遠方で、思うようにお墓参りができない」などの理由があり、この場合は他県の納骨堂などに改葬されるパターンも多いです。
・沖縄のお墓「門中墓」から抜けるには?次男・三男は門中墓に入れない?納骨後の独立は?
沖縄の改葬④遺骨を残す墓じまい
◇墓じまいをして取り出した遺骨を、個別安置することもできます
お墓の維持管理が難しく継承者のあてもない場合には、お墓から遺骨を全て取り出して墓石を撤去する改葬、墓じまいが主流です。
この場合、お墓から取り出した遺骨は、霊園や寺院墓地の墓地管理者が、家族に代わって永代に渡り管理・供養する「合祀墓(永代供養墓)」に埋葬する方法があります。
けれども「まだ幼い子どもが、将来的にお墓を継承してくれるかもしれない」など、後々お墓を建てたい、遺骨を遺したい場合には、遺骨を残す永代供養もあります。
| <沖縄の改葬④遺骨を残す墓じまい> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ●自由 ・お墓、墓所は残らない ・将来的に継承の可能性がある |
| ②新しい墓石 | ●自由 ・永代供養付きの個別墓 ・納骨堂 ・集合墓 …など |
| ③墓所 | ・処分 |
| ④古い墓石 | ・撤去(処分) |
| ⑤遺骨 | ・一定年数残る ・契約更新あり |
遺骨を個別安置できる永代供養の種類は、一般墓に永代供養を付ける他、個別スペースに遺骨を収蔵する納骨堂や集合墓なども可能です。
ただし個別安置できるのは契約した一定年数であり、それ以上、個別安置したいならば、期間内に契約更新をしなければなりません。
契約更新なく一定期間が過ぎると、合祀墓(永代供養墓)に合祀されます。
沖縄の改葬⑤遺骨を残さない
◇墓じまいで取り出した遺骨を、合祀墓(永代供養墓)などに埋葬します
今の墓主が高齢になり、お墓の維持管理が困難になったものの、若い世代からの継承者がいないまま時が過ぎ、「無縁墓になるくらいなら、墓じまいをして供養をしよう」と選ぶ、沖縄の改葬事例が、墓じまいです。
墓じまいで取り出した遺骨は、合祀墓(永代供養墓)や自然葬で供養され、一度施してしまうと、二度と手元に遺骨は戻りません。
けれども永代供養墓では墓地管理者が家族に代わり、永代に渡って遺骨の供養をしてくれますので、遺骨の尊厳は守ることができます。
| <沖縄の改葬⑤遺骨を残さない> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・なし |
| ②新しい墓石 | ・なし |
| ③墓所 | ・処分 |
| ④古い墓石 | ・撤去(処分) |
| ⑤遺骨 | ・合祀墓(永代供養墓) ・樹木葬 ・散骨 …など |
墓じまいで取り出した遺骨は「お墓のない葬送」として、合葬墓や樹木葬など自然葬、海洋散骨などが選ばれ、墓じまい後は礼拝の対象となる、個別の墓標が残りません。
ただ合祀墓(永代供養墓)であれば合同の供養塔に参拝できます。
樹木葬でも埋葬したふもとのシンボルツリーに供養できるでしょう。
樹木葬や散骨などの自然葬の場合、定期的な供養はないものの、遺骨が自然に還る葬送ができます。
沖縄で注目される2つの改葬とは

◇墓じまい後、費用を抑えて遺骨を残す改葬が注目されています
個人墓地は個人でお墓のみならず、墓地まで管理するため、墓主にとってお墓の維持管理への負担が大きいものです。
行政手続きの他、定期的な墓地の掃除は広く大きく、代行を依頼してもそれなりの経済的負担がかかります。
さらにコンクリート造りの大きな沖縄のお墓は、修理修繕費用もままなりません。
そこで沖縄の改葬では、納骨堂や手元供養が注目されています。
①納骨堂
②手元供養
納骨堂や手元供養を選択することで、墓じまいをしてお墓を持たず、けれども楽に予算も抑えながら、遺骨を残して供養できるためです。
新たに個別墓を建てなくても、納骨堂や手元供養を遺骨の行く先として選ぶことで、比較的手ごろな価格帯で、個別に供養できるでしょう。
沖縄の改葬①納骨堂
◇「納骨堂」とは、屋内で遺骨を安置する施設です
「納骨堂」では、遺骨を収蔵する屋内施設で、ロッカーのように並ぶロッカー型や、仏壇に祀る仏壇型など、いくつかの種類があります。
なかでも個別の参拝スペースに案内され、自動的に遺骨が搬送される「自動搬送型(ビル型)」納骨堂は、お墓と同じように丁寧な参拝や法要ができると人気です。
契約した一定年数は個別に遺骨が残るので、将来的に遺骨の継承も可能です。
一定年数が過ぎると合祀墓に合祀されますが、契約期間内に更新できる施設が多いでしょう。
| <沖縄の改葬①納骨堂> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・自由 (将来的な引き取りも可) |
| ②新しい墓石 | ・なし |
| ③墓所 | ・処分 |
| ④古い墓石 | ・撤去(処分) |
| ⑤遺骨 | ・納骨堂に収蔵 ・年間管理料が必要 ・個別安置は一定年数のみ ・契約更新あり ・一定年数後は合祀 |
ただし納骨堂も一般墓に永代供養を付加したものと同じく、遺骨を個別に安置できるのは、契約時に提示された一定年数です。
この契約年数以内に契約更新をしないと、そのまま納骨堂の個別スペースは閉じられて、遺骨は施設内の合祀墓(永代供養墓)に、他の遺骨とともに埋葬されます。
また個別に遺骨が安置されている期間は、年間管理料が発生する施設が多いです。
沖縄の改葬②手元供養
◇「手元供養」とは、自宅で遺骨を保管管理し、供養することです
「手元供養」とは、遺骨を納骨せずに、自宅で安置し供養することを指します。
自宅に小さな祭壇を設けて祀る自宅供養の他、ネックレスのペンダントトップなどに小さい遺骨を入れて持ち歩く手元供養などもあるでしょう。
手元供養を選ぶ場合、沖縄で門中墓からの改葬により取り出した遺骨は、専門業者により洗浄され細菌やカビを死滅、充分に乾燥した後にパウダー状に粉骨される流れが一般的です。
| <沖縄の改葬:手元供養> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・自由 (将来的な継承も可) |
| ②新しい墓石 | ・なし |
| ③墓所 | ・処分 |
| ④古い墓石 | ・撤去(処分) |
| ⑤遺骨 | ・自宅 (持ち歩くなど) |
手元供養に掛かる費用は千差万別です。
遺骨を骨壺ごと、もともとある仏壇の近くに祀る人もいますが、この場合は特別な費用は掛かりません。
ペンダントトップなど約3千円ほどのものもあれば、上質なコンパクト仏壇に遺骨を祀るならば数十万円掛かるケースもあるでしょう。
自宅で複数の遺骨を祀る「自宅墓」とは
◇「自宅墓」とは、先祖代々の遺骨など複数の遺骨を収蔵した仏壇です
霊園や寺院墓地など屋外にお墓を持たずに、家族や先祖代々など、複数の遺骨を自宅に保管し、管理、遺骨供養した仏壇を「自宅墓」と言います。
手元供養は一般的に、遺骨を2mm以下の粉状に粉骨してコンパクトにした後、小さな骨壺に収蔵し祀りますが、自宅墓では粉骨した遺骨を本型の桐箱などに収蔵し並べるスタイルが一般的です。
| <沖縄の改葬:自宅墓> | |
| [対象] | [扱い] |
| ①継承 | ・自由 (将来的な継承も可) |
| ②新しい墓石 | ・なし |
| ③墓所 | ・処分 |
| ④古い墓石 | ・撤去(処分) |
| ⑤遺骨 | ・自宅に保管 ・家族で管理、供養 |
墓じまいで取り出した遺骨の粉骨は、専門の業者に依頼すると良いでしょう。
手元供養を扱う仏壇仏具店や、散骨業者などに相談すると、遺骨の手入れや洗骨、粉骨などを受けてくれる業者を紹介してくれます。
専門の粉骨業者により粉骨し、真空パックにまとめられた後、自宅墓用の「ブック型遺骨箱」に収蔵するでしょう。
遺骨は埋葬許可証を保管していれば、いつでもお墓に納骨できますし、夫婦など身近な家族では、一緒に棺に入れて火葬する事例もあります。
埋葬許可証が無くならないよう、遺骨箱に一緒に保管しておくと便利です。
まとめ:沖縄では改装後の遺骨の行く先が大切です

沖縄では改葬とひと口に言っても、門中墓やさまざまな今に残るしきたりも散見されるため、それぞれの問題や状況により、墓じまい後の遺骨の扱いには、いくつもの種類があります。
特に沖縄では他県とは違う、さまざまな改葬理由があります。
・コンクリート造りのお墓を、墓石造りにする
・負担の大きい個人墓地から、霊園へ引っ越す
・辺境にある古いお墓を、近くへ移す
墓主が高齢になっていて、継承者がいない現代の沖縄では深刻な問題です。
現代では墓主本人が、次の世代に問題を持ち越さぬよう、沖縄では改葬や墓じまいを決断するパターンが増えています。
・墓じまいを進める9つの流れとは?ステップごとの費用目安やかかる日数、墓石や遺骨は?