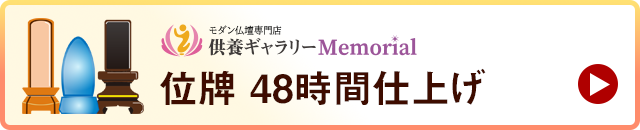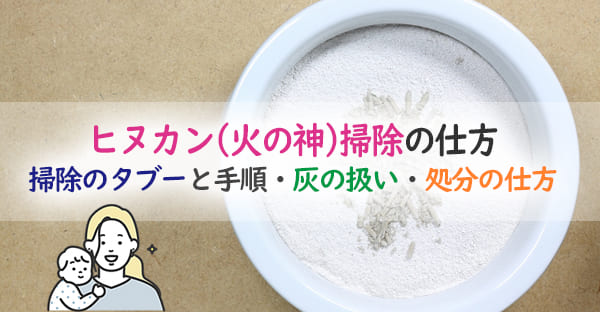沖縄では独自の御願文化があり、「おりんは必要?」と感じる方が多いですよね。ただ最近ではコロナ禍で不安定な状況のなか、心に安定を求めて新しく祭壇・仏壇・仏具を仕立てる家も多く、迷う方も多いです。
確かに沖縄の御願の仕方では、あまりおりんは登場しませんが、日々沖縄の暮らしで御願事を行う時、おりんを用いる方も多くいます。
今、新しく祭壇や仏壇、仏具を整える際、沖縄で御願事のためにおりんまで揃えるかどうかは、おりんの役割を理解することで判断できるのではないでしょうか。
今回は、沖縄の御願事にはあまり用いないおりんの役割についてお伝えします。
お倫の3つの役割

特定の寺院で信徒になる檀家鮮度が根付いていない沖縄では、独自の御願文化の元、おりんを鳴らす習慣はあまりありませんが、全国的にはお仏壇を揃える時に必須となる仏具です。
私達も家で自由に過ごしていると、人が訪ねて来て玄関前でじーっと立っていても、なかなか気付きませんよね。そのため生きる人々の家にはチャイムがあります。
このチャイムと同じように、ご先祖様や神様へ拝む時にも、まずは「お忙しいところ失礼します、これから拝み(お供養)をさせていただきます。」のような、ご挨拶の感覚で、日々の拝みのなかでは、沖縄の御願でもおりんを鳴らす方は多いです。
【 沖縄の御願におりんは必要?3つの役割とは 】
● このようなご先祖様や神様、仏様への「チャイム」としての役割の他、仏教の教えのなかでは、下記のような3つの役割を示しています。
(1) 読経や拝みのグイス(祝詞)を始める、終える合図(リズムを取る)
… 仏教であれば読経の時、最初と最後に節目として鳴らす役割です。沖縄で拝みのグイス(祝詞)になります。
(2) ニライカナイまで拝みが届く
… 「この世」にはないニライカナイ(極楽浄土)は、言葉ではなく、音の周波数のようなもので届けると言われ、沖縄の御願ではおりんなど、周波数が良く響く音に乗せて、イチミ(生きる身)の想い(祈願事)を届けるとされてきました。
(3) ヤナムンやマジムンを祓う
… おりんが放つ周波数により、周囲のヤナムン(邪念や邪気)、マジムン(魔物など)を祓う役割を果たします。読経の前に場の空気を清らかにする目的で鳴らすイメージです。
また、沖縄では成功した時に周囲の嫉妬や噂から己を守るよう、「口難(くちなん)外し」の御願があるように、生霊(いきりょう)の存在も信じられていますが、この生霊も、沖縄の御願ではおりんを鳴らすことで、立ちどころに消えるとされてきました。
おりんの多くが「レ」の音を示していますが、この「レ」はお経と調和が取れやすく、読経の練習やリズム取りとしても役立てられています。
沖縄の御願でおりんを鳴らす注意点

このように、主には「これから読経を唱えますよ(沖縄では御願のグイス)。」とおりんを鳴らす流れです。
そのため清明祭(シーミー)など、沖縄の年中行事において、主にお仏壇やヒヌカン(火の神様)のお世話を担っていない家族であれば、沖縄の御願文化において、おりんの役割があまりピンと来ないのかもしれません。(あまり読経は行わないので…)
そこで、日常の拝みではいくつかの注意点もあります。
【 沖縄の御願でおりんは必要?注意点 】
● このような役割を示すおりんですから、いつでも気軽に鳴らすものでもありません。
→ 例えば、うさぎむん(お供え物)を供えたり、毎朝のご飯やミジトゥ(お水)、ウチャトゥ(お茶)の取り替え、お線香を上げる(読経やグイスなしに)時など、こまめにおりんを鳴らす様子を見受けますが、本来はそれほど頻繁に鳴らさないものです。
先ほど自宅の玄関に例えましたが、神様仏様・ご先祖様にとっても同じと考えてください。のんびり自宅でくつろいでいるのに、ピンポンピンポンとせわしなく鳴らされていたらどうでしょう…。
悪気のない行為であれば怒ることはないとは言え、オオカミ少年ではないですが、「ああまたか…。」と捉えて、大切なメッセージや祈願を行う時まで、あまり心に留めずに流されてしまうかもしれません。
● また沖縄の御願ではおりんを鳴らす時、あまり乱暴に強く鳴らさないようにしてください。
おりんを鳴らす音には気持ちをニライカナイへ伝える役割があると伝えましたが、その振動によるメッセージは、とても細かいところまで伝わるとされています。
おりんの種類と鳴らし方

沖縄の御願においておりんの鳴らし方はごく自由です。前述したように特定の寺院や宗旨宗派の檀家(信徒)になっている方は少ないので、独自の沖縄の御願文化に基づき、おりんを鳴らしているためです。
ただ「お倫に気持ちを込めて(メッセージを周波数に乗せて届ける気持ちで)」3回・もしくは2回を、拝みの最初と最後にならすとされています。
【 沖縄の御願におりんは必要?宗派で違う鳴らし方 】
● ただ仏教においては宗派によって鳴らし方が違ってきますので、下記を参照してください。
(1)臨済宗 … おりんを鳴らす回数は3回
(2)真言宗 … おりんを鳴らす回数は2回/最初は柔らかく鳴らす
(3)天台宗 … 拝みの最初に2回、お経の終わりに1回、全ての読経終了で3回
(4)曹洞宗 … おりんを鳴らす回数は3回、もしくは内側から鳴らして2回(※)
(5)浄土宗 … おりんは読経時のみ鳴らすため日ごろは必要なし(※2)
(6)浄土真宗 … 浄土真宗でも普段はおりんを鳴らしません。
(7)天台宗 … 読経の最初に2回、お経の終わりに1回、全ての読経終了で3回
(8)日蓮宗 … 日々のお世話のなかで朝に1回、夕方に2回
…以上の違いがあります。沖縄では臨済宗の寺院が多いため、沖縄の御願文化でもおりんを鳴らす場合には、3回、もしくは真言宗に倣い2回を鳴らす家が多い傾向です。
ただし、一定の宗旨宗派の檀家(信徒)である家は少ないので、門中や家、地域によって違うでしょう。拝みの最初に2回、拝みの区切りで1回、全ての拝みを修了で3回などの家も見受けます。
(※)曹洞宗は寺院によって鳴らし方が異なる傾向にあり、内側から鳴らす寺院も多いです。また(※2)浄土宗や浄土真宗では読経や座禅による勤行(ごんぎょう)を重要視しているため、おりんは鳴らしません。
読経の時には「八下(はちさげ)」と呼ばれるおりんの八回打ちが行われます。
※ 沖縄の御願で選ぶお倫の種類や選び方については、別記事「沖縄の御願でおりんは必要?揃える理由や役割、おりんの種類や選び方まで解説!」に詳しいです。
いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の御願では少ないおりんについて、沖縄で祭壇や仏壇・仏具を新調する時に必要なのか、おりんの役割や鳴らすタイミングなどについてお伝えしました。
沖縄では葬儀や法要、お仏壇を仕立てる時にも開眼供養が行われるなど、仏教ととても近しい関係にはありますが、本州のように特定の寺院や宗旨宗派を信仰する文化はありませんから(檀家制度)、必ずしもおりんが必要とは限りません。
けれどもおりんの役割を深く知ると、「沖縄の御願でもおりんを取り入れたい」と、購入する家が多い傾向にあります。
新しく仏壇を仕立てる時に揃えて購入する仏具については、別記事「沖縄の仏壇で揃える仏具には何が必要?仏壇仕立てで一緒に購入したい基本の仏具」に詳しいです。
まとめ
おりんを鳴らす3つの役割
(1) 拝みを始める、終える合図
(2) ニライカナイまで拝みが届く
(3) ヤナムンやマジムンを祓う●おりんはむやみに鳴らさない