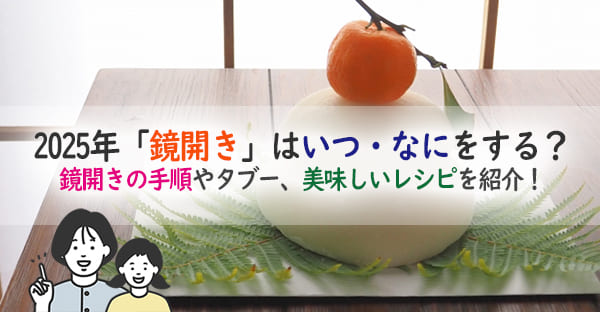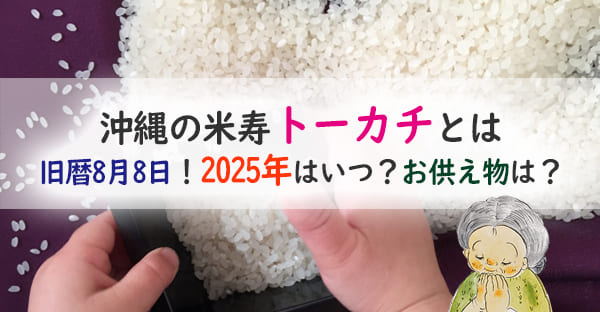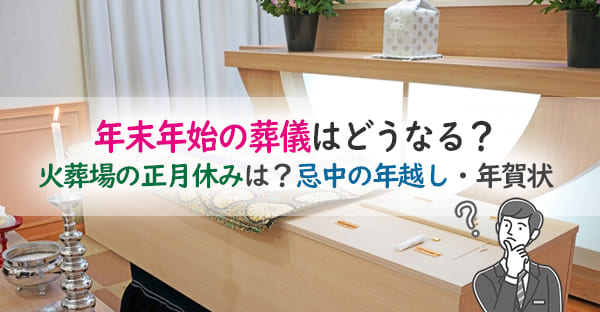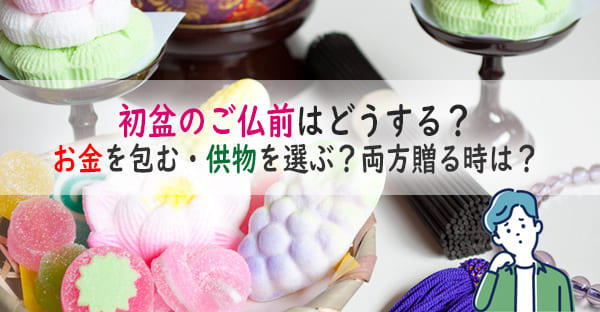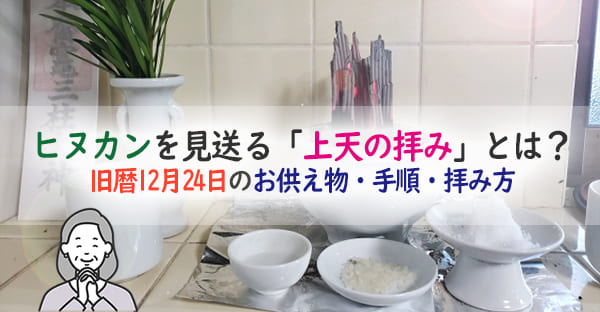「鏡開きって、どんな行事?」
「2025年の鏡開きはいつ?」
「鏡開きでは何を、どのように行うの?」
お正月の「鏡開き」とは、お正月に年神様が宿っておられた鏡餅を開くことです。「年神様」とは、その年を司る神様で、家族の一年を守護してくださいます。
本記事を読むことで、鏡開きとは何か?2025年鏡開きの日程や、正しい鏡開きの行い方やタブー、鏡開きを済ませた後のお餅を美味しくいただく5つのレシピが分かります。
「鏡開き」とは?

◇「鏡開き」とは、お正月飾りの鏡餅を開くことです。
「鏡開き」とは、お正月に年神様の依り代として祀っていた鏡餅を開き、年神様をお見送りするとともに、家族で鏡餅をいただいて年神様に身に住んでいただく儀式を差します。
日程は全国的に毎年1月11日、地域により異なりますが2025年1月11日(土)です。固くなった鏡餅をいただくため、鏡開きの行事食、お雑煮・お汁粉などにしていただきます。
①鏡開きの目的は?
お正月の間、神様の依り代だった鏡餅を開くと言うことは、年神様をお見送りすることです。年神様をお見送りしながら、この一年の恩恵を授かります。
鏡開きの後、鏡餅を残さずいただくことで年神様のパワーを授かるとともに、新しい1年の無病息災を祈願します。
②お正月の締めくくり
鏡開きは鏡餅を片付けること、正月飾りを片付けて元旦から続く正月祝いを締めくくりましょう。
正月元旦~1月7日までは正月を祝う期間「松の内」です。1月8日に正月飾りを片付ける家もあります。鏡開きでは、片付けた正月飾りを処分する地域もあるでしょう。
正月終わりは「鏡開き」だけ?

◇正月の締めくくりは、鏡開き・小正月・二十日正月があります。
鏡開きに鏡餅を下げますが、年神様が家に滞在する「松の内」明けが鏡開きです。なかには1月15日の小正月、1月20日の二十日正月など、正月の祝い納めに合わせて鏡開きを行う地域もあります。
【1月11日】一般的な鏡開き
関東地方・東北地方・九州地方など、全国的な鏡開きが1月11日です。1月11日を鏡開きとする地域では、多くが松の内を1月7日までの「松七日」としています。
松七日が明けた翌日にあたる1月8日に正月飾りを片付けて、1月11日の鏡開きに地域や寺院・神社で開催する「とんど焼き」などに参加して、正月飾りのお焚き上げをしてきました。
【1月4日】松四日
京都の一部地域では、正月期間が4日間となる「松四日」の風習があります。全国的な松七日が松四日になるので、正月飾りの片付けは1月5日です。
けれども鏡開きは1月11日とする地域が多く、お焚き上げ行事も1月11日に行う地域が多くあります。
【1月15日】小正月の鏡開き
関西地方では正月祝いの期間を1月15日までとする地域があります。1月15日は「小正月」です。かつて元旦から働いていた奉公人、家事を担う女性が休みをいただく日でした。
また月の暦で数える旧暦1月15日は満月、正月が明けて初めて訪れる満月の日です。
関西地方では多くの地域で、小正月を正月祝いの節目として、正月飾りを片付けるとともに鏡開きを行う風習があります。
【1月20日】二十日正月の鏡開き
最終的な締めくくりとされる日が1月20日の「二十日正月」です。関西地方の一部地域では、この二十日正月を鏡開きとする地域があります。
お正月にいただくおせちは日持ちが良く、長くいただけるものばかりでした。けれども二十日正月の時期には食べられなくなります。
おめでたい正月料理の残して福が漏れぬよう、骨汁などにして全ていただく風習がありました。鏡餅も開いた後に雑煮やお汁粉にしていただきます。
【旧暦1月14日】旧暦小正月
旧正月を祝う沖縄では、新正月に飾った鏡餅やしめ飾りなどの正月飾りを、旧暦1月14日まで飾り続ける家も多くあるでしょう。
特に新正月と旧正月が近い年には、ずっとしめ縄が玄関に飾られる家を多く見かけます。沖縄で正月飾りを片付ける締めくくり、鏡開きは旧暦1月14日の旧暦小正月とする地域が一般的です。
鏡開きはお正月だけ?

◇結婚式でも「鏡開き」を行います。
日本式の結婚式や祝賀会など、お祝いの席でも鏡開きを行うでしょう。けれどもこの「鏡開き」は、酒樽を木槌で開き、お酒をいただく儀式です。
正月明けに鏡餅を開く「鏡開き」とは、目的や役割が違うのでご注意ください。
①お祝いの「鏡開き」とは
お祝いの「鏡開き」とは、酒樽を木槌で開くことです。開いた酒樽のお酒は皆で分け合っていただきます。
神様への供物であったお酒は、その表面の様子から「鏡」と言われてきました。「鏡」は神道において神様の象徴であり、見る人の心や全てを映し出します。
鏡開きは開業祝いなど、新しい門出を祝う祭典で行う儀式ですよね。酒樽を木槌で割り現れたお酒をいただくことで、神様の恩恵をいただくことが目的です。
鏡餅を開く「鏡開き」の行い方

◇鏡開きは木槌を用います。
鏡開きで用いる道具は木槌です。鏡餅は依り代として年神様が宿っていますので、大切に扱わなければなりません。
ここでは分かりやすいよう、時々「割る」の言葉を用いていますが、本来は鏡餅は開くものです。縁起が悪いため「割る」「切る」の言葉もタブーになるのでご注意ください。
①鏡開きの準備
鏡開きにあたり、新聞紙と木槌を準備します。大きな木の板(まな板)などがあると木槌で叩きやすいですね。木の板(まな板)の上に新聞紙を敷き、その上で鏡開きを行います。
また、手がすべると木槌がぶつかって危険です。濡れ布巾を用意して、布巾の上に手を置いて手の位置を固定します。
・新聞紙
・大きな木の板(まな板)
・小豆缶など
鏡開きの後にお餅をいただくため、小豆缶などお汁粉やお雑煮の材料も用意しましょう!
広間や庭に新聞紙を広げて行いましょう。鏡餅を開く時には木槌も必要です。神様が宿る鏡餅を開くのに包丁は失礼にあたります。「縁を切る」として忌まれるため、木槌を用意しましょう。
②鏡餅を開く
鏡餅はお正月の期間中、飾っているため乾燥が進みカチカチですよね。突然二つに開こうとするのは危険が伴います。
鏡餅を開く時には乾いた鏡餅のヒビ割れたところから、少しずつ優しく叩くと開きやすいです。あまり強く叩かずに、少しずつ叩きましょう!
ヒビ割れたところから徐々に細かく割れて行くので、小分けにすると最初からひと口大が小さくなり調理がしやすいです。
鏡餅は残さず全ていただくとされるため、新聞紙に落ちた細かな部分まで取っておいて調理をします。
③鏡餅を柔らかくする
長く飾られてきた鏡餅は固くなっているでしょう。固い部分は水に約4時間~5時間浸して柔らかくします。ひと晩水に浸ける家も多いです。
鏡餅に包丁は使用できないので、柔らかくなったお餅は手で千切って食べやすいサイズに小さく分けます。
鏡開きトラブルQ&A!

お正月の間、ずっと飾っていた鏡餅は固く、木槌で叩いても開きにくいですよね。鏡開きでは、鏡餅が充分に乾燥していないと、木槌で叩いてもなかなか割れません。
充分に乾燥させて、ヒビに向かって叩くと開きやすくなります。そのため鏡開きの前に、充分に風通しの良い場所に置いてヒビ割れるまで乾燥させると、より開きやすくなるでしょう。
②木槌がない!
鏡開きの道具は「木槌」ですが、一般家庭にはなかなかありません。また鏡餅はなかなか固いので、近年では金槌を用いる家庭も多いでしょう。
鏡開きは縁起行事なので金槌をあまり良しとしませんが、もしも金槌しかないのであれば新聞紙やビニールで包むと良いでしょう。鏡餅に金属の付着も防ぐことができますね。
③固くて開かない!
充分に乾燥させてヒビ割れ箇所から木槌で優しく叩くことで、一般的な鏡餅は開いていきますが、それでも硬くて開かないこともありますよね。この場合は冷蔵庫にひと晩入れておくことで、より鏡餅を乾燥させて開きやすくできます。
また、反対に柔らかくして手でちぎる方法も良いでしょう。鏡餅を半日掛けて水に浸し、手でちぎると適度な大きさに分けやすいです。
すぐに鏡餅を手でちぎるくらいまで柔らかくしたい場合には、ラップを掛けた耐熱容器で温める方法もあるでしょう。
④細かな部分はどうする?
年神様の依り代であった鏡餅には福が宿っています。残さずいただくことで福を授かることができるので、細かな部分までいただきましょう!
木の板(まな板)や新聞紙の上で開くと、細かな鏡餅のカスも集めやすくなります。汁物だと細かなお餅までいただきやすいので、お雑煮やお汁粉として調理してはいかがでしょうか。
鏡開きのタブーとは?

お正月期間中、年神様が宿っていた鏡餅は年神様の象徴です。そのため鏡餅をいただいて、年神様の恩恵を受け取ることができます。
お正月の間は年神様に家族とともに過ごしていただき、お正月明けに鏡餅を家族でいただいて初めて、恩恵を授かることができるでしょう。
①包丁で切る
鏡開きでは、包丁を使いません。包丁で鏡餅を開いてしまうと年神様に刃物を向ける失礼な行為になるためです。
鏡開きで包丁を使い神様へ刃物を向けることで、今年一年の年神様とのご縁も切れてしまいます。せっかくの福が享受できないので、木槌で優しく叩きましょう。
またかつての日本では、刃物で鏡餅を切ることは「切腹」を連想する忌む行為としても避けられてきました。
②「割る」「切る」
年神様が宿る鏡餅を開く「鏡開き」では、「割る」「切る」などの言葉がタブーです。包丁を用いない風習とも似ていますね。
「割る」「切る」と言うことば自体が、縁起が悪い神様に失礼な言葉ですので、正月祝いの期間は使用しないように心がけましょう。
③鏡餅を食べない
鏡開きで開いた鏡餅は、家族で余すことなく全ていただきます。食べ残しを捨てることは、一年を守護する年神様を捨てる行為になるとして、避けられてきました。
鏡餅の細かなかけらにも神様が宿っているとされます。鏡餅をいただかない・残すことは神様の恩恵を無視することに繋がるので、小さな部分まで上手にいただきましょう。
④感謝を述べない
鏡開きの後、お雑煮やお汁粉で鏡餅をいただく時には、食事のご挨拶が欠かせません。日頃から「いただきます」「ごちそうさま」とご挨拶をすることは大切ですよね。
鏡開きでは年神様を今年も無事に迎え入れ、もてなすことができた幸せに感謝を捧げます。また福徳を持って訪ねてくださった年神様へ感謝のご挨拶をして、有難く鏡餅をいただきましょう。
⑤開いた鏡餅の美味しい食べ方は?
◇代表的な鏡開きの料理は、お雑煮やお汁粉です
昔ながらの代表的な鏡開きレシピと言えば、お雑煮やお汁粉でしょう。固くなったお餅も汁でふやかしていただくことで、柔らかくいただけます。
また乾燥してカチカチになったお餅は、昔からおかきになりますね。乾燥して別れた層から手でちぎり、小さく分けるのがポイントです。
鏡開きの行事食として定番のお雑煮・お汁粉の他にも、近年では鏡餅料理のアレンジがたくさん紹介されています。
餅を豚肉で包んだ餅の肉巻きは人気メニューのひとつです。この他、洋風の鏡餅料理では、グラタンにお餅を入れた餅グラタンなども美味しくいただけます。
下記より開いた鏡餅を美味しくいただけるレシピ、定番のお雑煮・お汁粉と併せて5品をご紹介しますので、どうぞ参考にしてください。
鏡開きレシピ(1)お雑煮

お雑煮は好みの具材でお吸い物を作り、お餅を加えるだけです。好みの具材と出汁で作ったお吸い物に、お餅を加えるだけなので鏡開きの行事食としても定着しています。
お正月と同じ具材でも良いですが、お餅と根菜類の相性が良いため、大根や里芋、こんにゃくなどを入れたごった煮が人気です。
【お雑煮の材料】
ひと口大に切り分けた鏡餅6個ほど、6人分の材料です。根菜類の里芋や大根が人気ですが、ほうれん草などの葉物を使うと、より早く調理できます。
基本的に家族が好きな具材を入れるだけで良いのですが、ここでは一般的なお雑煮の食材をご紹介します。
・切り分けた鏡餅…約6個
・にんじん
・里芋
・大根
・椎茸
・こんにゃく
・油揚げ
【味付け】
(味を見ながら調整)
・かつお出汁…約1000ccほど
・醤油 …約大さじ2
・白出汁…適量(小さじ1)
・みりん…約大さじ1
【仕上げ】
・小口ネギ
沖縄ではたっぷりのかつお節でかつお出汁を取り、お水代わりに使用しますが、かつお出汁を取らない時には、市販のかつお出汁を白だし同様に、適量加えて味を整えると良いでしょう。
①下準備
にんじん・里芋・大根・椎茸・こんにゃくは賽の目切りに、油揚げは短冊に切ります。鍋にはかつお出汁・醤油・白出汁・みりんを入れて沸騰させましょう。
②具材を煮る
かつお出汁・醤油・白出汁・みりんを入れて沸騰させた後、中火にします。ここににんじん・里芋・大根・椎茸・こんにゃく・油揚げの具材を入れて、柔らかくなるまで弱火~中火で煮ていくのみです。
③お餅を入れて仕上げる
野菜が柔らかくなったら、お餅を入れます。一度火を止めお餅を入れたら、柔らかくなるまでそのまま待ちましょう。火を入れて沸騰してしまうと、お餅が溶けてしまいかねません。
鏡餅のお餅は固いため中まで柔らかくなるように、お雑煮の汁ができたら火を止め、低温で時間を掛け、お餅が柔らかくなるまで放置します。
お餅が充分に柔らかくなったらお椀に盛り、彩りとして小口ネギを散らすと見栄えも良いでしょう。
鏡開きレシピ②お汁粉

鏡開きの後お汁粉を簡単に作りたい時には、茹で小豆缶が便利です。加糖の茹で小豆缶であれば、甘味も充分に整っているでしょう。
市販の茹で小豆缶でも一層美味しく仕上げるためのポイントは、適量のお塩です。味を整えながら一つまみほど加えます。
【お汁粉の材料】
鏡餅がまだまだ固く大きい状態であれば、少し細かくすると食べやすいでしょう。ジップロックなど丈夫な袋に入れて、めん棒などで叩きながら細かくすると、細かな欠片まで余すことなく、調理できます。
・切り分けた鏡餅…約3個ほど
・茹で小豆缶…1缶(約200g缶)
・水…1カップ
・塩…適量
こしあん・粒あんはどちらでも良いですが、小正月・二十日正月の鏡開きは厄祓い行事にもなるので、小豆が残る粒あんがおすすめです。小豆の赤が邪気を祓ってくれます。
①下準備
小豆缶で作るお汁粉は簡単なので、固い鏡餅を柔らかくするのみです。耐熱容器に水を少々入れてラップをした後、600Wの電子レンジに1分ほどかけると柔らかくなるでしょう。
電子レンジは熱のまわりにムラがあるので、前日から水に浸けて柔らかくしても構いません。好みの固さになるよう、少し電子レンジにかける程度です。
②お汁粉を作る
茹で小豆缶と水1カップを鍋に入れて、中火にかけましょう。時々木じゃくしで混ぜながらに立たせます。
③餅を入れる
お汁粉に充分火が通ったら、鍋の火を止めてお餅を入れます。
ごく弱火でお餅の中まで柔らかくなるよう約5分ほど温めますが、柔らかくなると鍋の底にお餅が付きやすくなるため、木じゃくしで混ぜながら温めると良いでしょう。
弱火にかけて味を見ながら塩を振り、調整しましょう!お餅が鍋の底につかないよう混ぜながら、柔らかくなるまで待ちます。お餅が柔らかくなったら、器に盛り付けて完成!
【小豆から作るお汁粉】

◇小豆から作る場合は小豆:砂糖の分量は1:1の甘さが一般的です。
家族4人分を想定すると小豆250gに対して砂糖250g、お塩をひとつまみほど入れながら味を調整しましょう!
最初にたっぷりの水で小豆を強火にかけ、沸騰したら灰汁を取りながら強火のまま7分です。煮汁は捨てて、灰汁を抜きましょう。ザルに開けると茹で小豆が仕上がります。
さらに小豆の4~5倍量の水で小豆を煮ます。最初は強火にして沸騰したら中火、途中で差し水をしながら灰汁をこまめに取ることがポイントです。指で潰せるほどまで約1時間煮込みます。
・ たっぷりの水で小豆250gを強火にかける
・ 沸騰したら強火のまま7分煮る(灰汁取り)
・ 小豆をザルに開ける
・ 再び小豆を4~5倍量の水で煮る
・ 強火で沸騰させる
・ 中火にして約1時間煮込む(灰汁取り)
・ 数回に分けて砂糖250gを加える
・ 焼いた鏡餅を入れる
最後に砂糖を数回に分けて加えて甘味調整です。木じゃくしで混ぜながら砂糖を少しずつ加えていきましょう。最初に砂糖を加えてしまうと、小豆が柔らかくならないのでご注意ください。
鏡開きレシピ(3)おかき

鏡開きで乾燥しきった鏡餅は、おかきが簡単です。乾燥しきってカピカピになった鏡餅なら、揚げておかきにしてしまいます。
日持ちのするお菓子に生まれ変わるので、残りは脂分を吸うキッチンペーパーにくるんだ後、ジップロックに入れて保存すると良いでしょう。
【おかきの材料】
鏡開きの開き方同様、風通しが良く涼しい場所に保管してヒビが入るまで待つ地、層に分かれてバラバラになりやすい部分から、手で分けて行きます。
乾燥を急ぐならば暖房器具などの前に置いておくのもおススメです。
・切り分けた鏡餅
・揚げ油
・塩など
目安としては約1~2cm角くらい、小さく分ける方が食べやすいでしょう。ヒビ割れたところから細かくしていくので、形状はざっくばらんです。
①低温で揚げる
フライパンに油を入れて揚げますが、120℃ほどの低温でじっくりと揚げていきます。油の温度が120℃になったら、鏡開きで開いた鏡餅を投入します。
10分くらい黄金色に鏡餅が色づくまでじっくりと待ちながら、揚げましょう!動かすとしてもフライパン全体を揺らす程度です。
②ひっくり返す
鏡餅の片面が黄金色に色付いたら返します。さらに両面が黄金色に色付いたら、バットに上げましょう。揚げている内に鏡餅が膨らんで、出来上がった頃にはサクサクに仕上がります。
熱いうちに塩などで味付けをして充分に冷めたら完成です!昔ながらの鏡開きおかきは塩味ですが、コンソメや青のり、カレー粉などを掛けて味付けしても美味しいです。
鏡開きレシピ(4)餅の肉巻き

現代、鏡開きレシピとして人気が出ている料理が餅の肉巻きです。鏡餅を豚バラ肉に撒いて、甘辛タレで焼き上げます。
フードスペシャリストの池田美希さんが、東海テレビの番組「スイッチ」で紹介したことがきっかけで広がりました。肉巻きおにぎりのお餅バージョンで、おかずとしてもいただけます。
【餅の肉巻きの材料】
池田美希さんのレシピでは醤油とみりんの甘辛タレとなっていて、気軽に作るには日本蕎麦や素麺で使う「つゆの素」を使っても簡単に作れます。
・切り分けた鏡餅…約6個ほど
・豚バラ薄切り肉…約280g
・薄力粉…適量
・塩コショウ…適量
・油…適量
【味付け】
・醤油…大さじ2
・みりん…大さじ2
・酒…大さじ2.5
味付けはコンソメや、塩コショウで炒めてポン酢でも美味しくいただけます。ご家族の好みで味付けを変更しても美味しいでしょう!
①下準備
お餅に豚バラ肉を敷き、塩コショウを振りかけます。お餅を棒状に並べると巻きやすいでしょう。細かなお餅を一列に並べても良いでしょう。豚肉を手前からくるくると巻いてお餅を包んだら、薄力粉をまぶして下準備です。
②餅の肉巻きを焼く
フライパンに油を入れて熱した後、下準備を済ませた肉巻きのお餅を並べて中火にかけます。約5分~7分焼くと焼き色がついて美味しそうに焼きあがりますよ!
美味しそうに焼きあがったところで、キッチンペーパーで拭き取る要領でフライパンの油を取ります。
③タレを絡める
醤油・みりん・酒を器に入れて混ぜた「タレ」をフライパンに回し入れて絡ませましょう!タレを回し入れた後、フライパンをゆするように絡めたら完成です。
【肉巻きアレンジは自由自在!】

豚バラの薄切り肉で具材を巻き、つゆの素などの甘辛タレで煮付けるレシピは、他のさまざまな具材にも使えます。
お餅の他にも、チーズや千切りキャベツを巻き付けるレシピも人気です。さまざまな具材を巻き付けてバリエーションを豊かにしても、家族で楽しめるでしょう。
鏡開きレシピ(5)餅入り豚汁

豚汁に餅を入れただけの簡単メニューもおすすめです。
お雑煮よりもカジュアルな鏡開きレシピが「餅入り豚汁」、特に沖縄では豚肉料理が人気なので、全国的には「餅入りけんちん汁」が定番ですが、沖縄では「餅入り豚汁」を作る家庭も増えました。
【餅入り豚汁の材料】
出汁の素は白出汁で良いですが、アゴなど魚系や昆布系の出汁はコクがでます。たっぷりのかつお節で煮出したかつお出汁を、水代わりに使用するのも良いでしょう。
・切り分けた鏡餅…約3個ほど
・豚バラブロック…約120g
・大根 …約1/4本
・にんじん …小1/2本
・椎茸 …約4個
・豆腐 …約半丁
・練り物 …約1個~半分
・ニンニク …約1片
【味付け】
・味噌…約大さじ2
・水…約3と1/2カップ
・出汁の素…小さじ2
・しょうがチューブ…小さじ1
・輪切り鷹の爪…適量
・ごま油…適量
豚汁は具材や味付けが家庭によっても違うでしょう。ここでは一般的な豚汁でご紹介していますが、家庭ごとに親しみのある具材を入れて楽しんでください!
①下準備
豚バラブロック拍子切りで切り分けると美味しいです。大根・にんじんはいちょう切りだと縁起物としても良いでしょう。
椎茸は1/4ほどの大きさ、練り物は食べやすい大きさに細かく切ります。豆腐は大きめの賽の目切り、ニンニクは潰しておきます。
②具材を炒める
鍋にごま油を敷き熱したところに豚バラを入れて、弱火で炒めましょう。根野菜中火は中火で炒めます。
③汁を作る
分量の水(約3と1/2カップ)・椎茸・潰したニンニクを入れて煮立たせ、沸騰させたところで灰汁を取りましょう!
灰汁が取れたら一度火を泊めて、出汁の素・しょうがチューブ・輪切り鷹の爪・ごま油を入れた後、豆腐も加えて弱火にかけます。弱火で15分~20分ほどじっくり煮込んだ後、味噌を溶いて味の調整です。
⑤鏡餅を加える
最後にお餅を投入しふたをしながら弱火で3分ほど煮ます。火を止めてお餅が充分に柔らかくなったら完成です。
お餅は豚汁を作った最後に加えます。お餅が大きめで固いようならば、雑煮同様に一度火を止めて鏡餅を投入し、じっくりと中が柔らかくなるまで待つのも良いでしょう。
まとめ:2025年の鏡開きは1月11日(土)です

全国的に違いはありますが、一般的な鏡餅の日程は毎年1月11日、2025年は1月11日(土)となります。
現代の鏡開きが広く1月11日となったのは、古くは江戸時代が起源です。もともとは正月最後の締めくくりとされる、1月20日の二十日正月に鏡開きを行ってきました。
けれども江戸幕府三代将軍家光の忌日と重なったため、1が並び縁起が良い1月11日を鏡開きと改めた歴史があります。
そのため1月11日を鏡開きとする地域は特に関東地方に多い傾向で、関西地方の一部では小正月の1月15日や二十日正月、京都の一部では松の内を3日とし、4日には鏡開きを行う地域もあるほどです。
年神様が宿り恩恵をいただく鏡餅、ぜひ家族で美味しく調理をして家族団らん、楽しみながらいただいてみてはいかがでしょうか。