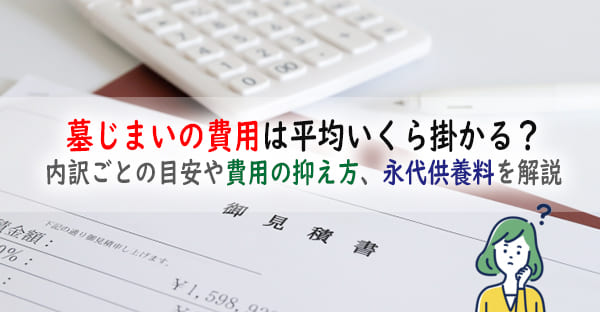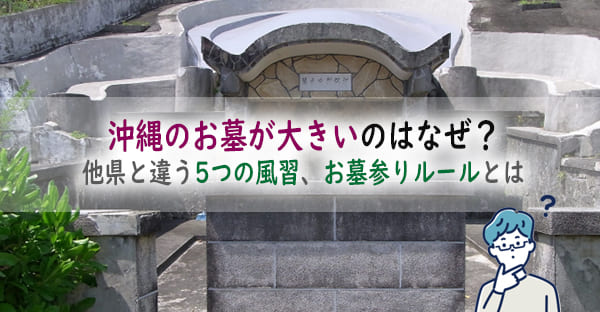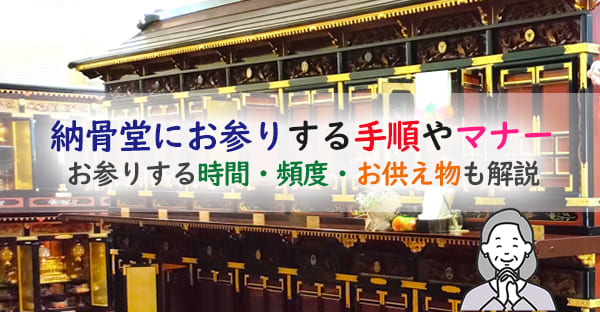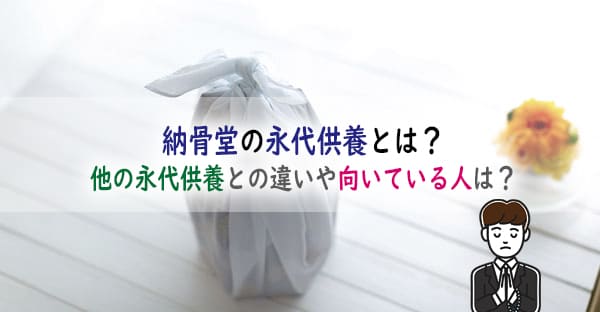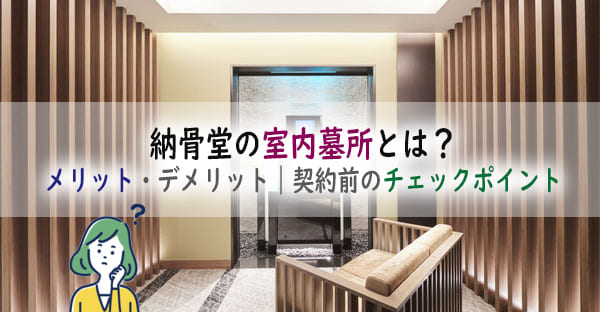・墓じまいの流れは?
・墓じまいをするには、どうしたらいい?
・墓じまいの流れごとに掛かる費用は?
墓じまいの流れは、まず墓じまいで取り出した遺骨の新しい納骨先を決めることから始まります。
行政手続き上スムーズに進むだけではなく、経験豊富な新しい納骨先が心強いサポーターになってくれるためです。
本記事を読むことで、墓じまいを進める9つの流れやステップ、それぞれの段階での費用目安や、墓じまいに掛かる日数やおすすめのタイミング、墓じまい後に墓石や遺骨がどうなるか?まで分かります。
墓じまい9つの流れとは?

◇墓じまいとは、現存のお墓を撤去して墓地管理者に返還することです
「墓じまい」とは、現存のお墓から遺骨を取り出した後、墓石を撤去して墓地を更地とした後、霊園など墓地管理者へ永代使用権を返還することを指します。
①親族で相談する
②埋葬証明書をもらう
③受入証明書をもらう
④石材業者に依頼する
⑤改葬許可証をもらう
⑥閉眼供養を執り行う
⑦遺骨を取り出す
⑧墓石の撤去、返還
⑨新しい納骨先へ納骨
墓じまいそれぞれの流れについては、下記より詳しく解説します。
沖縄では個人墓地が多いですよね。
個人墓地の墓じまいの流れは、遺骨を取り出してお墓を閉じ、墓地を廃止する手続きを取ることで、法的には土地の売買が可能です。
・個人墓地の墓じまいとは?無許可墓地の問題点とは?墓じまい後の個人墓地は売却できる?
①親族で相談する
◇墓じまいをするとお墓がなくなるため、親族には最初に相談をしましょう
墓主として自分の世代で墓じまいを決めた場合、お墓の名義人である墓主は独断で行政手続きができますが、後々になって心情的なトラブルが起こらぬよう、最初に親族相談をします。
①お墓の管理や供養が負担になっている現状を伝える
②墓主を他の人に託せないかを尋ねる
③墓じまいを検討している旨を伝える
④墓じまいによるメリットを伝える
⑤墓じまい費用の分担などを相談する
他の親族に伝えずに墓じまいを進めてしまうと、その後トラブルに発展しかねません。
不要なトラブルを避けるために、親族から墓じまいに関する同意を得ておきましょう。
また墓じまいをするには、それなりの費用がかかります。
親族間で話し合う際は、墓じまいにかかる、費用やその後の供養方法について話し合いましょう。
・墓じまいの費用は平均いくら掛かる?内訳ごとの目安や費用の抑え方、永代供養料まで解説
②埋葬証明書をもらう
◇現存の墓地管理者から「埋葬証明書」をいただきます
「埋葬証明書」とは、墓地に遺骨が収められていることを証明するものです。
墓じまいは勝手にできるものではなく、遺骨を取り出すにあたり、お墓が建つ自治体の役所窓口で改葬許可申請をした後、改葬許可証をもらいます。
・「墓じまい」は民間から発生した言葉で、行政手続き上では「改葬」です。
・「改葬(かいそう)」とは、お墓や遺骨を引っ越すことを指します。
この改葬許可申請で提出する書類のひとつが、埋葬証明書です。
墓地の管理は、寺院墓地、公営・民間霊園、共同墓地で管理者はそれぞれ異なります。
| <墓地の種類と埋葬証明書の発行場所> | |
| [墓地の種類] | [入手先] |
| ①寺院墓地 | ・ご住職 |
| ②公営墓地 | ・自治体 ・墓地管理事務所 |
| ③民間霊園 | ・霊園管理事務所 |
| ④共同墓地 | ・管理組合 ・地域の代表 ・役所など |
ただし、昔からある地方の共同墓などになると、墓地によって誰が管理しているのかが分からない場合があります。
また、沖縄の個人墓地の場合、すでに墓主が亡くなって長く、誰が名義人であるか分からなくなっているケースもあるでしょう。
このように、墓地の管理者が不明な場合は、自治体に問い合わせると確実です。
③受入証明書をもらう
◇墓じまいでは、新しい納骨先を先に決めるとスムーズです
墓じまいをすると、まずお墓から遺骨を取り出さなければなりません。
取り出した遺骨は刑法190条により、法的にも放置したり勝手に処分できないため、何らかの方法で供養をします。
●行政手続き上、改葬許可申請書には新しい納骨先を記載し、新しい納骨先の墓地管理者から発行された「受入許可証」とともに提出しなければなりません。
ただ改葬先によって費用が大きく異なりますし、改葬方法によっては親族から反対意見が出る可能性もあるので、ここでは慎重に考える必要があります。
下記は、取り出した遺骨の新しい納骨先と、費用目安です。
| <新しい納骨先と費用目安> | |
| [納骨先] | [費用目安] |
| ①一般墓 | ・約100万円~300万円 (平均…約175万円ほど) |
| ②合祀墓 (永代供養墓) | ・約5万円~150万円 (平均…約10万円ほど) |
| ③納骨堂 | ・約10万円~150万円 (平均…約60万円ほど) |
| ④散骨 | ・約5万円~50万円 (平均…約15万円ほど) |
| ⑤樹木葬 | ・約20万円~80万円 (平均…約25万円ほど) |
| ⑥手元供養 | ・約5万円~30万円 (平均…約15万円ほど) |
取り出した遺骨の新しい納骨先は、いずれも供養の手厚さや施設の質などにより、費用幅があります。
散骨や樹木葬などの自然葬は近年注目される供養方法ですが、納骨後も手を合わせたい、個別に遺骨を遺したいなら納骨堂が良いなど、ニーズに合わせた選択が、後々まで後悔しないポイントです。
・墓じまい後の永代供養とは?取り出した遺骨の供養5つの方法、メリットデメリットも解説
・刑法(明治四十年法律第四十五号)
④石材業者に依頼する
◇石材業者を決めて、遺骨の取り出しや墓石の撤去を依頼します
霊園に建つお墓の墓じまいでは、墓石を撤去した後に更地にして、元の状態に戻してから返還しなければなりません。
個人墓地であっても墓じまい後に土地を売買したいならば、墓地を廃止するため、更地にしなければならないでしょう。
そのため墓石を解体・撤去し、お墓を更地にして返還します。
・昔からおつきあいのある石材業者
・墓地・霊園と提携している石材業者
・複数の石材業者を相見積もりをして決める
ただし墓地によっては、提携していない石材業者だと作業ができない規約もあるので、まず墓地管理者に確認をすると良いでしょう。
また石材業者の目当てがない場合は、複数の石材業者に相見積もりを出します。
墓じまいの工事費の相場は約10万円/1㎡ですが、山奥に墓地があるために重機を使えず、思わぬ追加料金が発生する可能性もあるでしょう。
⑤改葬許可証をもらう
◇埋葬証明書、受入許可証とともに、改葬許可申請を行います
石材業者や墓地管理者へ「改葬許可証」を提出するのが、遺骨を取りだす墓じまいの流れです。
お墓のある自治体の役所に改葬許可申請書を提出します。
今ではホームページで改葬許可申請書がダウンロードできる役所もあるので、予め確認を取ると良いでしょう。
| <改葬許可証の発行に必要な書類> | ||
| [書類] | [発行元] | [内容] |
| ①埋葬証明書 | ・現在の墓地管理者 | ・お墓に埋葬されている故人を証明 |
| ②受入証明書 | ・新しい墓地管理者 | ・遺骨の受け入れを許可を証明 |
| ③改葬許可申請書 | ・お墓がある市区町村 | ・お墓の移動許可を申請する書類 |
自治体によっては改葬許可申請書と受入証明書が一体化しているものもあるので、最初に改葬許可申請書を入手しておくと、後々の手続きがスムーズです。
⑥閉眼供養を執り行う
◇「閉眼供養」とは、現存のお墓から魂を抜く儀式です
「閉眼供養」とは、お墓から魂を抜く仏教儀式で「魂抜き」とも呼ばれます。
お墓には先祖の魂や仏様・自然霊が宿っているとされ、閉眼供養を行うことで、お墓から物としての「墓石(石材)」へ変わるためです。
寺院墓地であれば寺院のご住職に依頼し、民間霊園や公営墓地であれば、墓地管理者やインターネットなどで僧侶を手配して以来します。
・墓じまいでの閉眼供養とは?お布施の金額相場や準備、当日の流れや服装、お供え物を解説
⑦遺骨を取り出す
◇遺骨を取り出した後、状態によっては手入れも行います
お墓の開閉や遺骨の取り出しは、自分達でできないこともないですが、墓石は重いので石材業者に依頼するのが一般的です。
お墓には約6柱~8柱ほど収蔵できるスペースがあり、遺骨を取り出す追加費用は約3万円~5万円ほど掛かるケースもあるので、最初に確認すると良いでしょう。
また長期間お墓に納められていた場合、溶解やカビの発生など、メンテナンス作業が必要になる遺骨が多くあります。
| <遺骨の取り出し> | |
| ①遺骨の取り出し | …約3万円~5万円/1柱ほど |
| ②遺骨の手入れ | …約2万円~3万円/1柱ほど (洗骨の場合) |
| ③遺骨の搬送 | ・送骨サービス…数万円 ・ゆうパック…約1,0000円/1柱 ・自分で移動…0円 |
一般的には車や電車などを利用して、自分達で遺骨を移動しますが、遠方で遺骨を郵送する場合、日本郵便「ゆうパック」のみが受け付けてくれます。
送骨サービス業者も見受けますが、数万円掛かることが多いでしょう。
⑧墓石の撤去、返還
◇お墓は墓石の撤去後、墓地は更地にして返還します
墓石の解体や撤去は、石材業者に依頼をします。
一般的にはお墓を購入した石材業者に依頼したり、霊園などであれば墓地管理者に紹介してもらい、依頼をすることが多いです。
前述したように、目当てがない場合は自分達で複数の石材業者に相見積もりを取り、比較検討をして依頼をします。
また墓石解体の専門業者に依頼することもあるでしょう。
霊園・寺院墓地の場合、指定石材業者があるケースもあるため、まずはお墓がある墓地に確認をします。
⑨新しい納骨先へ納骨
◇新しい納骨先へ遺骨を納骨して終了です
墓じまいで取り出した遺骨は、新しい納骨先に納骨供養して終了します。
墓じまいでは、お墓の維持管理が困難であったり、後々の継承者がいないなどが背景にある家が多いため、一般的には墓主や継承者を必要としない「永代供養」を選ぶ人が多いでしょう。
●「永代供養(えいたいくよう)」とは、家族に代わり墓地管理者が遺骨の管理や供養を永代に渡って行ってくれると言う、形のないサービスです。
そのため永代供養の形はさまざまで、他の遺骨と一緒に合祀埋葬される合祀墓(永代供養墓)の他、納骨堂や個別墓による永代供養もあるでしょう。
永代供養の形により、墓じまいの費用総額も大きく変わります。
詳しくは、下記コラムをご参照ください。
・墓じまいの費用は平均いくら掛かる?内訳ごとの目安や費用の抑え方、永代供養料まで解説
墓じまいでの行政手続きの流れ

◇墓じまいの行政手続きは、改正許可申請です
墓じまいは沖縄の個人墓地であっても、遺骨を取り出すため、勝手に自分達で進めることはできません。
遺骨を取り出す際に、お墓のある自治体から「改葬許可証」をもらうため、市町村役場の窓口で改葬許可申請をします。
●まず、自治体の役所で「改葬許可申請書」を手に入れましょう。
・市町村役場の窓口(お墓のある自治体)
・ホームページでダウンロード
注意点として、改装許可申請書は遺骨の数だけ提出しなければなりません。
例えば門中墓に8柱の遺骨があった場合、8枚の改葬許可申請書が必要です。
また、もし墓主(お墓の名義人)と改葬許可申請をする人が異なる場合、墓主による「承諾書」が必要です。
※使用者自身が申請する場合、承諾書は必要ありません。
①埋葬証明書をもらう
◇現存のお墓がある墓地管理者から「埋葬証明書」を入手します
自治体により改葬許可申請書の書類形式はさまざまです。
そのため、なかには墓地管理者から埋葬証明書を発行してもらい、そのまま提出する墓じまい手続きの流れもありますが、埋葬証明の欄が設けられた改葬許可申請書も見受けます。
| <埋葬証明書をもらう> | |
| ①埋葬証明の欄がある | ・署名・捺印をもらう |
| ②埋葬証明書の提出 | ・墓地管理者より証明をもらう |
| ③個人墓地の場合 | ・墓地名義人(墓主)より証明をもらう |
自治体によっては、「埋葬証明書」を使うこともあるため、事前に確認が必要です。
また沖縄では墓主が墓地を所有する個人墓地が多いですが、沖縄では多くの自治体で、個人墓地の地図を提出します。
②受入許可書をもらう
◇遺骨の新しい納骨先から、受入証明をしてもらいます
受入証明も、改葬許可申請書に受入証明の欄が設けられている自治体があるので、この場合には新しい納骨先の墓地管理者に署名・捺印をしてもらうと良いでしょう。
| <受入証明書をもらう> ●受入証明が必要のない自治体もある | |
| ①受入証明の欄がある | ・署名・捺印をもらう |
| ②受入証明の提出 | ・墓地管理者より証明をもらう |
| ③受け入れ先がない | ・役所に相談する |
ただ改葬許可申請書に納骨先の情報を記入するだけで改葬許可申請ができて、受入証明が必要ない自治体もあります。
また手元供養や散骨など、墓じまいで取り出した遺骨の新しい納骨先がない場合、空欄で提出しても良い自治体も多いです。
新しい納骨先がない時には、役所窓口で相談して指示を受けましょう。
③改葬許可申請を行う
◇改葬許可申請の書類を揃えたら、いよいよ申請です
埋葬証明書、受入証明書などの書書類一式を揃えたら自治体の窓口に提出します。
この場合、身分証明の提示が求められるのは墓主(お墓の名義人)ではありません。
改葬許可申請に訪れている人の身分証明が一般的です。
④改葬許可証をもらう
◇改葬許可証は石材業者や新しい納骨先で提出します
改葬許可申請書の提出から、改葬許可証が発行されるまで、約3日~1週間ほどの期間がかかる場合があるでしょう。(土・日・祝日を除いた日数)
改葬許可証は墓じまいで遺骨を取り出す際に、石材業者に提出するものです。
また取り出した遺骨の新しい納骨先にも、改葬許可証を提出します。
①石材業者
②新しい納骨先
③散骨業者など
また自然葬で遺骨を埋葬供養しない散骨業者などでも、現代では改葬許可証の提出が求められ、提出できない場合は受け付けない業者が多いです。
そのため墓じまいの行政手続きと、石材業者とのスケジュール調整を同時に行っているならば、工事日程は余裕をもって予約しなければなりません。
墓じまい手続きの流れで困ったら?

◇墓じまいの手続きで困ったら、まず窓口に相談すると良いでしょう
ひと昔前まで、墓じまいで取り出した遺骨は、お墓や永代供養墓に埋葬されました。
けれども現代では、新しいお墓や永代供養墓以外にも、遺骨を供養するにあたり、さまざまな選択肢が増えています。
・散骨
遺骨を埋葬・収蔵しない墓じまいが始まったのはごく最近です。
そのため改葬許可申請などの行政手続きが、その新しい供養方法に対応していない自治体も少なくありません。
墓じまい手続きの流れで困ったことがあれば、まず窓口で相談しても良いでしょう。
①個人墓地の場合
◇墓地の名義人である墓主が、埋葬証明を行います
沖縄に多い個人墓地だけではなく、全国的にも昔からある敷地内や、個人が所有する山の中などにあるお墓などは、埋葬証明に戸惑う墓主も多いです。
個人墓地では多くの場合は墓地管理者も個人にはなりますが、墓地の名義人(墓主)が、埋葬証明書を発行したり、捺印・署名を行います。
…自治体に所有者を確認すると良いでしょう。
古い門中墓や共同墓など、墓地管理者が不明なお墓があった場合、「みなし墓地」として自治体が運営者となっている場合もあるためです。
②風葬や土葬の遺骨があった
◇風葬や土葬の遺骨は火葬が必要なケースがほとんどです
お墓に古い風葬や土葬による遺骨があった場合にも、墓じまい手続きが必要です。
ただ、もし遺骨が完全に土に還っているなど、遺骨を取り出すことができない状態だった場合には、改葬許可申請は必要ありません。
| <風葬や土葬の遺骨> | |
| ①遺骨を移動できる | ・改葬許可証をもらう ・火葬許可証をもらう ・火葬をする ・新しい納骨先に納骨 |
| ②遺骨を取り出せない | ・改正許可申請は必要ない |
また現代の日本では火葬を済ませていない遺骨は、新たに納骨・埋葬することは許可しない墓地がほとんどです。
そのため改葬許可申請を行う際、一緒に火葬許可証ももらいましょう。
火葬を経て、新しい納骨先に納骨します。
③お墓に遺骨がない場合
◇まだ納骨していないお墓の墓じまいは、特別な手続きは必要ありません
まだ遺骨が埋葬されていないお墓の墓じまいでは、そもそも遺骨を取り出し移動する必要がないため、改葬許可申請や閉眼供養を行わなくても良いでしょう。
ただしお墓を建てた時、魂を入れる開眼供養を済ませていたお墓には、閉眼供養が必要です。
| <お墓に遺骨がない> | |
| ①開眼供養をしていない | …閉眼供養も行わない |
| ②開眼供養をしている | …閉眼供養は行う |
お墓に遺骨がなくても開眼供養を行ったことで、お墓に魂が宿ります。
開眼供養と閉眼供養は対になっているので、建てた時の法要に倣うと良いでしょう。
④手元供養の場合
◇受入証明書がないことを、役所窓口で相談しましょう
散骨や手元供養では、取り出した遺骨の新しい納骨先がないため、受入証明書がありません。
多くが手元供養や自然葬など、新しい供養の形に、墓じまいの行政手続きの流れが追い付いていないことが理由なので、何らかの対策を取ってくれる人が多いです。
⑤遠方でお墓に行けない場合
◇遠方にあるお墓の墓じまいでは、書類を郵送しても手続きができます
もし墓地が遠方にある場合、改葬許可申請に必要な書類を、郵送で送付しても問題ありません。
・別途返信用の切手を同封する
・改正許可申請の手数料を定額小為替で同封
改葬許可申請書は大切な書類ですので、普通郵便ではなく書留で送付すると安心です。
改葬許可申請書は自治体により形式が異なりますが、お墓のある自治体で改葬許可申請書をダウンロードできるホームページも多いです。
・那覇市:改葬許可申請
墓じまいの流れごとの、費用相場は?
◇墓じまいの費用相場は、総額約30万円~300万円ほどかかります
「墓じまい」とは、お墓を撤去するだけではなく、取り出した遺骨を何らかの方法で供養するまでが墓じまいになるため、遺骨の供養方法により費用幅が広いです。
墓石の撤去、墓地の返還のみであれば、石材業者に支払う約20万円~30万円や、僧侶へのお布施などで収まりますが、取り出した遺骨は何からの方法で供養をしなければなりません。
①新しい納骨先の費用相場
◇新しい遺骨の納骨先へ支払い…約10万円~100万円
墓じまいで取り出した遺骨は一般的に永代供養されますが、永代供養の選択肢によって費用幅が広いです。
最も安く収まる遺骨の納骨先は合祀墓(永代供養墓)で、約3万円~30万円ほど/1柱で収まります。
ただ一方で、合祀墓(永代供養墓)では遺骨を骨壺や骨袋から出して、他の遺骨と一緒に合祀埋葬されるため、一度埋葬されると二度と取り出すことはできません。
| <新しい納骨先への費用相場> ●約10万円~100万円ほど/1柱 | |
| [供養方法] | [費用相場] |
| ①個人墓 | ・約50万円~200万円ほど/1柱 |
| ②合祀墓 | ・約3万円~30万円ほど/1柱 |
| ③樹木葬 | ・約30万円~100万円ほど/1柱 |
| ④納骨堂 | ・約30万円~100万円ほど/1柱 |
永代供養は形のないサービスなので、一般墓にも付加することが可能です。
そして後から遺骨を個別に取り出すこともできますが、墓石が建つため費用も割高になるでしょう。
供養する方法によって、必要な金額だけでなく、埋葬方法も変わってきますので、慎重に検討した上で決めることが重要です。
②石材店に支払う費用相場
◇墓石解体費用の相場は約8万円~15万円ほどです
墓石の解体費用は、区画の広さや撤去する墓石の量、使用できる機材によって異なる場合がありますので、お墓の規模が大きい場合は15万円以上かかることもあります。
また墓地や墓地区画の立地や環境により、重機が必要になるなど追加料金が発生することもあるので、まずは墓石業者に内部調査を依頼するなどして、現地を見てもらいましょう。
③お布施の費用相場
◇閉眼供養のお布施相場は、約3万円~10万円です
お墓から遺骨を取り出す際、僧侶による閉眼供養が行われます。
閉眼供養は僧侶に読経供養を依頼して行われる、正式な法要です。
墓じまいで包むお金の平均費用は、約3万円~10万円ほど/1柱ですが、寺院墓地にお墓が建つ場合、菩提寺と檀家としてのお付き合いの歴史などにも配慮します。
不安があれば経験の深い年配の親族に聴いたり、僧侶ご自身に「皆様いくらほど包まれているでしょうか?」などと相談するのも一案です。
④行政手続きの費用相場
◇墓じまいの行政手続きは、遺骨1柱ごとに行います
墓じまいの行政手続きの流れで、書類作成に掛かる費用は、約1.500円ほど/1柱です。
ただ墓じまいの行政手続きは、取り出した遺骨1柱ごとに行うため、書類の数も多くなるでしょう。
地域や墓地・霊園によって異なりますので、正確な費用は分かりません。
ただ改葬許可申請に必要な書類に掛かる費用は、約3,000円あれば充分です。
⑤「離檀料」が掛かる場合
◇寺院墓地でなければ離檀料も、一般的にかかりません
寺院墓地の場合、墓じまいは菩提寺から離れる「離檀(りだん)」を意味します。
そのため、今までお墓の管理や供養に対するお礼として、お墓を建てている「檀家(だんか)」はお金を包みますが、これが離檀料です。
公営・村墓地(野墓地)・民間霊園では、そもそも檀家制度がないため連絡だけで済みますが、寺院墓地では離檀トラブルにならぬよう、ご住職への配慮も必要です。
・菩提寺・檀那寺とは?檀家になる・離檀するとは?寺院とのお付き合いで心得るマナーとは
墓じまいの流れをスムーズにするポイント
◇墓じまいでは、最初に内部調査を依頼すると良いでしょう
墓じまいを検討し始めたら、流れとしてまず、石材業者に依頼して内部調査を行っておくと良いでしょう。
お墓の内部調査は墓じまいの流れとして、最初に行う性質のものですが、新しい納骨先を先に決めておくことで、無料で内部調査を受け付けてくれる業者もあります。
| <お墓の内部調査とは> | |
| ①内容 | ・お墓の中を確認する ・遺骨の柱数を確認する |
| ②依頼先 | ・石材業者 ・墓地管理者 (新しい納骨先) |
| ③費用目安 | ・無料 ・約3万円~5万円ほど |
特に沖縄のお墓は古いものも多く、風葬の歴史があったため、前述したように風葬の時代の遺骨が出てくることもあるでしょう。
お墓の内部調査を行うことにより、墓じまい費用の予算立てや、取り出した遺骨の扱いについて早い段階で検討できます。
遺骨の数をご確認する
◇現存のお墓に納骨された遺骨の数を、確認すると動きやすいです
墓じまいで取り出した遺骨の新しい供養先は、納骨堂や樹木葬など、遺骨の数によって決まることもあるでしょう。
特に現代は墓じまいで取り出した遺骨は、後々継承者を必要としない永代供養が一般的ですから、料金体系も1柱ごとの計算です。
また納骨堂や集合墓を選んだ場合、スペースに限りがあるため、予めどのような遺骨が何柱納骨されているのか、把握していると良いでそう。
墓じまいの時期
◇寺院墓地や霊園の繁忙期を避けるとスムーズです
墓じまいの時期は、寺院や霊園の繁忙期を避けると良いでしょう。
お墓の撤去作業が大変になるため、梅雨の時期も避けたいところです。
沖縄では雪は降りませんが、もしも降雪地域での墓じまいがあるならば、雪の多い時期も避けます。
| <墓じまいで避ける時期> | |
| ①寺院や霊園の繁忙期 | ・お盆 ・お彼岸 (春彼岸、夏彼岸) ・お正月 |
| ②雨の多い時期 | ・梅雨 |
また墓じまいは七回忌や三十三回忌など、年忌法要を目安に進める家も多いです。
この場合、墓じまいの相談をしてから約2か月~3か月以上掛かります。
中には数年単位の期間が掛かることもありますので、「〇〇までに墓じまいを済ませたい」などの希望があるならば、スケジュールを逆算して余裕を持って動き出します。
墓地管理者の理解
◇寺院墓地のに建つお墓の場合、ご住職の理解が必要です
沖縄に寺院墓地はほとんどありませんが、もしも寺院墓地に建つお墓の墓じまいであれば、墓地管理者である寺院とは菩提寺と檀家の関係性になるため、民間霊園などよりも慎重にご相談をします。
「菩提寺」とはその墓地にお墓が建っている寺院で、お墓を建てた家は「檀家」です。
菩提寺は檀家の仏事の一切を担います。
①早い段階でご住職に伝える
②閉眼供養は菩提寺に依頼する
③離檀料として多めにお金を包む
寺院墓地の墓じまいで菩提寺から理解を得られず、トラブルに発展してしまうと、お墓から遺骨を取り出して、墓石を撤去する際に必要となる書類「改葬許可申請」に必要な「埋葬証明書」がもらえないトラブル事例などがあります。
代行業者に頼む方法もあります
◇墓じまい代行業者を利用するのも一案です
「墓じまいの流れが分からない」「忙しい」などの場合、墓じまい代行業者に依頼するのもひとつの手段です。
| <墓じまい代行業者の費用目安> | |
| ①すべてを代行 | …約16~30万円 |
| ②行政手続きのみ | …約4万円~ |
| ③墓石の解体・撤去 | …約10~30万円 |
| ④遺骨の取り出し・納骨 | …約7万円~ |
ただし代行業者の種類によって代行できる範囲が異なります。
行政書士が行う墓じまい代行は手続きのみとなる、などです。
門中墓や先祖代々墓の墓じまいの場合、そもそも納骨されている遺骨の柱数が分からないことが多いため、まずは代行業者にお墓の内部調査を依頼すると良いでそう。
墓じまいの流れQ&A

人生のなかで何度も行うことのない墓じまいは、流れが分からず動きが取れない墓主も少なくありません。
具体的な方法が分からないと不安も増えるため、疑問や質問は早い段階で確認しておくことで、墓じまいの予算も立てやすくなります。
①墓じまいの費用総額の平均は?
◇墓じまいの費用総額は、平均で約30万円~300万円ほどです
墓じまいで墓石を撤去するのみであれば、約20万円ほどでできます。
ただ、ご遺骨を放置したり廃棄したりすることは墓埋法では違法です。
行政手続きも含めて、新しい納骨先までのプロセスも墓じまいに含まれるでしょう。
費用相場が幅広いのは寺院へのお布施金額や、新しい納骨先の価格など、状況や選択肢によって異なるためです。
②墓じまいにかかる日数は?
◇墓じまいには、1ヶ月から数年かかることもあります
親族や寺院への相談によって要する日数は、各家庭の事情によって異なります。
親族との意見の相違が深刻だった場合には、話し合いが長引くこともあるでしょう。
また新しい供養先を決める時間も人によってさまざまです。
実際に施設を訪れたり、パンフレットを取り寄せるなど、新しい納骨先を選ぶだけで、数ヶ月の期間を要することもあるでしょう。
③墓じまいで取り出した遺骨はどうする?
◇墓じまいで取り出した遺骨は、永代供養が一般的です
門中墓や先祖代々墓で墓じまいで取り出した遺骨は、複数取り出されるケースは多くあります。
そのため遺骨の供養先として、最も費用が抑えられるため、他の遺骨と一緒に埋葬される「合祀墓」での永代供養墓が選ばれる傾向です。
| <墓じまいの遺骨:新しい納骨先> ●遺骨の性質により、下記2つが多いです | |
| ①合祀墓 (永代供養墓) | …遠いご先祖様 |
| ②納骨堂 ・集合墓 | …身近な家族など |
| ③手元供養 | …夫や妻、子どもなど |
両親や祖父母、妻や夫など、思い出のある故人の遺骨では、納骨堂や集合墓、個別の一般墓などを建てて、個別に遺骨を残す選択もあります。
また夫婦や子どもなどで、より手厚く供養したい人々は、自宅で遺骨を祀り供養する「手元供養」も人気です。
④墓じまいで撤去した墓石はどうなる?
◇現在では多くの墓石がリサイクルされます
撤去された墓石は魂抜き(性根抜き)すると、ただの石材です。
ただの石となり砕石した後、資源としてリサイクルされます。
しかし過去には、不法投棄された墓石が山林で多数見つかった事例がありました。
墓石を責任持って処分してくれる、専門業者を選ぶ必要もあります。
⑤墓じまい後の「永代供養」とは?
◇「永代供養」とは、墓地管理者が家族に代わり遺骨を管理供養することです
「墓じまい」と「永代供養(えいたいくよう)」は異なるものです。
永代供養は形のないものなので、一般墓に永代供養を付けることができる他、納骨堂や集合墓にも、現代では永代供養が付いています。
| <墓じまい・永代供養とは> | |
| ①墓じまい | ・遺骨を取り出す ・墓石を撤去 ・墓地を更地に戻す ・使用権を返還する |
| ②永代供養 | ・遺骨の管理 ・遺骨の供養 |
また合祀墓(永代供養墓)では、他の遺骨と一緒に合祀参租うされ、他の遺骨と一緒に定期的に供養されます。
ただし合祀墓(永代供養墓)に埋葬した遺骨は、一度埋葬すると二度と取り出すことができません。
⑥墓じまいをしなかったら?
◇墓じまいをしないでお墓を放置すると「無縁墓」になります
寺院墓地や民間霊園、公営墓地に建つお墓であれば、お墓を放置して何年も年間使用料やお布施を滞納してしまうことになるでしょう。
●放置されたお墓は年間管理料の未払い状態が続きます。
…そこで一定期間を超えると「無縁墓」として扱われ、強制撤去になるでしょう。
強制撤去されてしまうと、遺骨は縁者がいないとして供養塔で埋葬されます。
沖縄の個人墓地の場合は、放置され続けることで墓地全体がうっそうとしてしまい、時には自治体により強制撤去される事例も多くありました。
⑦墓主がいない場合は?
◇お墓の名義人である墓主は、自治体で調べてみます
墓じまいを行う全ての権限は「名義人」にあるため、まず墓じまいをするお墓の「名義人」を確認してください。
名義人がわからない場合は、現在のお墓がある自治体の役所に問い合わせます。
個人情報に関わるため、必ずしもすべてのケースで自治体が対応するとは限りませんが、ほとんどのケースで対応してくれるでしょう。
まとめ:墓じまいの流れでは、先に納骨先を決めます

スムーズな墓じまいの流れでは、先に納骨先を決めることをおすすめします。
特に沖縄では個人墓地が多いですが、民間霊園などでは墓じまいをまる任せできる「墓じまいパック」の提供も多く見受けます。
墓じまいで取り出した遺骨を想定して、先に新しい納骨先を決めることで、新しい納骨先である霊園などへ、お墓の内部調査や墓じまいパックなど、もろもろを相談できるでしょう。
また閉眼供養を行う僧侶や、墓石の撤去を依頼する石材業者も紹介してくれます。
特に個人墓地に建るお墓の墓じまいでは、新しい納骨先は心強い存在です。