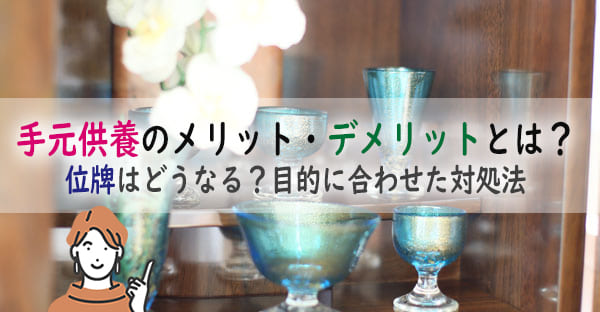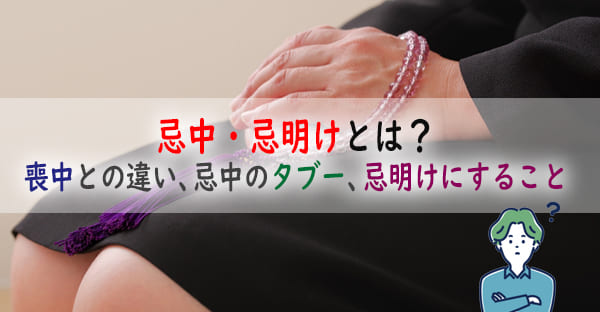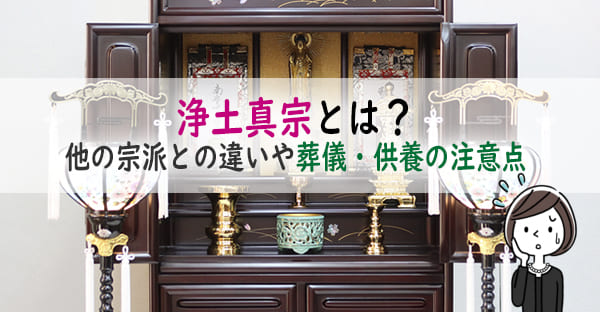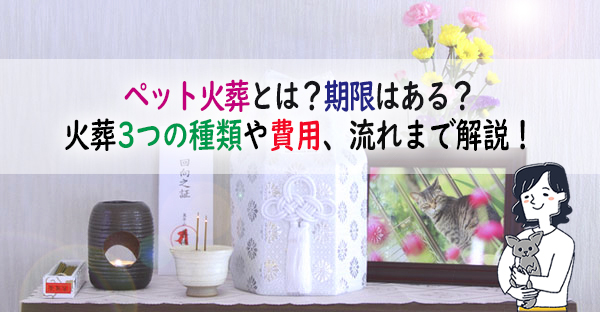・仏壇のお参りは毎日するもの?
・仏壇のお参りで毎日供えるものは?
・仏壇でお参りをする時、お線香は何本?
仏壇へのお参りは毎日、朝と就寝前の朝夕2回行うと良いとされます。
仏壇へのお参りの基本は毎日の「六種供養」、お供え物も「五供」に添うと行いやすいです。
本記事を読むことで、仏壇へお参りする、朝と夕方、毎日の基本の供養「六種供養」と、お供え物「五供」が分かり、心を込めた供養ができます。
後半ではお線香をあげに行く弔問での仏壇へお参りマナーもご紹介するので、どうぞ最後までお読みください。
仏壇のお参りは、毎日朝・夕の2回

◇仏壇のお参りは、毎日、朝と夕方の2回を目安に拝みます
決まり事はないものの家に仏壇がある家でお参りは、朝と就寝前の2回の他、毎日2回~3回、お食事を供える時にお線香をあげて手を合わせる人が多いです。
| <仏壇のお参り:毎日の流れ> | |
| [朝] | ・仏壇の扉を開ける ・乾拭き掃除 ・お供え ・ロウソクの火を消す |
| [昼] | ・仏壇の扉は明けたまま ・いただきものは供える ・手が空いたら乾拭き掃除 |
| [夜] | ・一日の感謝を伝える ・火が消えているか確認 ・扉を閉める |
仏壇へお参りを毎日するにあたり、ロウソクの火だけは注意をします。
ロウソクの火、お線香の火を必ず確認してから、扉の開け閉めをしましょう。
ロウソクの火は火消しの仏具を使用し、お線香は口で吹き消すことなく、手で仰ぐ、シュッとお線香を引き下げるなどして、消します。
仏壇のお参り:毎日の「六種供養」とは

◇仏壇のお参りで毎日行う「六種供養」は、最小限の供養です
沖縄で手元供養を選ぶ方々に広がる日々の拝み「六種供養」とは、全ての宗旨宗派に共通した部分をまとめた、ごく最小限の供養方法を差します。
| <仏壇のお参り:毎日の流れ> | |
| [六種供養] | [方法] |
| ・閼伽(あか) | ・清い水 |
| ・塗香(ずこう) | ・塗り香 |
| ・華鬘(けまん) | ・清い花 |
| ・焼香(しょうこう) | ・お線香 |
| ・飲食(おんじき) | ・お供え物 |
| ・灯明(とうみょう) |
・灯り |
全ての宗旨宗派に共通するため、檀家制度が根付く本州では、菩提寺より離檀して無宗教となった方々が、家族を供養するために行う傾向にあり、拝む人を問いません。
六種供養と六波羅蜜
◇「六波羅蜜」とは、菩薩が行っていた6つの修行です
大乗仏教における、日々の暮らすなかで行う6つの修行「六波羅蜜(ろくはらみつ)」は、六種供養と連動しています。
六波羅蜜は菩薩が如来になるために課せられました。
| <仏壇とお参り:毎日の六波羅蜜> | ||
| [六種供養] | [六波羅蜜] | [意味] |
| ・閼伽(あか) | ・布施(ふせ) | ・施し |
| ・塗香(ずこう) | ・持戒(じかい) | ・戒律を守る |
| ・華鬘(けまん) | ・忍辱(にんにく) | ・忍耐 |
| ・焼香(しょうこう) | ・精進(しょうじん) | ・努力 |
| ・飲食(おんじき) | ・禅定(ぜんじょう) | ・精神統一 |
| ・灯明(とうみょう) | ・智慧(ちえ) | ・悟り |
仏壇へのお参りを毎日行うなかで、仏道の修行「六波羅蜜」を意識することで、毎日の功徳を積むことにもなります。
・【沖縄の春彼岸】仏前で彼岸に行う「六波羅蜜」とは?意味と行い方を分かりやすく解説!
仏壇のお参り:毎日の仕方

◇仏壇へお参りを毎日するなかでは、お供え物とお線香、合掌をします
一般の人々が仏壇へお参りを毎日するなかでは、六種供養を意識しながら、下記の流れでお供養をすると良いでしょう。
(1)お水やお茶の交換
(2)仏飯を供える
(3)お花の手入れ
(4)ロウソクを灯す
(5)お線香を上げる
(6)合掌をする
以上が六種供養の基本ですが、前述したように仏壇へお参りを毎日行うなかでは、朝は扉を開け、就寝前は扉を閉め、日中は手が空いたら掃除をしたり、いただきものを供えるなどするでしょう。
(1)お水やお茶の交換
供えるものはお水やお茶、お酒など何でも構いません。
宗旨宗派がある場合には、そのお茶やお水など上げるお供えが決まっている宗派もあるでしょう。
(2)仏飯を供える
生きている家族がいただく前に、朝一番でご飯をお供えします。
身支度を整えたら、家族が朝食をいただく前にお仏壇に供え、朝食を終えたタイミングで仏飯を下げると良いでしょう。
(3)お花の手入れ
生花は枯れる前に手入れをして交換します。
最近ではブリザーブドフラワーなど、美しいフェイクフラワーも増えました。
ムリのない範囲でお花を供え、手入れをします。
(4)ロウソクを灯す
ロウソクは、マッチやライターから火を灯します。
お線香は、ロウソクから火をいただく方が良いでしょう。
消す時は、仏具のロウソク消しを使うと良いです。
(5)お線香を上げる
◇ロウソクの火から火をいただき、お線香を上げます
お線香の火を消す時は、穢れを避けるため口で吹き消すことは避けてください。
・手で仰ぐ
・シュッとお線香を下げるように消す
宗旨宗派によりお線香の上げ方や本数は異なりますが、毎日のお線香は3本もしくは略式で1本が理想的です。
※お線香の本数について、詳しくは後半で解説します。
(6)合掌をする
◇合掌して拝みます
朝はご挨拶、夜は一日の感謝を述べると良いでしょう。
読経や念仏を唱える人もいますし、沖縄では「ウートゥートゥー」です。
沖縄では馴染みが少ないお倫ですが、お倫を鳴らすことで仏様へのチャイム、合図の役割を果たしますので、鳴らすことをおすすめします。
仏壇のお参り:毎日行う4つの供養

◇仏壇へお参りし毎日供養するためには、「4つの供養」があるとされます
仏壇のお参りは、毎日基本的にこの六種供養で良いのですが、六種供養は六波羅蜜とも関係性が深い、仏道の修行の一環です。
故人へ供養するにあたり、仏壇へお参りする際は、毎日4つの供養があるとされます。
| <仏壇のお参り:毎日4つの供養とは> | ||
| [供養] | [行うこと] | [意味] |
| ●灯り供養 | ・ロウソクを灯す | ・あの世とこの世の道を照らす |
| ●香り供養 | ・お線香を供える | ・仏様の食べ物 |
| ●勧請 (かんじょう) |
・お倫を鳴らす | ・仏様のおいでを願う |
| ●正行 (しょうぎょう) |
・お経や念仏 | ・実践的な修行 |
独自の祖霊信仰を持つ沖縄では、仏教宗派に倣った読経供養や念仏ではなく、ご先祖様や故人へ語り掛けても良いでしょう。
無宗教でも読経や念仏を行いたい時には、観音経や般若心経が多いです。
朝のお参り手順
◇朝起きたら、洗顔や歯磨き等を済ませた後、朝食前に行います
朝に行う仏壇へのお参りは、毎日身支度を整えた後、朝食前に仏様へご飯やお水をお供えし、ご挨拶をする流れです。
| <仏壇へのお参り:毎日の朝> | |
| [扉を開ける] | ・仏壇へ一礼し合掌 ・扉を開ける |
| [お供え物] | ・仏飯を供える ・お水、お茶を取り替え ・お花を整える |
| [お参り(正座)] | ・ロウソクを灯す ・お線香を供える ・合掌 ・お倫を2回鳴らす ・ご挨拶をする (読経や念仏でも良し) ・お倫を2回鳴らす ・合掌 ・ロウソクを消す |
| [お仕舞] | ・ロウソクを消す ・お供え物を下げる(共食後) ・扉を閉める |
朝、朝食前に仏壇のお参りをしたら、家族が朝食を済ませた後に、仏壇のお供え物を下げましょう。
二重扉のお仏壇であれば、内扉のみ閉じます。
お昼のお参り手順
◇お昼に家族が在宅していれば、仏壇の扉は開けてお供えや、簡単な掃除をします
ご先祖様や故人と共に暮らす気持ちで、日中に家族が在宅してれば、仏壇の扉を開けて1日を過ごしながら、いただきものをしたらお供えしたり、手が空いた時に乾拭きなどの簡単な掃除をすると良いでしょう。
| <仏壇へのお参り:毎日のお昼> | |
| [お参り(正座)] | ・仏壇へ一礼 ・いただきものなどをお供え ・ロウソクを灯す ・お線香を灯す ・合掌 ・お話をする (読経や念仏でも良し) ・終わりの一礼 |
仏壇はご先祖様への供養や、仏道の修行としての役割がありますが、何よりも亡き故人と繋がるためのものでしょう。
正しい仏壇のお参りでは、毎日読経や念仏を唱えますが、お供えの時には故人と会話をするように語り掛けます。
夜のお参り手順
◇夜は就寝前、感謝と一日の出来事をお伝えします
仏壇へ夜のお参りは毎日就寝前に行い、今日一日を無事に終えたことへの感謝と、出来事を報告するお参りです。
最後は、朝に開けた仏壇の扉を閉めましょう。
| <仏壇へのお参り:毎日の夜> | |
| [お参り(正座)] | ・ロウソクを灯す ・お線香を灯す ・合掌 ・お倫を鳴らす ・お話をする (読経や念仏でも良し) |
| [お仕舞] | ・お供え物は下げる ・仏壇の扉を閉める |
仏壇が座りながらお参りをする高さであれば、正座をして行います。
近年では立った目線よりも高い位置になる「立ち仏壇」も多いです。
またタンスの上に配置するモダン仏壇や、手元供養もあるでしょう。
このような時には、正座ではなく、立ちながらのお参りでも問題はありません。
仏壇へのお参り:毎日お線香の本数は?

◇お線香の本数は宗派により異なりますが、沖縄では1本~3本です
檀家制度が根付いておらず、独自の祖霊信仰を持つ沖縄でお線香は、3本もしくは1本を目安に供えます。
| <仏壇のお参り:毎日のお線香> | |
| [日本線香] | ・3本、もしくは1本 |
| [沖縄線香] | ・半ヒラ(半分の3本分に割る) |
全国的なお線香の上げ方に倣う場合、仏教宗派によりお線香の本数や上げ方が異なってくるでしょう。
| <仏壇のお参り:お線香の本数> | ||
| [宗派] | [本数] | [あげ方] |
| ●臨済宗 ●曹洞宗 ●日蓮宗 |
・1本、もしくは2本 | ・立てて供える |
| ●天台宗 ●真言宗 |
・3本 | ・立てて供える |
| ●浄土宗 | ・1本 | ・折り立てて供える |
| ●浄土真宗 | ・1本 | ・折り寝かせて供える |
基本的には上記のような違いがありますが、浄土真宗だけでも「真宗10派」があるように、さらにそれぞれの寺院によりしきたりが異なります。
気になる時には、信仰する寺院や菩提寺に確認しましょう。
お倫の鳴らし方
◇お倫は2回鳴らします
沖縄では馴染みがないお倫ですが、仏壇へのお参りを毎日行う時には、最初と最後でお倫を2回ずつ鳴らすと、ご先祖様や故人への合図の役割を果たします。
| <仏壇のお参り:毎日のお倫> | |
| [2回鳴らす] | |
| ・1回目 | …優しく鳴らす |
| ・2回目 | …少し強めに鳴らす |
お倫はいわば玄関のチャイムです。
日中はむやみにお倫を鳴らすことは控え、少し強めに鳴らす程度で、カンカンとけたたましく鳴らすことは避けましょう。
読経や念仏を唱える場合
◇読経や念仏は、信仰する仏教宗派に倣ったものを唱えます
沖縄の仏壇は位牌を中心として飾り、特定の仏教宗派を信仰する家は少ないです。
そのため基本的には沖縄の祀り方で整えますが、特定の仏教宗派に倣った仏壇を仕立てている場合は、唱える読経や念仏も、その宗派に倣います。
・「檀家制度」とは、「戒名」は必ず必要?菩提寺(檀那寺)との関係性
仏壇のお参り:毎日のお供え物は?

◇仏壇のお参りで毎日のお供え物は、「五供」に倣うと良いです
仏壇のお参りを、六種供養で毎日行っていれば、自然と全てのお供え物が整います。
内容はほとんど同じですが、お供え物には五種供養の「五供(ごく・ごくう)」があるので、五供に添っても良いでしょう。
| <仏壇のお参り:毎日のお供え「五供」> | |
| [五供] | [内容] |
| ・水(みず) | ・お水、お酒、お茶 |
| ・香(こう) | ・お線香 |
| ・花(はな) | ・生花、造花 |
| ・灯明(とうみょう) | ・ロウソク |
| ・飲食(おんじき) | ・食べ物、仏飯、果物 |
仏壇へのお参りで毎日供える飲食(おんじき)は仏飯です。
仏飯の他に供える時には、りんごやミカンなどの丸い果物も良いとされます。
季節を感じる果物や生花であれば、尚良いでしょう。
御膳を供える時には、「五供」に倣い陽数とされる5品目が好まれます。
仏壇へのお参り:毎日の合掌

◇沖縄の合掌は、右手よりも左手を少し下に下げます
…右手が神様・仏様、左手は私達自身だからです。
沖縄の合掌は、神様・仏様・私自身を合わせる行為を表します。
合掌により、神様・仏様の境地を体感するとされ、心を静めて精神統一し、誠実に生きることを誓うのが合掌です。
| <仏壇へのお参り:毎日の合掌> | ||
| [手] | [意味] | [行動] |
| ・右手 | …智慧(ちえ) | ・気付き(神様・仏様) |
| ・左手 | …禅定(ぜんじょう) | ・行動(私自身) |
このように合掌は「慧と定をひとつにする」と言われ、神様・仏様からいただいた智慧(気付き)を行動に移し、誠実に生きることを誓います。
まとめ:仏壇へお参りを毎日する際は、六種供養を意識します

仏壇へのお参りを毎日する行為は、故人やご先祖様へのお供養の他、毎日の修行としての役割も持ちます。
ロウソクやお線香、お供えまで、行為ひとつひとつに意味を感じ、意識をしながら仏壇へお参りを、毎日行うと良いでしょう。
お線香を上げに弔問へ訪れる時には、電話で予約をして手土産を持って訪問し、深緑やグレーの落ち着いたおお出掛け着で整えた「平服(ひらふく)」で伺います。
注意点は、座布団を足裏で踏まないよう、両膝から入ることです。
座布団の縁に両膝をのせ、両手をついて中に入るように進みます。