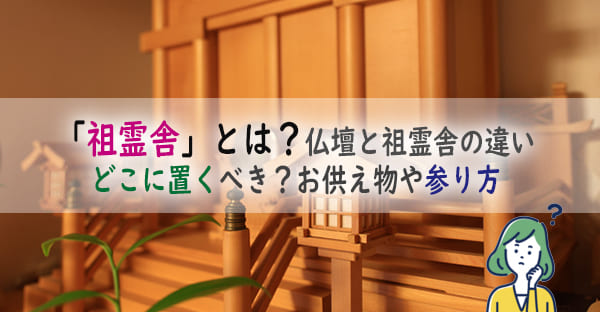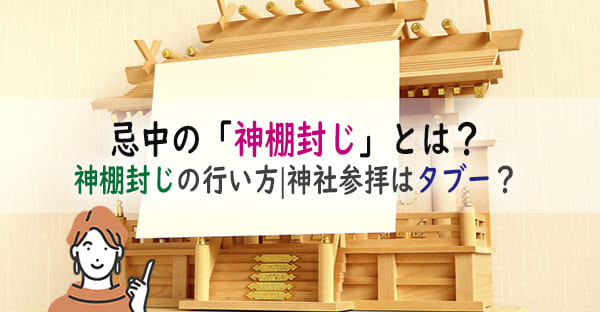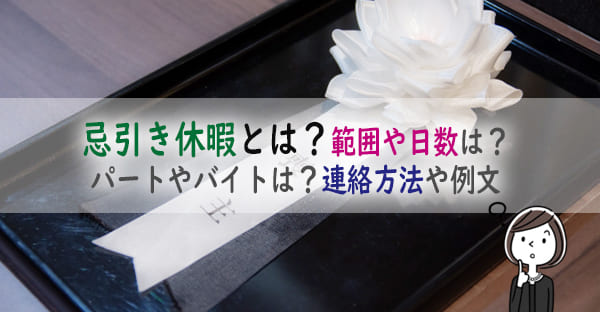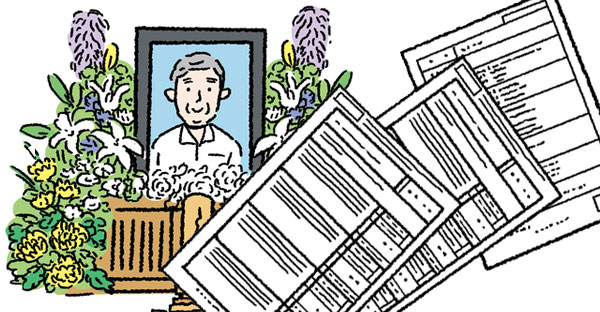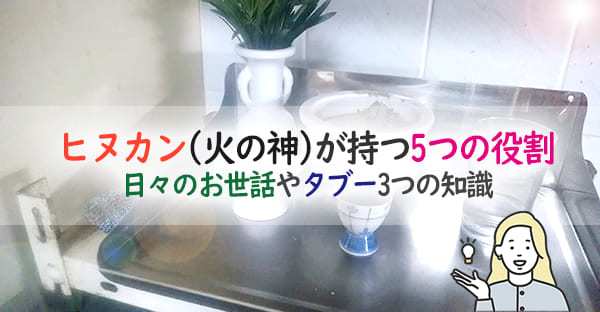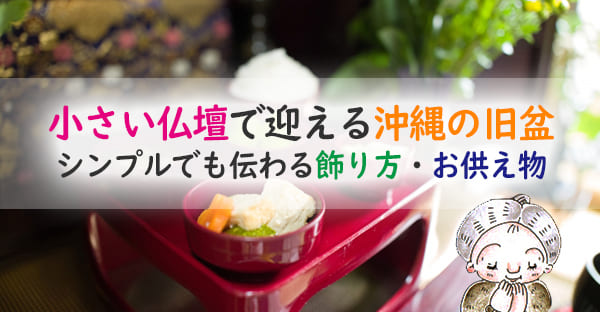・「祖霊舎」とは何?仏壇との違いは?
・祖霊舎の置き方、置き場所は?
・祖霊舎へのお供え物や参拝の仕方は?
「祖霊舎」とは、神道において先祖代々の御霊を祭る社(やしろ)です。
仏教におけるお仏壇と同じ役割がありますが、死生観の違いから、祀る物や祀り方、参拝方法が違います。
本記事を読むことで「祖霊舎」とは何か?
仏壇との違いや祖霊舎の置き場所や方角、祀り方の作法や参拝方法が分かります。
「祖霊舎」とは何?

◇「祖霊舎」とは、神式の仏壇で先祖代々の御霊を祀る社(やしろ)です
江戸時代から民衆が集落の寺院の「檀家」となり、家族の供養祭祀を菩提寺(檀那寺)に託していた「檀家制度」により、現代の戸籍の役割を果たしてきた日本では、多くが仏教に倣い、故人を供養しています。
そのため仏壇が根付いていますが、神道で故人の霊魂を祀る祭壇が「祖霊舎(それいしゃ)」であり、祖霊舎には位牌に代わる「霊璽(れいじ)」を祀ります。
・祖霊舎(それいしゃ)
・御霊舎(みたまや)
・神徒壇(しんとだん)
・祭壇宮(さいだんみや)
祖霊舎は「祖霊舎」の他にも、御霊舎や祭壇宮など、さまざまな呼び名がありますが、いずれも神道の位牌にあたる「霊璽」を祀る祭壇で、仏教の仏壇と同じ役割です。
祖霊舎と仏壇の違い
◇仏壇の中心には御本尊を祀ります
仏壇の中心は御本尊ですが、祖霊舎の中心は仏教の位牌にあたる霊璽です。
沖縄のブチダン(仏壇)も、多神教の神道に考え方が似ているため、中心にはトートーメー(先祖代々位牌)が祀られますよね。
同じように、祖霊舎と仏壇への祀り方の違いは、死生観によるものです。
| <祖霊舎とは?仏壇との違い> | ||
| [違い] | [祖霊舎] | [仏壇] |
| ●祭壇 | ・祖霊舎 (それいしゃ) |
・仏壇 (ぶつだん) |
| ●霊魂の依り代 | ・霊璽 (れいじ) |
・位牌 (いはい) |
| ●祀り方 | ・霊璽のみ | ・御本尊の下に位牌 |
仏壇も祖霊舎も、ご先祖様の霊魂を依り代とした霊璽や位牌を祀るための祭壇ですが、死後の考え方から祀り方が大きく異なります。
仏教では仏壇の中心に宗派に則った御本尊が祀られ、その両脇、一段下の段に位牌を祀りますが、神道では、霊璽のみを中心に祀る形式です。
・「檀家制度」とは、「戒名」は必ず必要?菩提寺(檀那寺)との関係性
祖霊舎と神棚の違いは?
◇祖霊舎はご先祖様が亡くなって守護神となった「祖霊」を祀ります
神棚と祖霊舎では祀る神様が異なり、神棚の神様はより高貴な神様です。
基本的な祀り方や参拝の仕方は変わりませんが、神棚に祀る神様は、格の違う神様とされます。
| <祖霊舎と神棚の違い> | |
| [祖霊舎] | ●霊璽を祀る (ご先祖様の御霊) ・家の守護神 ・祖霊神 |
| [祖霊舎] | ●お神札を祀る (神社の神様) ・格の違う神様 |
そのためもともと神棚がある、祖霊舎がある家でも、霊璽と神社からいただいた「御神札」を一緒に祀ることはタブーです。
ただし祖霊舎と神棚、それぞれの基本的な日々のお世話やお供え物、参拝の仕方は同じように行って良いでしょう。
・「神棚」とは?置く場所・方角|お供え物や日々参拝するときの作法、タブーを詳しく解説
神道とは?仏教との違いは?
◇神道とは、古代日本の信仰に基づいた多神教のひとつです
「八百万の神(やおよろずのかみ)」の言葉から分かるように、神道の神様はお米や水、海まであらゆるものに宿るとされてきました。
人も神道では亡くなると五十日祭の後に、その家を守護する守護神になります。
一方、仏教では人が亡くなると四十九日間の冥土の旅の道中、七か所の関所で生前の罪が裁かれ、次の輪廻「六道」が決まり、御本尊様のお見守りの元で生まれ変わりますよね。
| <神道とは?仏教との違いは?> | ||
| [違い] | [神道] | [仏教] |
| (1)人が亡くなると | ・家の守護神となる | ・輪廻転生する |
| (2)開祖 | ・特定の開祖がない多神教 (八百万の神様) |
・御本尊 (宗派により異なる) |
| (3)故人の霊魂 | ・御霊(みたま) | ・霊 ・仏様 |
神道には得度や洗礼(キリスト教)など、入信のための特別な儀式はありません。
神棚を祀り、祖霊舎を仕立てて霊璽やお札をお祀りし、神道の儀式に倣い日々神棚や祖霊舎のお世話をすることで、神道になります。
また神道は、他の宗旨宗派への信仰にもこだわりません。
日本の仏教が比較的他信仰に対して、比較的寛容な宗教観を持つ理由は、日本古来の多神教、神道に影響を受けたとの一説もあります。
そのため日本では神棚と仏壇、祖霊舎がともに祀ってある家も多くあるでしょう。
祖霊舎を仕立てるには?

◇五十日祭までに祖霊舎を用意し、神職にお祓いをしてもらいます
故人の御霊(みたま)を祀る祖霊舎を仕立てるタイミングは、多くが家族を亡くした時ですので、五十日祭を目安に祖霊舎を購入する家が多いでしょう。
「五十日祭」とは仏教の四十九日法要にあたり、神道では五十日祭を経て、故人の御霊が家を守護する守護神になります。
仏教では四十九日法要を経て成仏し、故人の霊が成仏しますよね。
| <祖霊舎の仕立て方> | |
| (1)神職へ霊璽を仕立てる | ・遷霊祭 (せんれいさい) |
| (2)祖霊舎一式を購入 | ・祖霊舎 ・新具 ・真榊 ・灯篭 ・神鏡 ・榊立て ・白皿(お塩やお米を供える) ・水玉(お水を供える) ・徳利(お酒を供える) …など |
| (3)神職にお祓いをしてもらう | ・五十日祭 |
| (4)祖霊舎へ霊璽を祀る | ・奥の内扉に納める ・内扉は閉める ・外扉は開けておく |
| (5)お供え物を供える | ・お米 ・お塩 ・お水 ・お酒 ・榊 |
| (6)参拝をする | ・二拝二拍手一拝 |
霊璽は多くが、神式の通夜「通夜祭」内で行う遷霊祭(せんれいさい)で、故人の御霊を霊璽に移す儀礼を行い、仕立てます。
冥土の旅がない神道では仏式の「仮位牌」はありません。
この遷霊祭で仕立てた霊璽をそのまま祀ることになるでしょう。
「通夜までに霊璽を用意できない!」と慌てそうですが、霊璽は神職で用意する場合がほとんどです。
霊璽は人目に触れない
◇霊璽を納めた内扉は閉じて、前に神鏡を置きます
神道で神様は見てはいけない存在、故人も家の守護神となるため同様です。
内扉がある祖霊舎では、内扉に霊璽をしまい扉を閉じます。
①最上段の内扉の奥へ納める
②内扉を閉める
③内扉の前に神鏡を置く
また神道では、人が亡くなると「2つの神様」になるとされてきました。
祖霊舎に祀られる霊璽は心を司る神であり、子々孫々を守護する家の守護神です。
| <人が亡くなると2つの神様に分かれる> | |
| (1)心を司る神様 | ・霊璽(祖霊舎) ・家を守護する |
| (2)体を司る神様 | ・奥津城(おくつき) ・お墓に納められる |
神道では死を穢れとするため、神社内に墓地はありません。
宗旨宗派を問わない民間霊園や、公営墓地などで建てられます。
神式のお墓は仏式とは形も彫刻も異なり、お墓の上部「棹石(さおいし)」の上部は三角錐のように尖った「角兜巾型(かくときんがた)」、「○○之奥津城」と彫刻されるお墓です。
・神道のお墓がいらないとは?どこに建てる?納骨やお供え物、参拝の仕方をくわしく解説!
祖霊舎の価格帯は?
◇現代の祖霊舎は上置き型~床置き型までさまざまです
現代の祖霊舎は大きさも上置き型や、おしゃれなリビングにも相性の良い、モダンな祖霊舎も販売されるようになりました。
展開の広がりにより、価格帯もさまざまに分かれます。
| <祖霊舎の価格帯は?> | |
| [祖霊舎の種類] | [価格帯] |
| (1)床置き型の祖霊舎 | ●台座なし…約15万円以上 ●台座あり…約30万円以上 |
| (2)上置き型の祖霊舎 | ・約5万円~10万円以上 (祖霊舎の置台も販売) |
| (3)モダンな祖霊舎 | ・約5万円~10万円 (デザインにより異なる) |
祖霊舎は仏壇のように漆塗りなど色塗りをせず、素地を生かした無垢な白木造りが特徴です。
近年ではコンパクトな祖霊舎が数多く販売され、特にリビングにも配置しやすい壁掛け型も販売されるようになりました。
祖霊舎を置く場所とは?

◇祖霊舎は南向き、東向き、神棚よりも下に置きます
神社の神様の依り代となるお神札を祀る神棚は、祖霊舎よりも格上、神棚が最も高い位置になるよう、配置する点が注意点です。
祖霊舎を置くのに良いとされる向きは、家族団らんであれば南向き、果報が届く方向であれば東向きとされてきました。
| <祖霊舎の仕立て方> | ||
| [要素] | [良い場所] | [タブー] |
| [向き] | ●決まりはない ・東向き ・南向き |
●真北を避ける |
| [高さ] | ・神棚よりも下 | ・仏壇とぶつからない |
| [場所] | ●清浄な場所 ●家族がお参りしやすい場所 ・リビング ・床の間 ●神棚とは別の部屋 |
●人の出入りが激しい ・玄関 ・ドアの上 ●汚れやすい ●直射日光が当たる |
祖霊舎を整えるにあたり、大きな祖霊舎になると、榊に五色の房が付いた「真榊」を左右に配置する家も多いですが、左右それぞれの配置に注意をしてください。
真榊の房を繋ぐ部品「管玉(くだたま)」のアイテムに注目します。
向かって右側の真榊は管玉が鏡、向かって左側の真榊は管玉が剣です。
祖霊舎と神棚、仏壇がある家の配置は?
◇神棚が最も高く、続いて祖霊舎、仏壇の高さに注意します
祖霊舎と神棚、仏壇全てがある家もありますよね。
できれば祖霊舎と神棚、仏壇はそれぞれ別の部屋に置くと好ましいです。
けれども祖霊舎・神棚・仏壇を同じ部屋に置く時には、格上の高さ順や、それぞれがぶつからないよう、注意しましょう。
| <祖霊舎・神棚・仏壇がある配置> | |
| (1)神棚 | ・最も高い位置に配置 |
| (2)祖霊舎 | ・神棚よりも下に置く ・仏壇よりも上に置く ・神棚、仏壇と向かい合わない |
| (3)仏壇 | ・神棚よりも下に置く ・祖霊舎よりも下に置く ・神棚、仏壇と向かい合わない |
祖霊舎と神棚と仏壇、それぞれが向かい合った配置にしてしまうと、いずれかにお参りした時、他の神様仏様に背を向けてしまいます。
そうならないように、対角線上にそれぞれを置くことを控えて、神棚を最も高く、続いて神様(家の守護神)となった祖霊舎、最後に仏壇が最も低い配置です。
祖霊舎へのお供え物は?

◇祖霊舎へのお供えは、主にお米・お塩・お水・お酒・榊です
祖霊舎であっても神棚と同じ扱いですので、お供え物は神棚と同じく、主にお米・お塩・お酒・榊を供えます。
また祖霊舎は神棚と同じく、掃除を怠らずにお世話をすることも大切です。
| <祖霊舎へのお供え物> | |
| (1)洗い米 | ・白皿に供える ・お米を七回すすぐ |
| (2)お塩 | ・白皿に供える |
| (3)お水 | ・水玉に供える |
| (4)お酒 | ・徳利に供える (左右一対) |
| (5)榊(さかき) | ・榊立てに供える (左右一対) |
| (6)その他 | ・季節の果物 ・故人の好物 …など |
神道でのお供え物は仏教とは違い、お魚を供えることもあるでしょう。
ただ一般的に祖霊舎へ、特別な日のお供え物は、お米やお水、お酒などの基本的なお供え物の他、リンゴやバナナなどの果物や、大根やニンジンなどの野菜を供える家が多いです。
祖霊舎へのお参りの仕方は?

◇祖霊舎は家の守護神を祀る「家の神社」です
ご先祖様を祀る祖霊舎は、ご先祖様が家の守護神となった「神」を祀る家の小さな神社ですので、基本的な参拝方法は神社と変わりはありません。
神社によっても異なりますが、基本的な神社での参拝方法は「二拝、二拍手、一拝」です。
| <祖霊舎へのお参りの仕方> | |
| (1)手と口を清める | ・手を洗う ・口をすすぐ |
| (2)祖霊舎にご挨拶 | ・これからお参りをするご報告 ・軽くお辞儀 |
| (3)二拝 | ・祖霊舎へ向かう ・深くお辞儀 ・再び深くお辞儀 |
| (4)二柏手 | ・左手よりも下に右手 ・柏手をたたく ・再び柏手をたたく |
| (5)一拝 | ・深くお辞儀をする |
| (6)祖霊舎にご挨拶 | ・終わりのご報告 ・軽くお辞儀 |
以上が一連の祖霊舎へお参りの仕方ですが、故人が亡くなって家の守護神になるまでの五十日前は、柏手の打ち方が変わります。
故人を偲び、柏手は音を立てずに静かに行う「忍び手(しのびて)」で行ってください。
祖霊舎の日々のお世話
◇祖霊舎には、毎月1日・15日にはお供え物を交換します
穢れや汚れを嫌う神道では、祖霊舎や神棚は常に掃除しなければなりません。
特に旧暦時代には新月である1日、満月となる15日には、お水やお米、お塩などのお供え物を全て交換します。
| <祖霊舎への日々のお世話> | |
| (1)毎日のお参り | ・二拝一礼一拝 ・お水の交換 ・お酒の交換 ・榊のお水 ・その他は必要に応じて交換 |
| (2)毎月1日のお世話 | ・お水の交換 ・お酒の交換 ・お米の交換 ・お塩の交換 ・榊を入れ替える |
| (3)毎月15日のお世話 | ・お水の交換 ・お酒の交換 ・お米の交換 ・お塩の交換 ・榊を入れ替える |
毎日のお参りを行わず毎月1日・15日のみとして、一緒に祖霊舎の掃除やお供物の交換をする家もあり、家それぞれで習慣の違いもあるでしょう。
沖縄では台所を司るヒヌカン(火の神)も神様ですから、毎月旧暦1日と15日に拝みを捧げるように、神道の風習と似ている部分もあるでしょう。
・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日ヒヌカンの拝み方☆お供え物やお線香の本数を解説!
祖霊舎に神棚封じは必要?

◇祖霊舎には神棚封じの必要はありません
神棚を祀る家で家族が亡くなると、「死の穢れ(けがれ)」が神様の目に触れぬよう、忌中の四十九日間~五十日間は、神棚から目隠しする「神棚封じ」を行います。
祖霊舎に祀るご先祖様も家を守る守護神「祖霊」ではありますが、神棚に祀る神様とはステージが違うため、祖霊舎に神棚封じは必要ありません。
| <祖霊舎を仕立てた後は?> | |
| (1)神棚封じは必要ない | ・お参りでは「忍び手」 (柏手で音を立てない) |
| (2)神社参拝は控える | ・お祓いは神社に確認 ・五十日祭などは神職に確認 |
| (3)霊祭、式年祭 (仏教の法要) |
・神職に依頼して自宅で祭祀 ・霊璽を神社へ持参して祭祀 |
家族が亡くなり祖霊舎を仕立てた家では、仏教の法要と同じく定期的に、神職に依頼して祭祀を執り行ってもらいます。
| <祖霊舎を仕立てた後の霊祭、式年祭> | ||
| [種類] | [日にち] | [規模] |
| ●霊祭 | ||
| ・翌日祭 | ・2日目 | ・ご遺族のみ |
| ・十日祭 | ・10日目 | ・参列者を受け入れる |
| ・二十日祭 | ・20日目 | ・ご遺族のみ |
| ・三十日祭 | ・30日目 | ・ご遺族のみ |
| ・四十日祭 | ・40日目 | ・ご遺族のみ |
| ・五十日祭 | ・50日目 | ・参列者を受け入れる |
| ・合祀祭 | ・50日~100日 | ・ご遺族のみ |
| ・百日祭 | ・100日目 | ・ご遺族のみ |
| ●式年祭 | ||
| ・一年祭 | ・翌祥月命日 | ・参列者を受け入れる |
| ・三年祭 | ・3年目 | ・参列者を受け入れる |
| ・五年祭 | ・5年目 | ・参列者を受け入れる |
| ・十年祭 | ・10年目 | ・ご遺族のみ(省略) |
| ・五十年祭 | ・50年目 | ・ご遺族のみ |
故人が亡くなって1年目までの祭祀を「霊祭」、故人が亡くなって1年以上を「式年祭」と言い、規模によって省略、家族のみ、広く参列客を受け入れる霊祭、式年祭もあるでしょう。
・神道における法要とは?霊祭・式年祭の日程一覧|神式の法事の流れや手順、マナーを解説
まとめ:「祖霊舎」とは、神式のお仏壇です

「祖霊舎(それいしゃ)」とは、神道における仏壇の役割を果たします。
仏教の仏壇のように御本尊は祀らずに、祖霊舎の中心は「霊璽(れいじ)」です。
「霊璽」とは、仏教における位牌と同じ役割ですが、神道では人が亡くなると五十日祭の後に家を守護する守護神になるため、ご先祖様ご本人が神となります。
そのため祖霊舎も神棚と同じ、家にある小さな神社ではありますが、神社の神様とはステージが異なるため、一緒に祀ることはありません。
祖霊舎を仕立てた家は、仏壇のある家と同じく、定期的な儀式を行います。
五十日祭や百日祭、式年祭まで多くの儀式がありますが、現代では、仏式の法要にあたる霊祭や式年祭を、省略する家も増えました。
・法要とは?法事と法要の違いや法要の意味とは?お布施の目安・行うタイミングまで解説!