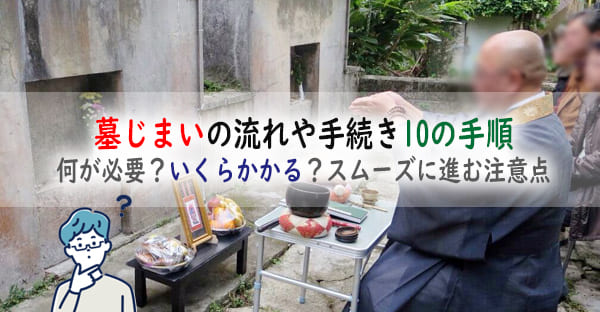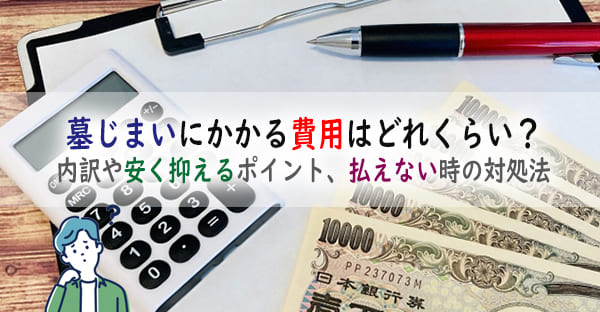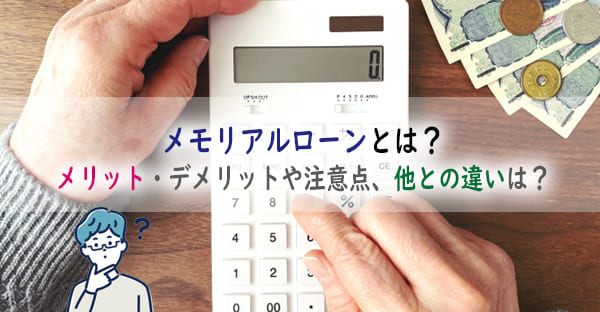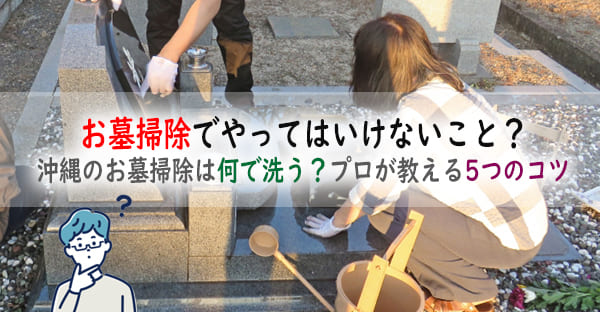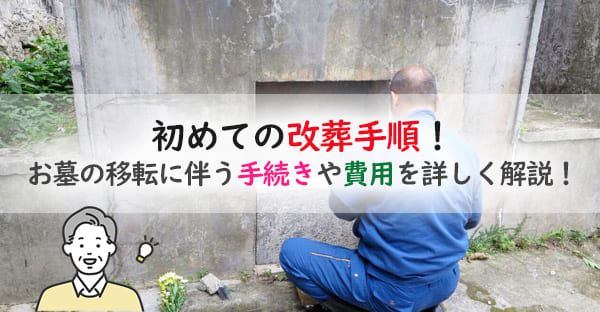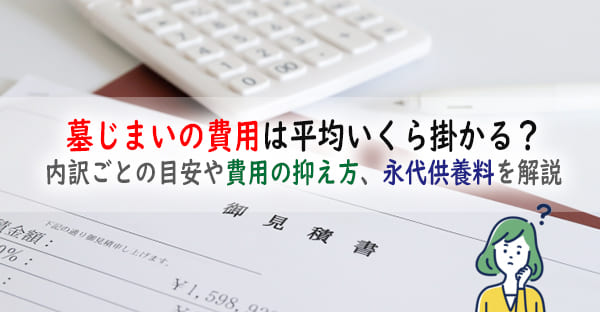・墓じまいを進める手続きの流れは?
・墓じまいの手続きに必要な書類とは?
・墓じまいをスムーズに進める注意点は?
今までのお墓を閉じて撤去し、墓地管理者に返還する「墓じまい」は改葬許可申請の手続きが必要です。
改葬許可申請には各種書類が必要ですので、墓じまいは計画的に進めます。
本記事を読むことで、スムーズに進める墓じまい手続き10の手順や注意点の他、大まかな費用目安が分かります。
墓じまいに必要な手続きとは?

◇墓じまいをするには、お墓がある自治体の「改装許可証」が必要です
そもそも「墓じまい」は民間から産まれた造語ですので、行政手続きを行う時は「改装」として手続きを行います。
墓じまいの手続きを行う場所は、お墓のある自治体の役所です。
書類は窓口でも受け取ることができますし、予めホームページからもダウンロードをしても良いでしょう。
| <墓じまいに必要な書類> | |
| (1)改葬許可申請書 | ・お墓がある自治体の役所で入手 (ホームページからダウンロードも可) |
| (2)埋葬証明書 | ・遺骨がある墓地で発行 (遺骨が埋葬されていることを証明) |
| (3)受け入れ証明書 | ・遺骨の受け入れ先 (遺骨の納骨先が決まっていることを証明) |
| (4)改葬承諾書 (一部で必要) | ・墓じまいを依頼する人と墓地の使用者が異なる場合に提出する書類 (使用者が同じ場合は、提出する必要はありません。) |
これらが揃ったら、改葬許可申請書とともに役所に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
改装許可証が発行されて初めて、遺骨の取り出しやお墓の撤去が可能です。
そのためお墓の撤去工事の日程が決まっているならば、その日よりも前に墓じまい手続きを済ませておかなければなりません。
「墓じまい」とは?
◇墓じまいは簡単に言えば、「お墓」を終わらせることです
墓じまいは行政手続き上「改葬(かいそう)」と呼ばれます。
ただし人々が使う言葉としては、墓じまいと改葬では、お墓に対する扱いに違いがあるでしょう。
現在の墓石を撤去し、更地にして、墓地管理者に返還することが墓じまいです。
墓じまいで取り出した遺骨は、別の形で供養します。
| <墓じまいと改葬の違い> | |
| [形式] | [違い] |
| (1)墓じまい | ・民間から産まれた造語 ・「お墓」の形式を終わらせる |
| (2)改葬 | ・行政手続き上の言葉 ・お墓の形式が終わるとは限らない |
一般的に改葬は「お墓の引っ越し」と言われますが、墓じまいでは改めてお墓を建てる選択は、あまり多くはありません。
改葬にしろ墓じまいにしろ、行政手続きや墓地管理者との交渉が必要です。
また墓石の撤去や、墓地区画を更地にするなど、業者へ依頼して進めます。
一般的な生活をしていると、墓じまいの機会は頻繁に訪れないため、このような行政手続きや業者への依頼を負担に感じて先延ばしになる人は多いです。
あらかじめ墓じまいの流れや、手続きの手順を知ることで、不安は大きく解消されるでしょう。
・昭和23年5月31日(法律第48号)厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」
墓じまいの手続き10の手順

◇墓じまいは、取り出した遺骨の供養までがワンセットです
墓じまいの背景には、地方の過疎化や少子化などの影響があります。
「次の世代にお墓の負担をかけたくない」「お墓が遠方にありお墓の維持管理が難しい」「夫婦それぞれの実家のお墓を守るのが大変」などの問題です。
そのため墓じまいの場合、最終的に継承者のいらない供養を目的とした墓じまいが多いでしょう。
(1)親族と相談
(2)墓地管理者と相談
(3)お墓の内部調査
(4)遺骨の納骨先を決める
(5)埋葬証明書をもらう
(6)受け入れ証明書をもらう
(7)改葬許可申請
(8)閉眼供養
(9)墓石の解体
(10)遺骨の納骨
改葬では家の近くの霊園にお墓を建て、遠方から遺骨を移動して納骨するケースも見受けますが、墓じまいで取り出した遺骨は、継承者を必要としない永代供養が一般的です。
墓じまいの行政手続きでは、取り出した遺骨の受け入れ先を記載する必要があることからも、最初に遺骨の受け入れ先を決めると、墓じまい手続きがスムーズに進みます。
(1)親族と相談
◇永代供養のなかには、埋葬すると遺骨が取り出せないものもあります
墓じまいで取り出した遺骨は、継承者を必要としない「永代供養」が多いです。
「永代供養」とは、墓地管理者が家族に代わり、遺骨の管理や供養を比較的長い世代まで続く永代にわたり担うことを差します。
自然葬や合祀墓では、一度埋葬すると遺骨は二度と手元に戻らないため、最初に家族や親族への相談や理解が必要です。
また墓じまいに掛かる費用を分担できると、墓主の負担も軽減するでしょう。
・墓じまいで起きがちなトラブルは?霊園や親族、思わぬトラブル10の事例と解決策を解説
(2)墓地管理者と相談
◇改葬許可申請には、現在のお墓の管理者が発行する埋葬証明書が必要です
墓地の使用契約の解除もあるため、それに関連する手続きや費用についても確認しておきましょう。
沖縄では少ないものの寺院墓地にお墓が建っている場合、墓地管理者との関係性は菩提寺(寺院)、檀家(家)であることが多いです。
閉眼法要や檀家を離れる際にかかる費用なども、一緒に相談すると予算計画を立てやすいです。
(3)解体業者を決める
◇複数の業者に相見積もりを取ると比較検討しやすいです
墓じまいをするためには、解体業者を探さなくてはなりません。
お墓から遺骨を取り出した後、墓石を撤去し、地面を整える作業を行ってくれます。
石材店も解体作業を行ってくれるので、複数の業者に見積もりを依頼してみることをおすすめします。
墓地の形や地形によっても差が出るため、具体的な費用を把握するためには、現地を見て詳細な見積もりをもらうことが重要です。
また寺院墓地や霊園では提携する石材業者があるでしょう。
なかには提携石材業者以外は工事ができない墓地もあります。
その場合、複数の業者に見積もりを依頼することは難しいので、詳細な見積もりをもらうようにしましょう。
作業内容や費用についてよく確認し、不明点があれば納得いくまで質問することがポイントです。
・墓じまいに掛かる平均的な費用はいくら?内訳や安く抑えるポイント、払えない時の対処法
(4)お墓の内部調査
◇お墓の内部調査は無料で受け付けてくれる業者が多いです
墓じまいを前提に石材業者や霊園に相談をすると、お墓の内部調査を無料で行ってくれる業者が多いでしょう。
お墓の内部調査のみを行う場合、費用目安は約3万円ほどです。
特に風葬の歴史があった沖縄では、火葬されていない古い遺骨が出てくることもあるので、墓じまいを検討し始めたら、最初に内部調査を行っておくと安心です。
(5)遺骨の納骨先を決める
◇先に遺骨の納骨先を決めると、墓じまい手続きがスムーズです
お墓の内部調査でお墓の状態や、眠っている遺骨の柱数が決まったら、遺骨を取り出した後の納骨先を決めます。
行政手続きを行うためには、次の受け入れ先が決まっている方が手続きがスムーズに進みます。
ただし改葬先によって費用がかなり異なってきます。
一基ごとに費用を支払うお墓と違い、永代供養は遺骨1柱ごとの料金形態が一般的ですので、柱数と予算で検討すると良いでしょう。
| <遺骨の納骨先による費用の違い> ※大まかな費用相場 | |
| [納骨先] | [費用相場] |
| (1)お墓を建てる | ・約100万円~300万円 |
| (2)永代供養(合祀墓) | ・約5万円~150万円 |
| (3)納骨堂 | ・約15万円~150万円 |
| (4)散骨 | ・約5万円~50万円 |
| (5)樹木葬 | ・約20万円~80万円 |
| (6)手元供養 | ・約3万円~30万円 |
費用はもちろん、選択肢によって親族から反対されるリスクもあるため、相談しながら選ぶ必要があります。
自然に還る自然葬は注目され、特に散骨や樹木葬の需要が高まっていますが、手を合わせる場所が欲しい人は、永代供養や納骨堂がおすすめです。
永代供養墓などは募集期間が決まってきた時に入れないケースも出てきます。
時間に余裕を持って進めていくことが大切です。
・墓じまい後の永代供養とは?取り出した遺骨の供養5つの方法、メリットデメリットも解説
(6)埋葬証明書、受け入れ証明書をもらう
◇埋蔵(埋葬)証明書は、現在の墓地に誰が埋葬されているのかを証明する書類です
現在の墓地管理者から発行してもらいます。
霊園や寺院墓地、公営墓地であれば、管理会社に発行してもらいましょう。
沖縄でトラブルは少ないですが、寺院墓地ではご住職との関係性にも考慮して、丁重に墓じまいのご相談をすることも大切です。
●個人墓地の場合、墓主(墓地管理者)が分かっていれば、「改葬許可申請書」をお墓がある自治体の役所窓口で発行してもらい、墓主に署名・捺印をしてもらいます。
また一部の自治体では、改葬許可申請書と一体化している場合もあります。
この場合には、自治体が発行する改葬許可申請書に記入をしてもらわなければなりませんから、予め確認をして、二度手間にならないように進めましょう。
受け入れ証明書は遺骨を納骨する墓地管理者から入手します。
手元供養などで受け入れ証明書の入手ができない時には、自治体の役所窓口で相談しましょう。
・改葬許可申請書|沖縄市
(7)改葬許可申請
◇「改葬許可申請書」は、現在の墓地がある自治体の役所で入手します
実際に窓口に行っても入手できますが、多くの場合は自治体HPからダウンロードすると便利です。
発行手数料は無料の場合もありますが、かかっても1,500円程度です。
記入する内容は、下記のような事項があります。
(自治体により内容は異なるので、あくまでも一例です。)
・申請者の署名・捺印
・埋葬されている人の情報
(氏名、没年月日、火葬場など)
・墓主と埋葬されている人の続き柄
・改葬理由
・遺骨の受け入れ先
・解体工事をする業者
埋葬されている人の情報は分からない箇所も多いですが、この場合「不明」と記載すれば概ね問題ありません。
自治体の記入のルールに従い、分からない箇所は相談しながら記入を進めましょう。
●改葬許可申請は、遺骨1柱につき1枚です。
…取り出した遺骨の数だけ、改装許可申請が必要になります。
また多くの自治体では、郵送でのやり取りが可能です。
遠方に住んでいて墓じまい手続きが不便な人は、HPから改葬許可申請書を印刷し、記入して役所に送付すると良いでしょう。
提出の際には、運転免許証など本人確認書類などが必要となりますので、どのような書類が必要か、あらかじめ確認してから手続きすることをおすすめします。
・改葬許可について|那覇市
(8)閉眼供養
◇「閉眼供養」とは、お墓の魂を抜く仏教的な儀式です
墓石を取り外す前に、閉眼供養を行います。
閉眼供養とは魂抜きとも言われ、仏様の魂を抜いて墓石をただの石に戻す儀式です。
仏教儀式なので無宗教や他宗教の場合、閉眼供養を行わないこともあるでしょう。
また浄土真宗では仏様を移す「遷仏法要」を行います。
寺院墓地であればご住職にお願いしますが、公営墓地や民営墓地は自分で僧侶を探し依頼したり、墓地管理者に紹介していただくと良いでしょう。
閉眼供養を行うにあたり、「お布施」として感謝のお金をお包みします。
●閉眼供養のお布施相場…約3万円~15万円ほど
(通常のお布施の約1回~3回分が目安)
お布施は、あくまでも気持ちでお渡しするため、明確な基準はありません。
また、閉眼供養に限らず、お布施は地域の風習やお寺とのお付き合いの長さによっても異なります。
分からなければ、高齢の親族や周囲に確認しても良いでしょう。
なお、閉眼供養は絶対に行わなければならないものではありませんが、この儀式が済んでいないと工事を請け負ってくれない石材業者も多いです。
スムーズに進めるためには、閉眼供養は行っておくことをおすすめします。
(9)墓石の解体
◇墓地管理者に墓地へ返還する時には、更地にして返還します
墓じまいによりお墓を閉じる際、霊園や寺院墓地、公営墓地に墓地区画を返還する時には、元の状態にして返さなければなりません。
また墓石は処分まで依頼をします。
墓じまいで撤去した後の墓石は産業廃棄物として、処分場で細かく粉砕されたのち、再生砕石として扱われる墓石も多くあるでしょう。
・平成12年12月6日生衛発第1764号「墓地経営・管理の指針等について」
(10)遺骨の納骨
◇取り出した遺骨は自然葬や永代供養を行います
墓じまいで取り出した遺骨は、墓地以外の場所に埋葬したり、ゴミとして処分することは、刑法190条により法的に許されていないため、自然葬や永代供養の形で供養すると良いでしょう。
取り出した遺骨は、一度自宅に持ち帰っても良いですし、状態が悪いようならば洗骨業者に依頼してキレイにしてもらいます。
| <墓じまいの手続き:遺骨の納骨> | |
| (1)遺骨の取り出し | ●石材業者に依頼 ①内部調査 ②閉眼供養 ③遺骨の取り出し |
| (2)遺骨の状態 | ●専門業者(粉骨業者など) ①遺骨を洗骨 ②遺骨の乾燥 (粉骨しても良い) ③自宅に持ち帰っても良い |
| (3)遺骨の搬送 | [搬送方法] ・公共機関により自分で移動 ・ゆうパックで郵送 ・NPO法人を利用 |
遺骨の搬送は一般的に自分達で車や公共交通機関を利用して持ち運ぶケースが多いですが、ゆうパックでは遺骨の郵送を受け付けています。
ただし、遺骨を郵送できるのは日本郵便のゆうパックのみですので注意をしてください。
・遺骨の郵送キット(楽天)
・遺骨を郵送できるのはゆうパックのみって本当?送骨サービスや梱包の仕方、送り方を解説
個人墓地の墓じまい手続きは?

◇個人墓地の墓じまいでは、必要書類を自治体に確認します
個人墓地の多い沖縄県では、どの自治体も基本的に、個人墓地による墓じまい手続きに対応していますが、その対応は自治体によって違うでしょう。
そのため墓じまいの手続きに行く際、自治体へ必要書類を確認しておくと安心です。
| <一般的な個人墓地の墓じまい> | |
| [個人墓地で必要な書類] | ●改葬許可申請書 ・墓主(墓地所有者)による署名・捺印 ・墓地の地図をコピーしたもの ・遺骨の受け入れ証明書(納骨先) ・申請者の身分証明書 |
| [必要に応じて必要な書類] | ・墓地使用者等の承諾書 (墓主以外が墓じまいをする場合) ・委任状 (代理申請の場合) |
墓じまい手続きは、現在墓地がある自治体で申請を行います。
改葬許可証を受け取ることで、遺骨の取り出しや搬送が可能です。
また新しい納骨先に納骨する時にも、改葬許可証の提出が求められますので、大切に保管してください。
改葬許可証は当日発行ではない自治体もありますので、墓じまい手続きは余裕をもって進めましょう。
手元供養の墓じまい手続き
◇新しい納骨先の記入欄がある場合、窓口に確認を取りましょう
手元供養は近年増えた新しい形の供養方法です。
そのため墓じまい後に手元供養を行うケースの手続きに対応していない自治体も、全国的に見受けられます。
一般的には新しい納骨先の記入欄を空白にする、受け入れ証明書なしで良い、など、対応策を取ってくれます。
・墓じまいで起きがちなトラブルは?霊園や親族、思わぬトラブル10の事例と解決策を解説
墓じまい手続きの注意点とは?

①改葬許可申請書は、申請者載が記入します
改装許可申請は代理申請をする場合もありますが、代理申請であっても、書類は申請者本人による記載でなければなりません。
| <墓じまい手続き:記載の注意点> | |
| ●改装許可申請書 | ・申請者本人の記載 |
| ●受け入れ証明書 | ・代筆が可能 ・委任状の添付が必要 |
代理を頼む際には、急いで手続きをしないためにも、書類を早めに確認しておきましょう。
改葬許可申請書は1柱に1枚必要です
②改正許可申請は、遺骨1柱に付き1枚で申請します
「改葬許可申請書」は、1つの遺骨につき1枚が必要ですので、複数の遺骨を改葬する場合は、取り出す遺骨の柱数だけの枚数を記載しなければなりません。
ただ自治体によっては、1枚の改葬許可申請書で複数の遺骨分の改葬を申請できる場合もあります。
自治体の役所へ出向いて手続きを行う前に、担当部署に問い合わせてみると、二度手間を回避できるでしょう。
お墓の撤去前に墓じまい手続きを済ませます
③取り出した遺骨をすぐに納骨できるよう、手続きは早く済ませます
石材業者によるお墓の撤去を終えた後、取り出した遺骨が残ります。
新しい納骨先が決まっていれば、そのまま納骨ができますが、決まっていない場合はどこか保管場所を用意しなければなりません。
目安としてはお墓の撤去工事を行う日の約1か月前から、役所窓口に出向いたり、改装許可申請書などの必要書類をダウンロードするなどして、墓じまい手続きの準備を進めます。
遺骨は自宅保管もできますが、数が多いと家族としても戸惑いますよね。
遺骨を取り出した後を想定して、早めに行動することが、墓じまいを円滑に進めるための重要なポイントです。
墓じまい費用の相場を知る
④墓じまい費用の相場を知り、法外な請求トラブルを回避します
墓じまいにかかる費用相場は、全国的に約30万円~300万円です
コンパクトなお墓であれば、お墓の撤去のみであれば約30万円でもできるでしょう。
ただ、撤去費用は、墓石のサイズや墓地の広さ、機材の使用の有無などのさまざまな条件によって決まります。
そのため撤去工事後に予想以上の費用を請求され、困るトラブルもあるのです。
実際に全国的には、高額な撤去費用の請求被害も見受けますので、墓じまいを依頼する際には、注意をしてください。
●複数の業者に相見積もりを取る
・業者を比較検討できる
・依頼するお墓の墓じまい費用相場が分かる
・複数の担当者と触れることで、違和感に気づく
墓じまいの費用の相場は全国的に約30万円~300万円ほどと費用に幅があるため、自分のお墓がどれほどの価格帯が分かりにくいこともあるでしょう。
ただ、墓じまいの費用相場に幅がある理由は、「取り出した遺骨の納骨先をどのようにするか」によるものが大きいです。
この点を踏まえて、墓じまい相場や相見積もりから、予算を割り出すと良いでしょう。
・墓じまいにかかる費用はどれくらい?内訳や安く抑えるポイント、払えない時の対処法
まとめ:改装許可申請が墓じまい手続きです

墓じまいは行政手続き上「改葬(かいそう)」ですので、役所窓口で行う行政手続きとして、「改装許可申請」を行います。
改装許可申請には、現在遺骨を納骨していることの証明「埋葬(埋蔵)証明書」と、取り出した遺骨の新しい納骨先が決まっていることの証明「受け入れ証明書」を用意しなければなりません。
個人墓地の場合、自治体によって対応は異なりますが、一般的には個人墓地の地図をコピーすることで申請ができます。
ただし地図は著作権のないもののコピーは避けてください。
墓じまいを依頼する石材業者や、閉眼供養で読経供養を依頼する僧侶は、新しい納骨先の霊園などで相談しても紹介してくれます。
まずは霊園や石材業者など、専門業者に相談をして、お墓の内部調査から始めてみてはいかがでしょうか。