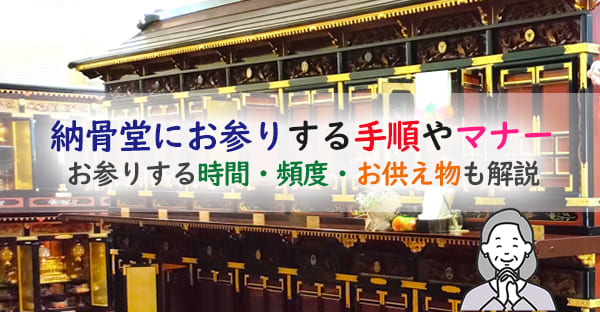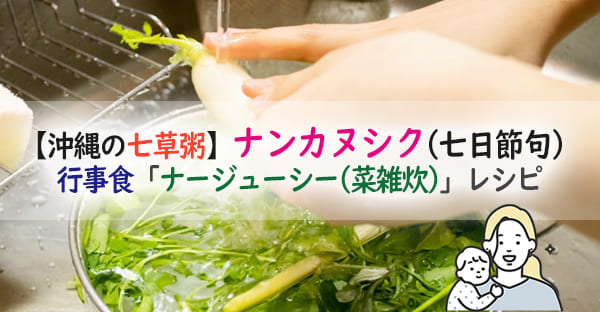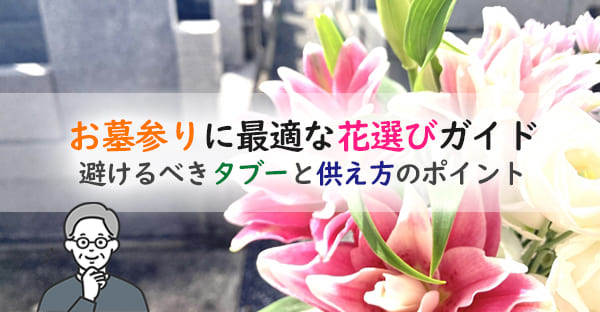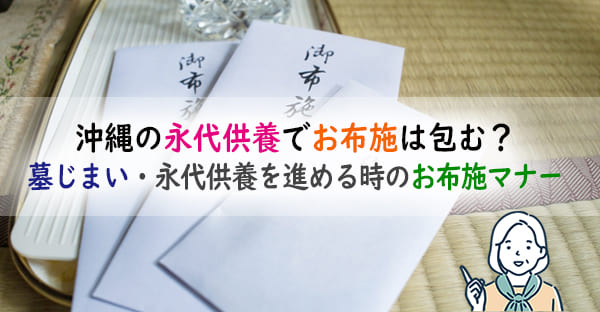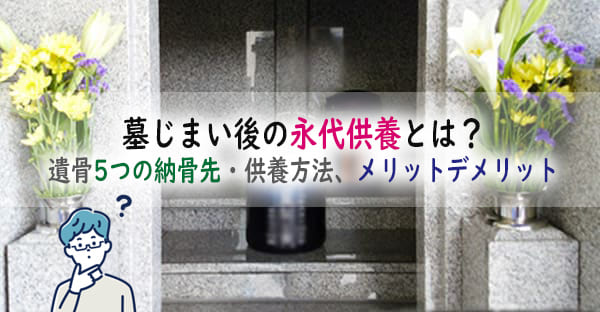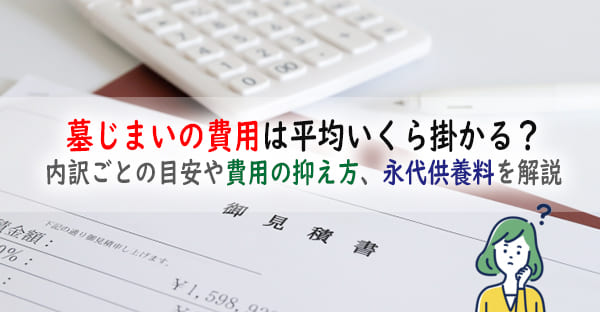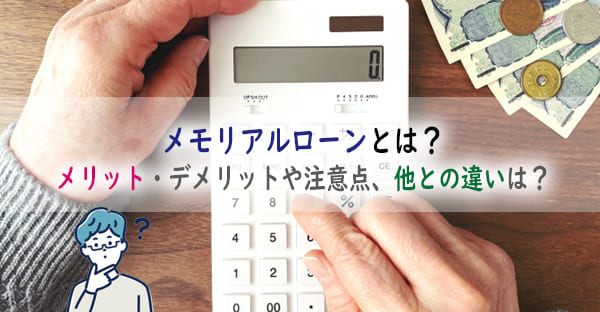「納骨堂にお参りに行くにはどうしたらいい?」
「納骨堂でお参りするマナーとは?」
「友人でもお参りはできる?」
継承問題などそれぞれの事情から、近年はお墓を閉じる「墓じまい」が増えました。そこで増えた供養の形が、屋内で遺骨を納める「納骨堂」です。
ずっとお墓参りに慣れていると、「お線香はあげていいの?」「大勢で行っても良いのかしら?」などなど、屋内と屋外で違う手順やマナーが心配になりますよね。本記事を読むことで、納骨堂ならではのお参り手順やマナー、持ち物や注意点が分かります。
納骨堂のお参りとは

◇「納骨堂」とは屋内のスペースに遺骨を収蔵し、保管する供養の形です
納骨堂は屋内に個別スペースを契約し、遺骨を納める新しい供養の形となります。遺骨の納め方は従来のロッカー式や仏壇式の他、お参りに行くと個別の部屋に案内され、そこに収蔵した遺骨が機械式で出てくる「マンション型」など、さまざまです。
納骨堂のお墓参りとは、屋内に設けられた遺骨収蔵スペースで行うお参りのことです。納骨堂にはさまざまな種類があり、それぞれに応じたお参りの方法があります。
ロッカー型
ロッカー型の納骨堂では、遺骨が収められたロッカースペースの前でお参りを行います。鍵を使って開閉できるため、プライバシーを保ちつつお参りが可能です。
これにより、ロッカーと同じく上下左右にロッカースペースがあるため、周囲の参拝客への配慮も必要になります。また、納骨堂はアクセス環境の良い立地が多く、天候に左右されず、いつでも快適に訪れることができるのも大きな魅力です。
仏壇型
仏壇型の場合は、仏壇の前でお参りをします。このタイプは、伝統的な仏壇と同じようにお供え物を置いたり、線香を立てたりすることができます。
お参りの際には、静かに手を合わせ、故人の思い出を心に浮かべながら祈りを捧げることが大切です。また、家族と共に訪れ、故人との思い出を語り合うことで、心の安らぎを得ることもできます。
マンション型や室内墓所タイプ
マンション型や室内墓所タイプの納骨堂では、個室に案内されてお参りを行うことが一般的です。個室には椅子やテーブルが備え付けられていることが多く、ゆっくりと故人を偲ぶことができます。
また、プライベートな空間が確保されているため、他の方の目を気にせずに、故人との思い出に浸ることができます。さらに、納骨堂によっては、季節に応じた装飾や音楽が流れるなど、心安らぐ環境が整えられていることもあります。
位牌型
位牌型の納骨堂では、位牌の前で手を合わせます。このタイプは、位牌が中心となるため、仏壇を置くスペースが限られている場合に適しています。
また、多くの納骨堂では位牌が並べられていますが、訪問者が静かに祈りを捧げられるよう、落ち着いた環境を提供しています。お参りの際には、事前に開館時間やお参りのルールを確認しておくと良いでしょう。
さまざまな納骨堂の登場
納骨堂のお参りの仕方は、納骨堂の設計と運用に応じて異なるため、訪問前に納骨堂の種類とお参りの流れを確認しておくと良いでしょう。 ひと昔前まではロッカー式の納骨堂がほとんどで、その用途もお墓が建つまでの一時的な安置場所でした。
けれども沖縄で墓じまいが進むとともに、墓じまい後に亡くなった家族を供養するための形として、お墓同様に扱われるようになりました。
それに伴い、納骨堂も個別の法要スペースが設けられるなど、遺骨の供養が充分にできる施設へと変化しています。詳しくは下記コラムをご参照ください。
「墓じまい」や「永代供養」とは

◇納骨堂のお参りが注目される理由は、墓じまいや永代供養の増加です
沖縄で納骨堂のお参りが注目される理由は、お墓の継承者問題や、個人墓地による管理問題などがあります。お墓の継承や維持管理が困難になり、お墓を閉じる「墓じまい」が増えました。
沖縄で納骨堂が注目されるのは、施設管理者が家族に代わり永代に渡って遺骨を供養する「永代供養」が付加されているからです。納骨堂のお参りには、墓じまいや永代供養といった選択肢があります。
墓じまいとは
墓じまいとは、お墓を閉じることを意味します。具体的には、まず遺骨を取り出し、その後お墓を撤去し、最終的に墓地を返還するというプロセスを経ます。このようなプロセスを経る理由には、後継者がいない場合や、お墓の維持が困難になった場合が挙げられます。
墓じまいを行った後、遺骨を納骨堂に安置する選択も増えてきています。納骨堂は、都市部でもアクセスが良く、天候に左右されずにお参りができるため、多くの人々に利用されています。
永代供養とは
永代供養は、管理者が遺骨を管理し供養する方法です。家族に代わり墓地管理者が遺骨を永代に渡り供養することを差します。
そのため沖縄に多い個人墓地では、墓主が所有者になるため、永代供養が成り立ちません。個人墓地にお墓がある墓主が墓じまいの後に永代供養を希望する場合、霊園や寺院墓地へ遺骨を移動する必要があります。
永代供養の契約をした遺骨は契約した一定年数において個別に収蔵されます。そのひとつの選択肢が納骨堂です。ただし、個別に管理・供養されますが、一定年数が経過すると合祀されるプランが一般的です。
また合祀墓(合葬墓)のように、遺骨を合同で管理・供養する方法も選べます。沖縄では先祖代々位牌「トートーメー」の永代供養も注目されています。この永代供養により、後継者がいない場合でも、安心して遺骨を供養することができるでしょう。
・沖縄メモリアル整備協会|お墓の引越し「改葬・墓じまい」
納骨堂でのお参りのポイント
納骨堂でのお参りは、天候に左右されず、いつでも快適にお参りできるのが特徴です。沖縄ではお墓参り行事の時のみ、お墓へ行く風習がありますが、納骨堂はいつでも気軽に故人に会いに行けるでしょう。
また、施設によっては、遺族が集まりやすいよう、アクセス環境の良い立地や広い駐車場、家族や親族が利用できる芝生広場や屋内施設など、設備が整っている場合が多いでしょう。
一般的に納骨堂には開館時間が設定されており、その時間内でのお墓参りが必須です。お参りの際には、事前に納骨堂の開館時間やルールを確認しておくとスムーズに進められます。
沖縄で墓じまいが増える背景
若い世代が地元から離れて他県や世界へ飛び回るようになり、お墓の継承者問題はもちろんのこと、そもそも門中の人々が少なくなる悩みも増えています。
門中の人々が少なくなると、模合による収入が少なくなるため、経年劣化によるお墓の大幅な修繕などもできません。
沖縄のお墓はコンクリート墓も多いので、経年劣化によるひび割れや損傷が激しくなり、後々のお墓継承者の充てもないことから、墓じまいを決断する墓主も多いのです。
納骨堂でのお参りはいつ行く?

納骨堂は基本的にいつでもお参りが可能です。ただし、先ほどお伝えしたように開館時間があるので、開館時間内に行かなければなりません。
納骨堂へ頻繁にお参りに行きたい場合、契約時に施設の利用規約をよく確認しましょう。開館時間の他、施設によっては、供え花やお線香の制限がある、一度に参拝できる人数が限られる、などの可能性があります。
納骨堂のお参りに適した時間帯はある?
一般的には、お墓参りは午前中が良いとされ、夕方以降のお参りは良くありません。「夕方以降はお墓に眠る悪しき者が付いてくるから」などの迷信がありますが、これは夜中のお墓参りが危険だったからでしょう。
また、屋外では明るい午前中の方が、お墓参りをしていて気持ちも良いです。実際に、朝9時から夕方6時までの時間帯にお参りに行く家族が多いですよね。これは屋外のお墓参りの風習から、この時間帯に人気が集まる傾向です。
ただし、屋内の納骨堂へお参りに行く場合は、辺境地に建つお墓のような危険リスクもないため、安全に夕方以降もお参りできます。
仕事帰りに立ち寄っても良い?
また、伝統的なお墓参りマナーとしては、仕事や用事の帰りに立ち寄ることを「ついで参り」と呼び、用事のついでにお墓に立ち寄ることを、ご先祖様や故人に失礼だとして、マナー違反とされてきました。
けれども納骨堂は、いつでも会いたい時にお参りをして、故人を偲ぶこともメリットのひとつとしています。そのため、仕事帰りなどに立ち寄る参拝者も少なくありません。
納骨堂は日々の暮らしのなかで、いつでも気軽にお参りができることから、大切な家族を失ったショックを癒す「グリーフケア」としても役立っています。
納骨堂は少人数でお参りしても良い?
納骨堂は、むしろ一人で仕事帰りに立ち寄る人々も多いです。
夫婦や家族など少人数でのお参りはもちろん、一人で訪れる方も多い点が、納骨堂へのお参りの特徴です。
友人でも納骨堂にお参りできる?
◇お墓参りと同じように、納骨堂は友人でもお参りできます。
ただ屋内施設である納骨堂は、場所が分からなければなりません。またマンション型納骨堂の場合、家族が所有するICカードにより、収蔵されている遺骨が繰り出されるので、ICカードが必要です。そのためご家族への連絡は必要になるでしょう。
・ご家族へ連絡する
・お参りする日時を伝える
・ご家族から納骨堂へ連絡
ICカードの持参を必要としない納骨堂でも、遺骨の家族であることを確認する施設もあります。最もスムーズな方法は家族と一緒にお参りに行くことですが、家族から納骨堂に連絡をしておけば、お参りは友人でもできることが多いです。
納骨堂のお参りでの服装マナー

◇納骨堂のお参りは、基本的に自由です
全国的な納骨堂のお参りでは、同じ納骨堂でも寺院が運営する場合、お参り前に本堂へご挨拶に伺うこともあります。沖縄の納骨堂はお参り前に本堂へのご挨拶を必要としない形式が多いですが、本堂へご挨拶へ伺うならば、畏まったおお出掛け着となる「平服」が良いでしょう。
推奨する服装
納骨堂を訪れる際には、落ち着いた色合いの服装がおすすめです。特に黒やグレー、紺などの控えめな色を選ぶと良いでしょう。清潔感のある服装を心掛け、畏まったお出掛け着を選ぶことで、故人への敬意を示すことができます。
また、女性であれば、派手なアクセサリーや露出の多い服装は避け、シンプルで上品な装いを心掛けましょう。男性も、スーツやジャケットを羽織ることで、よりフォーマルな印象を与えることができます。
服装だけでなく、靴も磨いておくと、全体として整った印象になります。納骨堂は静かな場所であるため、心を落ち着けて訪れることが大切です。訪問の際には、携帯電話をマナーモードにするなど、周囲への配慮も忘れずに行いましょう。
避けたい服装
納骨堂のお参りでは、華美な服装や露出が多いスタイルは避けるべきです。お参りは故人を偲ぶ厳粛な場であり、他の参拝者への配慮も必要です。カジュアル過ぎる服装も控え、落ち着いた色合いの服装を選ぶと良いでしょう。
また、強い香水は屋内に臭いがこもりやすく、他の参拝者に不快感を与えることがありますので、デオドラント程度に留めるのがマナーです。高いヒールは音が響きやすく、納骨堂の静寂を乱す可能性があるため、控えるのが望ましいです。
参拝の際には、こうしたマナーを意識することで、故人への敬意を表しつつ、他の参拝者との和を保つことができます。
・自宅弔問のマナーとは?いつ・どんな服装で行く?お供えなど持ち物、お線香の上げ方とは
納骨堂の利用規約を守る

◇屋内の納骨堂でのお参りは、まず施設の利用規約を確認します
屋内で行う納骨堂のお参りマナーは、・臭い・騒音・火元への配慮が必要です。まだ新しい施設である納骨堂は、マナーも利用規約明記していることが多いのですが、周囲の参拝者への配慮を意識すると良いでしょう。
お線香の取り扱いについて
お参りの際に配慮すべき点として、まずお線香があります。お線香に火を付けて良いのか、あるいは施設で電子線香などを準備しているのかを確認しましょう。納骨堂は屋内施設なので、火の元となるお線香に火を付けることを禁止している場合があります。
電子線香とは、火を使わずに電気で点灯する線香で、火災の心配がないため安全に利用でき、特に屋内の納骨堂でのお参りに適しています。
参拝場所の確認
参拝場所についても確認が必要です。納骨堂によっては、個室に案内される場合もあれば、合同の参拝スペースが別に設けられている場合もあります。事前に参拝方法を確認しておくことで、当日スムーズにお参りを進めることができます。
また、納骨堂によっては予約が必要な場合もあるため、訪問前に問い合わせておくと安心です。さらに、服装や持ち物についても確認しておくと、マナーを守ったお参りができるでしょう。
お供え物に関する注意
お供え物に関しても注意が必要です。個々のスペース内でお供えができるのか、供え花は持参して良いのかを確認しておくと良いでしょう。臭いが室内にこもりやすい供え花は持ち込まない(フェイクフラワーなどの使用)などの規定がある納骨堂もあります。
これらの点を事前に確認することで、納骨堂での訪問をよりスムーズに行うことができます。
納骨堂でお参りをする注意点

◇基本的におしゃべりを控え、お供え物や供え花は持ち帰りましょう
屋内施設である納骨堂のお参りでは、施設の規約に明記していなくても、周囲や今後の参拝客への配慮として、お供え物や供え花は持ち帰るのがマナーです。
臭いは屋内ではこもりやすいためですが、カーペットなどは汚れも目立つため、屋外以上にキレイに片付けて帰ると良いでしょう。
水と火の扱いには充分注意
納骨堂でのお参りでは、ろうそくや線香を使用することがあります。火を扱う際は、必ず安全を確認し、火が完全に消えるまでその場を離れないようにしましょう。また、水を供える際には、周囲を汚さないように慎重に取り扱い、清潔さを保つことが大切です。
施設をキレイに利用する
納骨堂は多くの人が利用する大切な場所です。お参りの際には、施設をきれいに保つことを心がけ、ごみや供物の包装は持ち帰りましょう。また、納骨堂内では静かに過ごし、他の参拝者の方々への配慮を忘れずに。
次に訪れる方々が気持ちよく利用できるようにするための小さな心遣いが、全体の雰囲気を良くすることに繋がります。
混雑を避ける
譲り合う多くの人が訪れる納骨堂では、混雑する時間帯を避けることが望ましいです。特に、お盆やお彼岸などの時期は訪問者が多いため、早朝や夕方など比較的空いている時間を選ぶと良いでしょう。
どうしても混雑する場合には、譲り合いの精神を持って行動し、他の参拝者の時間を尊重することが大切です。また、事前に納骨堂のルールやマナーを確認しておくことで、スムーズにお参りを行うことができます。
おしゃべりや騒音は控える
納骨堂は故人を偲ぶ静かな場所です。お参りの際には、静粛を心がけ、携帯電話の電源を切るかマナーモードに設定し、会話も控えめにしましょう。心静かに故人との時間を大切にすることが重要です。
また、お参りの前には手を清め、心を整えてから納骨堂に入りましょう。お花やお線香を供える際には、周囲の方々の迷惑にならないように配慮し、丁寧に供えます。これらのマナーを守ることで、故人への思いをしっかりと伝えることができます。
施設ルールは事前に確認
納骨堂にはそれぞれの施設ごとにルールが異なる場合があります。お参りの前に、施設のルールや利用時間を確認しておくことが大切です。これにより、スムーズにお参りを行うことができ、他の利用者とのトラブルも避けられます。
例えば、納骨堂では、持ち込み可能なお供え物や花の種類が制限されている場合があります。事前に確認し、適切なものを用意することで、施設の美観を保ち、故人への敬意を表すことができます。また、写真撮影が禁止されていることもありますので、記録を残す際には施設の許可を得るようにしましょう。
納骨堂は手ぶらのお参りもOK
ただしお墓参りとは違い、納骨堂のお参りでは掃除はほとんど必要ありません。そのため掃除道具などの持ち物も必要なく、納骨堂は手ぶらでも気軽にお参りができるでしょう。
多くの納骨堂では、清潔で整った環境が維持されており、訪れる人々は心穏やかに故人を偲ぶことができます。また、屋内にあるため天候に左右されることが少なく、年間を通じて快適にお参りができるのも納骨堂の魅力の一つです。
納骨堂の種類で違うお参りマナー

◇納骨堂は種類によって、お参りスペースが違います
納骨堂にはさまざまな種類があり、それに応じてお参りの仕方も異なります。そのため納骨堂のマナーは規約を守るだけではなく、お参りをする場所やスペースの広さ・プライベート性によって、それぞれお参りの仕方や配慮も異なってくるでしょう。
例えば、ロッカー型の納骨堂では各スペースの前で直接お参りを行います。 ロッカーですから、上下左右に他家のスペースが並ぶ施設が一般的です。この時、一般的なお墓参りと同じように、他家のスペースは視線を合わせないようにして、家族のスペースまで進みましょう。
次に、位牌型の納骨堂では合同スペースで他の参拝者とともにお参りする施設の一般的です。一方、プライベート性の高いマンション型の納骨堂では個室に案内され、個別に設けられたプライベートな空間でお参りができます。
これらの違いを理解することで、納骨堂でのお参りがよりスムーズに行えるでしょう。
(1)スペース前でお参り
◇周囲に配慮して、必要があれば譲り合いながらお参りをします
[多いスタイル]・仏壇型納骨堂・ロッカー型納骨堂など。
沖縄のお彼岸は家拝みが多いですが、都心部など地域によって、お彼岸に集中してお参りに訪れるため、混雑する納骨堂もあるでしょう。
施設で管理誘導する納骨堂は少ないので、参拝者がお互いに譲り合い、必要があれば順番待ちをしながらお参りをします。
| <お彼岸のお参り(1)スペース前> | |
| [混雑時] | ・先に拝んでいる家族がいたら順番待ちをする |
| [周囲へ配慮] | ・お線香に火を付けない ・香りの強い供え花は避ける ・臭いの強いお供えは避ける |
| [お参り後] | ・お供え物は持ち帰る ・供え花は持ち帰る |
| [個別法要] | ・読経供養は予約・確認 |
納骨堂の規約にお供え物・供え花の持ち込み禁止が明記されてはいないでしょうか。
確認をして明記されていたら、基本は手ぶらでお参りをします。
(2)合同スペースでお参り
◇合同スペースの規約に倣います
[多いスタイル]・位牌型納骨堂・ロッカー型納骨堂など。
納骨堂に合同の参拝スペースがある場合、ほとんどが屋外になるでしょう。
こちらも位牌型納骨堂の他、ロッカー式納骨堂や仏壇式納骨堂などに多いシステムです。
屋内では個別スペース前で手を合わせる程度とし、屋外の合同参拝スペースでお供え物や献花、お線香などをあげます。
| <お彼岸のお参り(2)合同参拝スペース> | |
| [遺骨スペース前] | ・手を合わせるに留める |
| [合同参拝スペース] | ●施設の誘導に倣う ・献花台…献花 ・焼香台…焼香 ・お供え台…お供え物 ※施設で準備か、自分で準備か |
| [合同供養] | ・合同供養があるか? ・頻度を確認 ・参加の可否を確認 |
| [個別法要] | ・読経供養は施設に確認 (日時を予約) |
合同参拝スペースを設けた納骨堂の場合、多くは献花台があれば供え花が、焼香台があればお線香が許されていることが多いです。
けれどもなかには、施設で用意したお花のみ、お線香のみ、供える納骨堂もあるので、事前に納骨堂の規約を確認をしましょう。
(3)個室に案内される
◇個室に案内される納骨堂では、手ぶらのお参りが多いです。
[多いスタイル]・マンション型納骨堂・室内墓所など。
マンション型で遺骨は、納骨堂の別スペースに収蔵されています。
家族が訪れた時には個室に案内され、そこに遺骨が搬送される仕組みです。
| <納骨堂(3)個室に案内される> | |
| [特徴] | [対策] |
| [仕組み] | |
| ・ICカードによる管理 | ・ICカードを持参 |
| ・手ぶらの参拝 | ・お供え物は持ち帰る |
| [確認点] | |
| ・待つ可能性がある | ・混雑状況を確認 |
| ・電子線香の使用 | ・納骨堂で用意している |
マンション型納骨堂に多い個室に案内される仕組みですが、納骨堂施設によってルールはさまざまです。
納骨堂のなかでも個室でお参りできる点が好まれます。
一方で個室の大きさはさまざまですし、混雑時は長い待ち時間が生じる可能性もあるので、親族を連れたお参りでは、行く前に状況を確認すると、気を使わずに済むでしょう。
納骨堂のお参りで持ち帰るもの

◇屋内の納骨堂では、来た時の状態で汚さずに帰ることが基本です。
供養のひとつの形として認知される納骨堂は、上質なホテルのような室内も多く、手ぶらでのお参りを基本として、火元と臭い、汚れを残さずに帰ります。
特にマンション型など、個室に案内される施設では汚れや臭いは目立つので、注意をしてください。
[なくても良い]
・お線香
・生花
・お供え物
・アルコール類(お酒)
アルコール類(お酒など)をこぼしてしまったり、ユリなどの花粉がカーペットに付着してしまった…、などの事例があります。
また現代は納骨堂でイヌイ(一年忌)など、個別法要を執り行う人も多いです。
近年の納骨堂には、個別法要のための専用スペースを貸し出す施設も増えました。
読経供養は室内でも響くため、個別法要の必要があれば、納骨堂の施設管理者に確認をすると良いでしょう。
納骨堂のお参りでの、お供え物・供え花
◇納骨堂でのお供え物や供え花は、フェイクがおすすめです。
現代は納骨堂にお参りする家族が増えたことから、フェイクフラワーや、食べ物を模したロウソクも多く販売されています。
納骨堂でのよりスムーズなお参りのため、お供え物がOKの施設でも、下記のようなものを選ぶと良いでしょう。
・缶やビンに入った飲み物
・フェイクフラワー
・お供え物を模したロウソク
・個包装の渇き菓子
お線香も帰りに持ち帰りますが、屋内の個別スペースなので大事がないよう、そもそもお線香には火を付けない方が安心です。
まとめ:納骨堂のお参りは手ぶらでも良いです

従来のお墓参りはお墓掃除があり、お参りもお供え物とお線香、供え花を供えるため、持ち物も手順も多いでしょう。
けれども納骨堂のお参りは掃除もほとんど必要なく、周囲への配慮を考えると、むしろお供え物や生花、お線香も避けた方が安心です。
そのため基本的に手ぶらでのお参りで、問題はありません。
一方、形式的にでもお供え物をして供養をしたい場合には、納骨堂でのお参りに適した、フェイクフラワーやフェイクのお供え物が販売されています。
供えたお供え物や供え花は持ち帰り、汚れや臭いを残さずに帰ることが、納骨堂でのお参りマナーです。
・樹木葬とは?納骨後お参りはできる?タイプ別費用の目安や、メリット・デメリットを紹介
まとめ
納骨堂のお墓参りマナー
[納骨堂のお参り]
・開館時間内を厳守
・友人は家族に連絡[水と火の扱い注意]
・お酒のお供えは避ける
・お線香の火を避ける
(もしくは施設に確認)[施設をキレイに]
・生花を避ける
・お供え物は生物を避ける
・持ち帰る
・フェイクがおすすめ[混雑時]
・事前に混雑状況を確認
・個別法要は事前予約
・混雑時は待つ、譲り合う[納骨堂の基本]
・手ぶらの参拝ができる
・規約は事前に確認