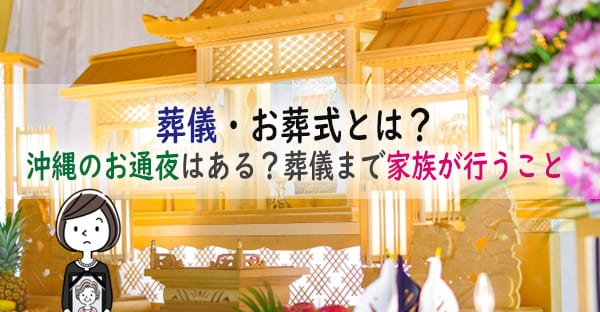
葬儀・お葬式とは?いつ行う?沖縄でお通夜は?家族が亡くなって葬儀までに行うこととは
「葬儀」とは家族を亡くした遺族や近しい人々が、故人の冥福を祈りお見送りをする儀礼です。分かってはいても家族が亡くなると戸惑うのは当然ですよね。本記事では…
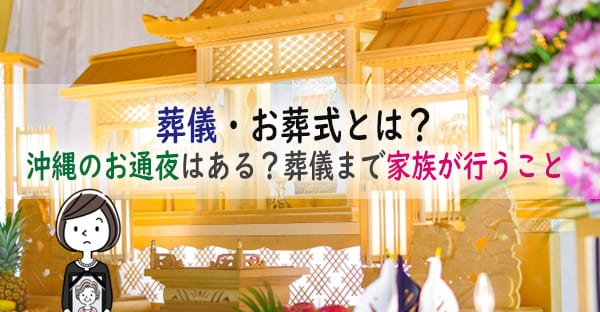
「葬儀」とは家族を亡くした遺族や近しい人々が、故人の冥福を祈りお見送りをする儀礼です。分かってはいても家族が亡くなると戸惑うのは当然ですよね。本記事では…

「供花」とは、故人の冥福を祈るために供える花々です。お通夜や葬儀の他、毎日の仏壇のお世話やお墓参りでも供えますよね。本記事を読むことで、送るタイミングで…
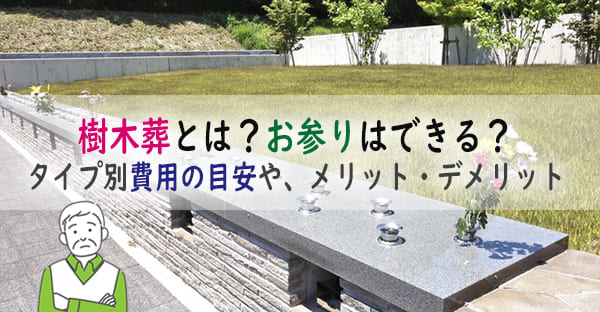
「樹木葬」とは、墓地(霊園)で樹木を墓標として遺骨を埋葬する供養の形です。いくつかのタイプによって、費用の目安も変わるでしょう。本記事では樹木葬と永代供…
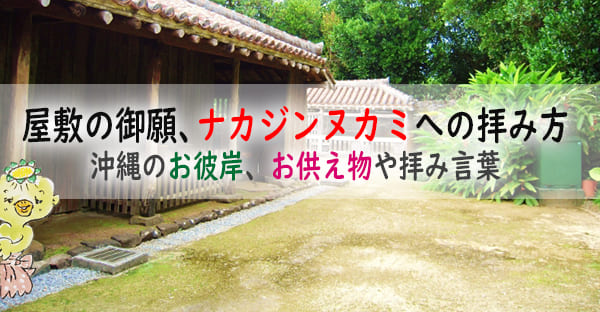
沖縄ではお彼岸になると「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」を行います。屋敷の神(ヤシチヌカミ)を巡拝する行事で、最後に拝む神様が中心を司る「ナカジンヌカミ…

沖縄のお彼岸、屋敷の御願で5番目に拝むのがフールヌカミ(トイレの神)です。フールヌカミは善きもの・悪しきものを選り分け凄いパワーで祓う力が特徴です。本記…

沖縄のお彼岸は屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)を行い、日ごろ守護いただいている6柱の屋敷の神(ヤシチヌカミ)を巡拝します。ジョウヌカミ(門の神)は4番目に…
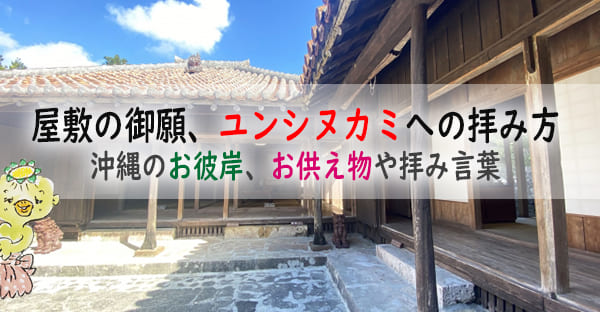
沖縄のお彼岸に行う屋敷の御願では、家の方々に鎮座される、屋敷の神(ヤシチヌカミ)を巡拝します。その3番目に拝む神様が東西南北のユンシヌカミ(四隅の神)で…
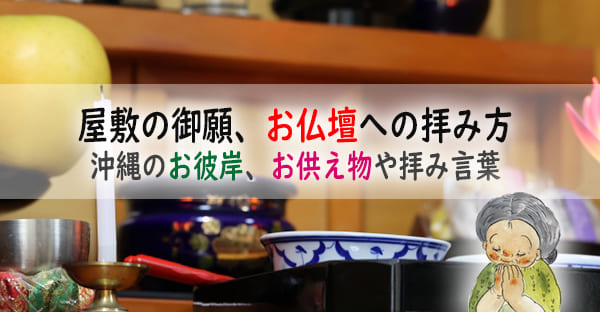
沖縄のお彼岸は「仏壇拝み」、家での供養です。また沖縄のお彼岸では屋敷の神へ拝む「屋敷の御願」を行います。本記事では、沖縄のお彼岸に行う仏壇への拝み方、「…
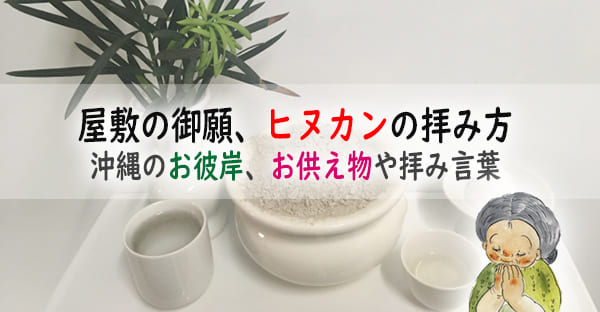
沖縄でお彼岸に行う「屋敷の御願」ではヒヌカン(火の神)へ拝みます。家を守護する神々へ感謝を捧げ、御守護を祈願する屋敷の御願で、ヒヌカンは台所を司る存在で…
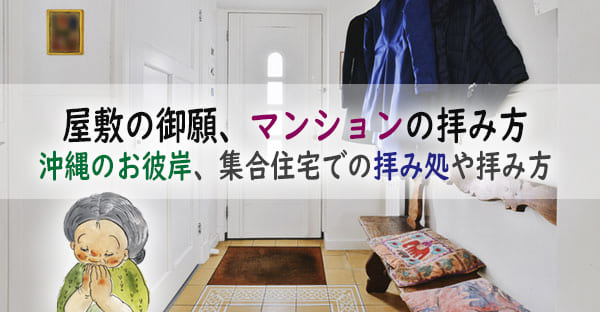
沖縄のお彼岸と言えば「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」です。家族を守護するヤシチヌカミ(屋敷の神)へ拝みますが、現代の集合住宅では当てはまらない手順も多…
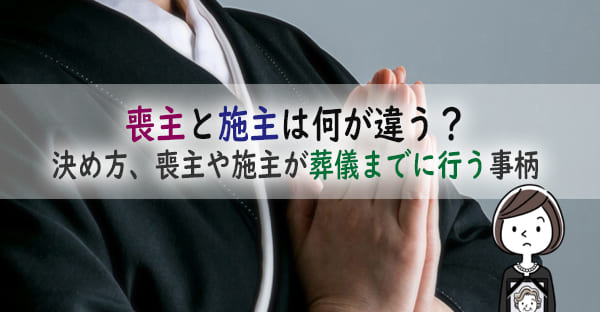
「喪主」とは葬儀の責任者・代表者を差し、「施主」は主に葬儀費用を負担するなど、実質的なサポートの役割で、一般的には同じ人が兼任します。本記事では喪主や施…
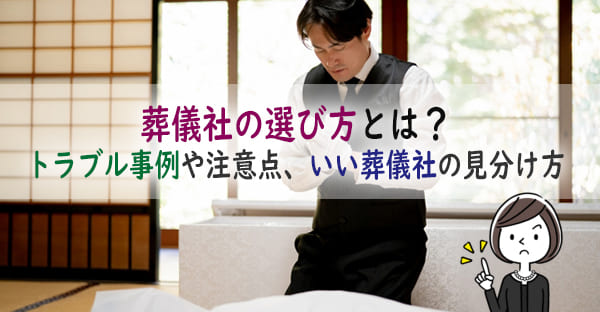
ご遺族が最初にすべき葬儀社の選び方ですが、平均3時間ほどで選ぶと言います。慌ただしいなかで選ぶため、トラブル事例や、後々後悔した声も少なくありません。本…