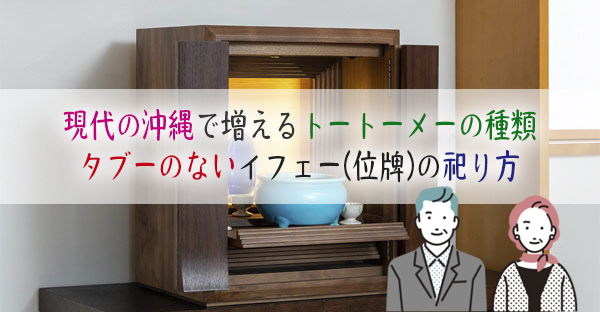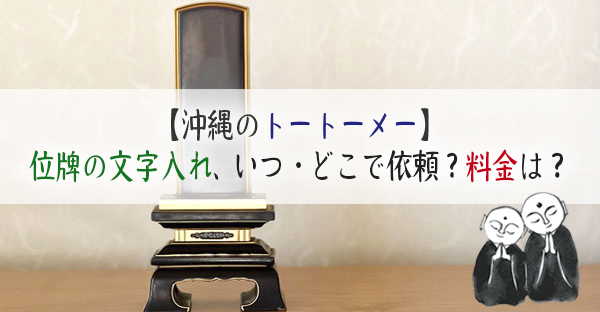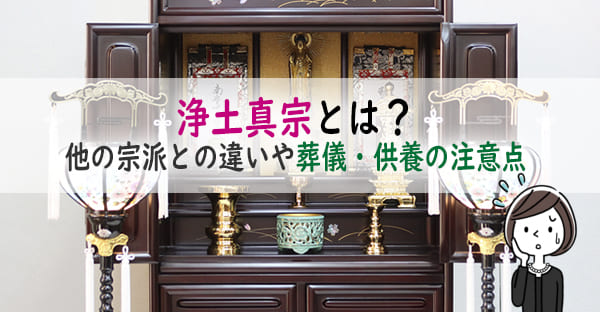現代の沖縄では、新しく仕立てるトートーメーの種類も多様になりました。
嫡男継承などタブーの多い先祖代々位牌のトートーメーを、弔い上げによりリセットする「仏壇じまい」の後、個人の魂を祀り、今後はタブーのない供養を望む沖縄の人々が増えたためです。
・今後タブーのないトートーメーを仕立てるには?
・複数のご先祖様を供養したい
・水子でもトートーメーを仕立てたい
・今後も祖霊に守っていただきたい
・今後も家を守護する存在が欲しい
今回は、先祖代々位牌としてのトートーメーを弔い上げ・お焚き上げした後、現代の沖縄で増える新しいトートーメーの種類をお伝えします。
タブーのないトートーメーを仕立てる

●現代の沖縄では、個人の魂を祀るトートーメーの種類が増えています
昔ながらのウチナーイフェー(沖縄位牌)は先祖代々位牌ですので、門中組織がある地域(沖縄本島)では、嫡男継承や祀り方など、さまざまなタブーがあるでしょう。
けれども現代の沖縄にはトートーメータブーが合わず、ウチナーイフェー(沖縄位牌)の永代供養やお焚き上げにより、タブーによる祟りをリセットする「仏壇じまい」が増えました。
・新しく先祖代々位牌としてのトートーメーを仕立てない
・一代で終わる、故人ひとりの魂を祀る
・弔い上げで終わる
そこで家族が亡くなり新しく仕立てる時、ご先祖様を代々祀るウチナーイフェー(沖縄位牌)ではなく、現代の沖縄ではトートーメーに、個人の魂を祀る種類が選ばれています。
ちなみに沖縄で弔い上げは一般的にはニジュウゴニンチ(二十五年忌)やサンジュウサンニンチ(三十三年忌)ですが、「繰り上げスーコー(焼香)」により、早く弔い上げを済ませる選択も増えました。
・沖縄のトートーメーでは4つのタブーが継承問題に繋がっている!問題を解決する方法は?
複数のご先祖様を残す

●タブーなくご先祖様を供養したい家では、ヤマトイフェー(大和位牌)が選ばれています
家族が亡くなった時に仕立てるトートーメーの他、例えば仏壇じまいの時、近しい家族の魂のみを複数残して、新しいイフェー(位牌)に移し、祀る事例も増えました。
・(両親など)夫婦二人のイフェー(位牌)を仕立てたい
・(両親と祖父母など)複数の魂を祀りたい
このような場合、現代の沖縄ではトートーメーの種類がカライフェー(唐位牌)でも、複数のイフェー(位牌)を並べて構いません。
けれども最近の沖縄では仏壇もコンパクトになり、充分なスペースがないため、カライフェー(唐位牌)ではなく、位牌札を重ねるヤマトイフェー(大和位牌)を選ぶ家も多いです。
・カライフェー(唐位牌)…個人、夫婦など二人まで
・ヤマトイフェー(大和位牌)…二人以上の位牌札をまとめられる
沖縄でトートーメータブーが残らない種類は、宮古島など離島地域で古くから祀られてきたイフェー(位牌)が多く、本州でも「繰り出し位牌」の名で見受けます。
祀り方も自由なので、A4サイズ用紙ほどの小さな仏壇から、さまざまな仏壇でカジュアルに祀る家が増えているでしょう。
・沖縄トートーメーの仕立てる方法。最初に仕立てる・すでにある家、仕立てる時期はいつ?
琉球ガラス位牌とは

●琉球ガラス位牌とは、琉球ガラスで作られた位牌です
個人の魂を祀るカライフェー(唐位牌)として選ばれる事例も多いのですが、近年では特に、女性や子ども、水子の魂を祀るイフェー(位牌)として選ばれるようになりました。
古い沖縄では、幼くして亡くなった子どもの魂はトートーメーに祀られない(神様に近い存在のため)、生家で亡くなった女性は台所に祀られる(サギブチダン)などの習わしがあります。
そこで、この純粋な存在を示すイフェー(位牌)として好まれているようです。
●特に琉球ガラス位牌で祀る家が増えています。
・水子の魂
・子ども
・女性
琉球ガラス位牌は丸いフォルムが特徴的で、純真なイメージがあるため、きっと故人の姿を思い返した時に、最も近しい形なのではないでしょうか。
手を合わせて見上げた時に、故人をイメージして会話ができるような、親しみ深いイフェー(位牌)として選ばれています。
・沖縄のトートーメーには種類がある?永代脇位牌やアジカイグァンス(預かり位牌)とは?
琉球ガラスを祖霊とする
●沖縄では弔い上げを終えた魂を、祖霊としてウタナー(御棚)に祀りますが、このウタナー(御棚)の依り代として、琉球ガラス位牌を祀る家が増えました
本来、ウタナー(御棚)は大きなウコール(香炉)のみを祀り、ウコール(香炉)の灰に宿っていただくのですが、近年では火の用心の観点から、ウコール(香炉)の代わりに琉球ガラス位牌を拝み先として祀る選択も見受けます。
・何も彫刻せずに、そのまま祀る
・本州のお墓のように「○○家」と彫刻して祀る
もともとウタナー(御棚)とは、「カミウタナー(神御棚)」などとも呼ばれ、七代以上のはるか祖霊が祀られる祭壇です。
けれども仏壇じまいが進みタブーがリセットされるようになった現代の沖縄では、弔い上げを終えたトートーメーの行く先として、ウタナー(御棚)を仕立てる家が増えました。
・沖縄トートーメーの仕立てる方法。最初に仕立てる・すでにある家、仕立てる時期はいつ?
祖霊+個人のイフェー(位牌)

●ウタナー(御棚)とお仏壇をまとめる形として、中央に祖霊を祀るイフェー(位牌)、その両脇に個人の魂を祀るカライフェー(唐位牌)の配置が増えています
先ほど琉球ガラス位牌の一例として、祖霊の位牌を仕立てるケースをお伝えしましたが、現代の沖縄では、古いトートーメーに宿るご先祖様の魂を、ひとつの位牌へ移して祀る方法も見受けるようになりました。
(1)中央に祖霊の位牌
・名前を彫らない
・もしくは「○○家」と彫刻
(2)脇に個人の位牌
・個人の名前を彫刻したもの
・複数並べても良い
…このような仏壇です。
本州の御本尊が「祖霊(それい=カミ)」となったような配置の方法で、守護の存在である祖霊の元、複数の個人の魂が守られながら祀られています。
・全国的なお仏壇の配置(祀り方)は宗旨宗派で違うの?ご本尊を中心とした仏具の配置とは
御本尊を祀る家

●また本州のお仏壇と同じように、沖縄ではトートーメーを処分した後、新しくお仏壇を仕立てた時に、御本尊を中央に配置するケースも増えました
ただ沖縄では本州のような檀家制度がありません。
「檀家制度」とは寺院墓地に先祖代々墓を建て、その寺院の信家(信徒)になる制度です。
沖縄では特定の仏教宗派を信仰せず、独自の御願文化を持つ家がほとんどなので、「浄土宗だから阿弥陀如来様が御本尊」と言う訳でもありません。
そこで今、しばしば沖縄の御本尊を祀る家で見受けるのが、十二支の御本尊です。
沖縄の御願文化では十二支を重視しているためでしょう。
(1)午年…勢至菩薩(せいしぼさつ)
(2)丑年・寅年…虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)
(3)辰年・巳年…普賢菩薩(ふげんぼさつ)
(4)子年…千手観音(せんじゅかんのん)
(5)酉年…不動明王(ふどうみょうおう)
(6)卯年…文殊菩薩(もんじゅぼさつ)
(7)戌年・亥年…阿弥陀如来(あみだにょらい)
(8)未年・申年…大日如来(だいにちにょらい)
となります。
ただ本州の仏教宗派による御本尊とは違い、現代の沖縄は独自の御願文化がもともとあるため、どちらかと言えば無宗教に近いです。
そのため御本尊も「敢えて選ぶならば」と言うところで、沖縄には観音信仰もあるため、好きな観音様を祀るなど、比較的自由な傾向にあるでしょう。
・「檀家制度」とは、「戒名」は必ず必要?菩提寺(檀那寺)との関係性
御本尊を祀る時に拝む場所
●近年仏壇を仕立てて御本尊を祀る沖縄の人のなかには、祀るに当たり、寺院へお参りをする様子を見受けます
ただし、こちらも現代の沖縄でしばしば見かけるものであり、仏教のように縛りのあるものではありません。
(1)盛光寺(せいこうじ)
・大日如来
(2)西来院達磨寺(さいらいいんだるまでら)
・文殊菩薩
・阿弥陀如来
(3)安國寺(あんこくじ)
・不動明王
(4)首里観音堂(しゅりかんのんどう)
・千手観音
・虚空蔵菩薩
・普賢菩薩
・勢至菩薩
沖縄で祖霊であるトートーメーを永代供養やお焚き上げで処分した時、個人の位牌を祀ると「守護の存在に守られながら、ゆったりと眠って欲しい」と感じる遺族もいるようです。
本州でも今では無宗教の家が増えましたが、菩提寺があればお仏壇の中心に御本尊を祀るため「守護の存在」がありますが、沖縄ではそれがトートーメーでした。
それに代わるものとして、御本尊を祀る選択があったのでしょう。
・沖縄の『首里十二か所巡り』とは☆人々を守る干支の守り本尊様を迎え入れる
沖縄らしさを残した仏壇仏具

●大きな沖縄仏壇やウチナーイフェー(沖縄位牌)を仏壇じまいしても、沖縄らしさを残したい人々に、やちむん仏具が人気です
沖縄独自の祖霊信仰を残しながら、現代の暮らしに見合ったムリのない、カジュアルな先祖供養は、仏壇じまいによって実現しますが、沖縄らしさが少なくなると、心配する人もいます。
そこで現代の供養の形に合わせつつ、沖縄らしさを残した仏壇仏具が注目されるようになりました。
①仏壇
・琉球松壁掛仏壇
②仏具
・やちむん仏具
ローコスト住宅やオシャレな木造住宅にも違和感なく、それでいて沖縄らしさを残す仏壇仏具が、さまざまに試行錯誤されています。
沖縄ならではの御願文化を残しながら、ムリのない供養が実現するでしょう。
[参考]琉球松を使用した壁掛け仏壇
・【沖縄の仏壇】六種供養で最小限・心重視の供養を。最小限の仏具とは
お線香は日本線香へ変化
●コンパクトな仏壇が広がり、お線香も日本線香を1本~5本供える家が増えています
家の二番座の壁一面を占めていた昔の沖縄仏壇とは違い、時にはA4用紙サイズよりも小さなコンパクト仏壇にトートーメーを祀り供養するには、今までの供養の仕方では、火の元が心配です。
●仏壇に伴い、ウコール(香炉)が小さくなり…、
・日本線香を1本~5本
・煙の少ない備長炭
・早く燃え尽きる、半分の長さ
・灰ではなくさざれ石
・お供え物は似せたロウ細工
…などなどが増えました。
特に夫婦共働きが増えた現代の沖縄では、騒がしい朝にお線香を上げても出発時にはお線香が終わるよう、短い長さが選ばれるようになっています。
折る方法もあるでしょうが、「お線香を折るのは良くない」と嫌がる人もいるためです。
・現代の沖縄でトートーメーは継承すべき?意識調査で分かる新しいトートーメー・役割の形
最後に
以上が先祖代々位牌としてのトートーメーをリセットした後、現代の沖縄で増えるトートーメーの種類です。
また、近年の沖縄ではトートーメータブーをリセットするにあたり、仏壇じまいや墓じまいも増えていますよね。
特に沖縄の仏壇やお墓は、門中組織により継承されてきたので、継承問題も深刻です。
そこで終活が広がる沖縄で、トートーメーやお墓の継承負担を子どもや孫の代まで引きずることのないよう、高齢の人々の間で仏壇じまいや墓じまいが進んでいます。
この他、門中組織から独立する家も増えていますよね。
そこで自由になった現代の沖縄では、トートーメーの種類だけではなく、仏壇や祀り方もカジュアルなものが選ばれるようになりました。
・【沖縄のトートーメー】仏壇をコンパクトに!今の沖縄で人気、暮らしに合う3つの種類
まとめ
現代沖縄で増えるタブーのないイフェー(位牌)の祀り方
●トートーメータブーを復活させない
・先祖代々位牌としてのトートーメーを仕立てない
・一代で終わる、故人ひとりの魂を祀る
・弔い上げで終わる●個人の魂を祀る
・カライフェー(唐位牌)…二人まで
・ヤマトイフェー(大和位牌)…二人以上の位牌札
※ヤマトイフェーは全国的に「繰り出し位牌」●琉球ガラス位牌の需要
・水子の魂
・子ども
・女性●ウタナー(御棚)にイフェー(位牌)
・何も彫刻せずに、そのまま祀る
・「○○家」と彫刻して祀る●祖霊+個人のイフェー(位牌)
●ご本尊+個人のイフェー(位牌)
・沖縄では家長の干支のご本尊が多い
(全国では家の宗派に倣う)