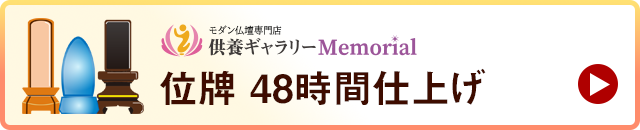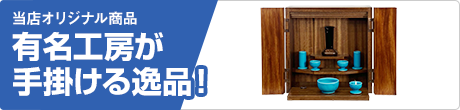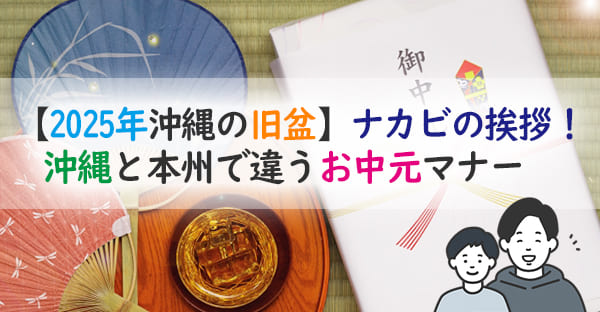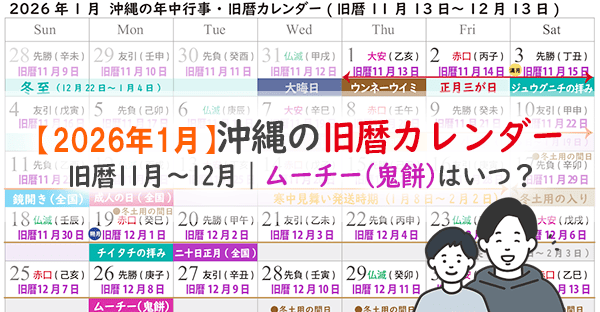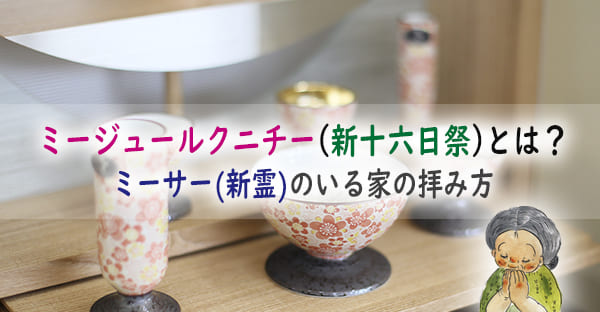・沖縄で旧盆の中日「ナカビ」の過ごし方は?
・沖縄の旧盆ではナカビに挨拶まわりをするの?
・沖縄で旧盆ナカビのお供え物は?
沖縄の旧盆で「ナカビ(中日)」とは「ナカヌヒー(中の日)」とも呼ばれ、初日「ウンケー(御迎え)」と最終日「ウークイ(御見送り)」に挟まれた中の日を差します。
沖縄で旧盆は毎年旧暦7月13日~15日ですので、ナカビ(中日)は旧暦7月14日です。
2025年、沖縄の旧盆でナカビ(中日)は9月5日(金)!
本記事を読むことで、2025年沖縄の旧盆、ナカビ(中日)の日程や過ごし方、拝み方が分かります。
沖縄の旧盆|ナカビ(中日)の過ごし方

◇親族が挨拶回りをする日です
沖縄の旧盆でナカビ(中日)は、先祖代々位牌「トートーメー」を祀る実家や義実家などのムチスク(本家)へ、親族が挨拶回りをしてきました。
●ご仏壇のない家では、ご仏壇のある親族の家を周り、ご先祖様にご挨拶をします。
挨拶に行く時には、約千円~2千円ほどの手土産を「お中元」として持参するのも風習のひとつです。一方でトートーメーを祀るムチスク(本家)では、訪問に来る親族を迎え入れもてなします。
基本的に沖縄では父方の血族で集まる「門中(むんちゅう)」文化がありますが、沖縄の旧盆では、夫婦であれば、両方の実家へ挨拶回りをすることもあるでしょう。
そのため沖縄の旧盆では、ナカビ(中日)に向けてお中元を複数準備する家が多いです。
沖縄の旧盆でナカビのお供え物は?

◇昔ながらの風習では、ナカビにスーミン汁を供えます
ご先祖様がいらっしゃる旧盆の3日間(もしくは4日間)は、家族と同じようにご先祖様へも朝ごはん・昼ごはん・晩ごはんの3食を供えます。
沖縄で従来から現代に残る旧盆では、ナカビ(中日)の昼食にスーミン汁(素麺汁)、おやつにあまがしを供える風習がありました。
ちなみに沖縄では朝ごはん・昼ごはん・晩ごはんを下記のように呼びます。
| <ナカビ(中日)のお供え物> | |
| [全国的な呼び方] | [沖縄の呼び方] |
| ①朝ごはん | ・ヒティミティムン |
| ②お昼ごはん | ・アサバン |
| ③おやつ | ・マドゥヌムン |
| ④晩ごはん | ・ユウバン |
ご仏壇がある家は親族など、御先祖様へ手を合わせに来る訪問客を迎え入れますが、多くはお昼前後からの来客となるでしょう。
旧盆のナカビ(中日)には、ご先祖様へとともに、来客する親族へもスーミン汁やあまがしを供えます。
[沖縄の旧盆2025年の日程]
・【沖縄の旧盆】2025年は9月4日(木)~6日(土)☆旧盆3日間の進め方を解説
お仏壇へ供える注意点
◇お仏壇に供える時には、お箸を添えます
お仏壇はご先祖様へのお供えなので、お膳にごはんを整えたらお箸を添えます。
一方で神様であるヒヌカン(火の神様)などにはお箸を添えません。
お仏壇には故人1人の御位牌を祀っている家もあれば、トートーメーとして多くのご先祖様を祀る家もありますよね。
この場合、故人の人数によって、お供え物に添えるお箸の数も変わります。
| <ご先祖様へお箸を供える> | |
| [ご先祖様の人数] | [お箸の数] |
| ①1人の御位牌 | ・1膳 |
| ②複数の御位牌 (トートーメーなど) | ・複数のお箸 |
祀る故人の人数に合わせてお箸を添えますが、トートーメーなど多くのご先祖様を祀る場合は、何人でも2膳を添える家もあるでしょう。
また箸休めの酢の物としてキュウリの酢の物など「ウサチ(酢の物のおかず)」も添えます。
ちなみに最終日のウークイ(御迎え)で出す重箱料理の「ウサンミ(御三味)」では、重箱の上にお箸を乗せて、供えてください。
[最終日ウークイ]
・【沖縄の旧盆】2025年最終日ウークイは9月6日!ご先祖様のお見送りや、お供え物
沖縄の旧盆:ナカビの朝

◇ナカビ(中日)の朝は、朝ごはんの御膳を供えます
沖縄の旧盆でナカビ(中日)の朝ごはんは「ヒティミティムン」です。
朝ごはんの御膳はご飯と汁物、酢の物などの副菜が基本ですが、家族がいただく朝ごはんを供えても問題はありません。
豚三枚肉の煮付けなどを供えても良いですが、ご馳走のジューバク(重箱)に詰めたご馳走は基本的に、最終日ウークイで、夕方頃に供えます。
<2025年沖縄の旧盆:ナカビの朝ごはん>
●御膳に乗せ、お箸を添えます
・ご飯(若しくはお粥)
・ウサチ(酢の物)
・汁物
沖縄では旧盆のナカビに、前日のショウガの葉を混ぜたジューシー(沖縄風炊き込みご飯)「ウンケージューシー(御迎えジューシー)」をお粥にする家もあります。
お粥などにしても喜ばれるでしょう。
ナカビの朝はヒヌカンへも拝む

◇「ヒヌカン(火の神)」とは、台所に祀る家を守護する神様です
お台所にヒヌカン(火の神様)がいらっしゃる家では、お仏壇にお供えをする前、朝一番でヒヌカンにも拝みます。
ヒヌカン様へはいつも通りの拝みで問題ありません。
ミジトゥ(お水)とウブク(ごはん)をお取替えして、下記のように唱えて手を合わせます。
<2025年旧盆:ヒヌカンへナカビの拝み>
「ウートゥートゥー、ヒヌカンヌ ウカミガナシー、
(あな尊き ヒヌカンの神様)
チューヤ、ヒチグァッチヌ ナカビヌヒ ナトゥーリビン、
(今日は旧盆のナカビの日です)
ウブンヌ ウトゥムチ リッパニシミティ クィミスーリー。
(お盆のおもてなしを無事にさせてください)」
沖縄の旧盆では、ヒヌカン(火の神様)がお台所にある家では、前日のウンケーですでにご報告するので、ナカビ(中日)は簡単なご報告です。
ヒヌカン(火の神様)は神様なので、ウブク(ごはん)にお箸を添える必要はありません。
ヒヌカンへ拝む人
◇主に台所を担い、ヒヌカンのお世話をする家族が拝みます
かつての沖縄では、台所を担ってきた女性の間で代々継承されてきたため、ヒヌカンをお世話する家の女性以外が触れてはならないとされてきました。
けれども共働き・男女平等が進む現代では、台所を主に担う家族であれば、男性であってもお世話をしても良いでしょう。
ただし主にヒヌカンのお世話をする家族以外は、ヒヌカンに触れることを控えます。
不安定な現代、家計安泰を守護するとして、新たに仕立てる家が増えました。
[ヒヌカンの始め方]
・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説
沖縄の旧盆:ナカビの昼

◇昔ながらの旧盆ナカビ(中日)の昼ごはんは、スーミン汁です
沖縄の旧盆で、ナカビ(中日)の昼ごはんは沖縄の言葉で「アサバン」と呼びます。
従来から沖縄の旧盆では、ナカビ(中日)のアサバンに「スーミン汁(素麺汁)」をいただいてきました。
<旧盆ナカビ(中日):昼ごはん>
・スーミン汁(素麺汁)
・ウサチ(酢の物)
冷たい素麺を供える家庭も多くありますが、昔からある沖縄の風習で「スーミン汁」は温かい汁でいただきます。
全国的な呼び名では「にゅうめん」ですね。
具などはシンプルなスーミン汁が多いですが、具だくさんでも、特に決まり事はありません。
沖縄南部のふかしイモ

◇沖縄南部の一部地域では、ふかしイモの輪切りを供えます
沖縄本島の多くの地域でスーミン汁を供えますが、南部などでは豊作への感謝も込め、さつまイモなどのイモ類をふかして輪切りにし、キュウリとともに供える地域も多いです。
| <南部など旧盆ナカビの昼ごはん> | |
| ①イモ類をふかしたもの | ●イモの種類 ・ターンム(田芋) ・さつまイモ ・チンヌク(里芋) …など ●調理 ・ふかす ・輪切りにする |
| ②キュウリのおかず | ・輪切りにする ・酢の物 …など |
ご先祖様が家に帰省する旧盆は、先祖供養行事ではありますが、ご先祖様をお迎えしもてなすお祝い行事として行われます。
そのため沖縄ではお祝いで出す食材「イモ」を供える家も多いのです。
なかでも赤い(紫)色のベニイモや、ターンム(田芋)などはお祝いの意味が強くなります。
[ムチスク(宗家)を訪問する手土産]
・【沖縄の旧盆】ナカビ(中日)の挨拶まわり☆お中元(手土産)タブーは?行けない時は?
沖縄の旧盆:ナカビのおやつ

◇沖縄の旧盆でナカビ(中日)に供えるおかずは「あまがし」が多いです
沖縄で旧盆ナカビ(中日)に供える、3時のおやつを「マドゥヌムン」と言います。
現代はお菓子やアイスなど、すぐにおやつを手に入れることができますが、沖縄で古くから親しまれてきた子どもが喜ぶおやつは、甘い金時豆と氷が美味しい「あまがし」でした。
<沖縄旧盆ナカビのおやつ>
・あまがし
・ぜんざい
…など。
今でも沖縄ではぜんざい屋さんが人気で、観光客が訪れるお店も多いですよね。
スーパーなどで沖縄ぜんざいも販売しているので、用意しやすいのではないでしょうか。
ただ現代の暮らしに合わせ、また故人の生前の嗜好を考慮して、違うおやつをお供えしても問題はありません。
[あまがしの作り方]
・沖縄の「あまがし」とは?沖縄ぜんざい「あまがし」は邪気も祓う?親子で作る簡単レシピ
沖縄の旧盆:ナカビの夜

◇沖縄旧盆でナカビ(中日)では、晩ごはんの御膳を供えます
沖縄旧盆でナカビ(中日)に供える晩ごはんは「ユウバン」です。
ご飯とみそ汁、おかずと副菜を揃えた御膳を供えますが、現代では家族がいただく夕食をそのまま供える家庭が増えました。
<沖縄旧盆ナカビ(中日)の晩ごはん>
●ユウバンの御膳
・ご飯
・ウサチ(酢の物)
・汁物
・煮物
※お箸を添える
ここでも、ご先祖様へ供えるお膳にはお箸を添えます。
お仏壇へお供えをする時には、お線香を供えて「ウートゥートゥー(あな尊い)」と拝み供えてください。
これは分家が訪問する際に、手土産である供物をお仏壇へ供える時にも同じです。
ジューバク(重箱)のおかずも良い
◇沖縄旧盆ナカビ(中日)のユウバンには、煮付けのおかずを供えます
必ずではありませんが、沖縄旧盆でナカビ(中日)に供えるおかずには、豚三枚肉の煮付けや大根やごぼうの煮しめなど、煮付けを供える家庭が多いです。
沖縄旧盆では最終日のウークイ(御送り)には、重箱に詰めたご馳走「ジューバク(重箱)」を供えます。
そのためナカビ(中日)には詰めるご馳走の調理を済ませる家庭も多く、そのおかずをお皿に盛って供えることがあるためです。
<おすすめの煮物おかず>
・厚揚げ
・大根
・シブイ(冬瓜)
・豚三枚肉
…など。
ちなみにジューバク(重箱)に供えるご馳走は、天・地・海、3つの尊い幸を表す「ウサンミ(御三味)」と沖縄では呼ばれます。
また御膳にご馳走を取り分けたおかずは、「ウチャワキ(お茶脇)」と呼ばれてきました。
ジューバク(重箱)には魚天ぷらなどを詰める家庭も多いですが、天ぷらなどは最終日ウークイ当日に揚げることが多いため、煮付けが多くなるのでしょう。
[ウサンミ(御三味)レシピ]
・沖縄の旧盆で供える重箱料理、定番おかずの作り方☆豚三枚肉の煮付けや昆布の結び方は?
沖縄の旧盆:現代のナカビ

◇現代は家族の食事を一緒に供えるナカビも多いです
現代の沖縄では、旧盆でもナカビ(中日)でも家族がいただく食事をそのまま御膳に配置してお供えし、一緒にいただくスタイルも増えています。
ここまでお伝えしてきた沖縄の旧盆でナカビ(中日)に供えるお供え物は、昔から続く伝統的なお供え物「ウサギムン」です。
けれども現代では、もっと気楽に供える家庭も増えました。
背景にはトートーメーを永代供養などで処分する「仏壇じまい」があるでしょう。
故人の好きだった食べ物でも良い
◇家族の御位牌には、故人の好きだった食べ物も多いです
先祖代々位牌トートーメーを永代供養やお焚き上げで処分した後、配偶者や両親など、近しい家族の御位牌として、カライフェー(唐位牌)を仕立てる家庭が増えました。
面識のないご先祖様ではなく、生前を知る故人を供養する目的が大きくなりつつあります。
<現代ナカビ(中日)の特徴>
・家族が食べる食事を一緒に供える
・故人が生前に好きだった食べ物を供える
沖縄の旧盆で、ナカビ(中日)はご先祖様と穏やかに1日を過ごす日です。
そのためご先祖様と共食し供に過ごすことが目的ですので、お仏壇を囲んで家族が食事を共にいただくならば、失礼にはならないでしょう。
[トートーメーの継承問題]
・沖縄のトートーメーとは?タブーで増える沖縄のトートーメー継承問題を解決する方法とは
沖縄の旧盆:ナカビのグイス(拝み言葉)

◇ごはんやおやつを供える時「ぜひいただいてください」と拝みます
沖縄の旧盆のなかでもナカビ(中日)は、そんなに畏まった拝み事はありません。
お食事を供える際「昼食をお供えしますよ、ぜひいただいてください」と、ご先祖様にお声掛けをするだけです。
<沖縄の旧盆:ナカビの拝み方>
「ウートゥートゥー ウヤフジガナシー、
(あな尊き ご先祖様)
マグクルクミティ アサバン ウサギティーイ ビングトゥ。
(まごころを込めた昼食を お供えいたしました。)
ウキトゥイジュラスァ ウタビミスーリー。
(受け取ってください。)」
基本的にはお供え物をする度に、供える家族はご報告をします。
また沖縄でお倫(おりん)のある仏壇は少ないですが、お倫があれば1回鳴らすと「これからご挨拶をします」との合図です。
拝み言葉は家や地域によって習慣も違いますので、一例として捉えていただければ良いでしょう。
沖縄のグイスは現代語でも良い
◇現代の言葉で拝んでも良いです
沖縄のグイス(拝み言葉)は、沖縄言葉でご先祖様と会話しています。
沖縄拝み言葉を表す「グイス」は全国的な呼び方で「祝詞(のりと)」ですが、沖縄のグイスは沖縄言葉でご先祖様へ話し掛ける「拝み言葉」です。
神様へ使えるユタやノロであれば、キチンとしたグイスを唱える必要もありますが、家庭で家族が故人やご先祖様へ話しかけるのであれば、現代の言葉でも問題はありません。
地域によっても違いますし、例えば「ウサガティンクィミスーリー(召し上がってください)」などの言い回しでも良いでしょう。
昔ながらの沖縄言葉が難しい時にも、気負わずに現代の言葉で、ご先祖様に「ウートゥートゥー」と手を合わせ、語り掛けてください。
沖縄の旧盆:ナカビで供えるお線香

◇お供え物を供える時には、サンブンウコー(三本御香)で良いでしょう
沖縄の旧盆でウンケー(御迎え)やウークイ(御送り)など、家長を中心に拝むウグァン(御願)を行う際には、家長は日本線香12本分を意味する「ジュウニフンウコー(十二本御香)」が基本です。
一方、ヒヌカン(火の神)には日本線香15本分を意味する「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」となります。
けれども沖縄の旧盆でナカビ(中日)での拝み事は、基本的に家族が3食、そしておやつを供えるだけですので、日本線香3本分を意味する「サンブンウコー(三本御香)」で良いでしょう。
| <沖縄の旧盆:ナカビのお線香> | |
| ①ヒヌカン(火の神) | ●ジュウゴフンウコー(十五本御香) ・日本線香…15本、もしくは5本 ・ヒラウコー…タヒラ半(2枚半) |
| ②お仏壇へ食事を供える | ●サンブンウコー(三本御香) ・日本線香…3本、もしくは1本 ・ヒラウコー…半ヒラ(半分) |
| ③お客様が供える | ●サンブンウコー(三本御香) ・日本線香…3本、もしくは1本 ・ヒラウコー…半ヒラ(半分) |
「ヒラウコー」とは沖縄のお線香です。
漢字で書くと平らなお線香を表す「平御香」で、日本線香6本分が1枚の板状になっています。
ヒラウコーには香りがなく価格も安い点が特徴です。
小さなご仏壇での注意事項
◇小さなウコール(香炉)のお線香は少なく供えます
現代は小さなお仏壇が増え、お仏壇のサイズに合わせてウコール(香炉)も小さくなりました。
沖縄では日本線香12本分、15本分と全国的なお線香の本数と比べると、たくさんのお線香を一度に供えます。
そのため沖縄では、たくさんのお線香にも耐えられるウコール(香炉)を使用しますが、小さなウコール(香炉)は対応していないものも多いです。
小さなウコール(香炉)でたくさんのお線香を供えてしまうと、パリンと割れてしまうことも多いので、日本線香にするなど、本数を少なく調整して供えてください。
旧盆用にウコール(香炉)を準備する
◇旧盆期間のみ、大きなウコール(香炉)を使用する家庭もあります
小さなお仏壇・小さなウコール(香炉)に新調したものの、沖縄の旧盆でナカビ(中日)の来訪者が多いムチスク(本家)などでは、旧盆用に従来の大きなウコール(香炉)を準備するケースも増えました。
家の建て替えや引っ越しで大きな沖縄仏壇から、小さなお仏壇へ取り替えた家庭などに多い対策です。
最終日ウークイには旧盆用に揃えた大きなウコール(香炉)を、そのまま門前まで持って行く家庭も見受けます。
沖縄の旧盆:ナカビにお中元が届いたら?
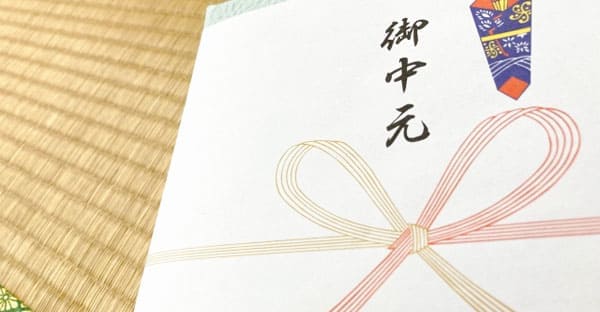
◇ナカビ(中日)にお中元が届いたらお仏壇に供えます
沖縄の旧盆ではナカビ(中日)に分家である親族が、手土産を持って訪問しますよね。
訪問できない分家から、旧盆期間やナカビ(中日)にお中元が届いた場合、手土産の代わりですのでお仏壇に供えましょう。
送り主は「訪問できずにごめんなさい」の気持ちを込めて送っています。
そして訪問できなかった親族の代わりにお線香を供えて、最終日ウークイにはウチカビ(打ち紙)も焚いてあげましょう。
[沖縄の旧盆で訪問できない時は?]
・【沖縄の旧盆】ナカビ(中日)の挨拶まわり☆お中元(手土産)タブーは?行けない時は?
お中元の供え方
◇お中元の上にウチカビ(打ち紙)3枚を添えます
沖縄の旧盆ではナカビ(中日)にお中元をご仏前に供える際、ウチカビ3枚をお中元の上に置きますが、送られたお中元を代理で供える時にも同じです。
供える時にはご先祖様に「誰から送られてきたか」をご報告して、代理でお線香を供えて拝み、最後にウチカビ(打ち紙)を添えます。
| <沖縄の旧盆:お中元の供え方> | |
| ①代理でお線香を供える | ●サンブンウコー(三本御香) ・日本線香…3本、もしくは1本 ・ヒラウコー…半ヒラ |
| ②送り主をご報告 | 「○○○○(住所)、○○(干支)の○○○○(名前)からです。」 |
| ③ウートゥートゥー | ・合掌して拝む |
| ④ウチカビを添える | ・ウチカビ(打ち紙)…3枚 |
家長であっても送られたお中元を供える時は、送り主の代理ですので、お線香はサンブンウコー(三本御香)で良いです。
お中元の上の添えたウチカビ(打ち紙)は、最終日ウークイ(御送り)の際に一緒に焚きます。
[ウークイの進め方]
・【沖縄の旧盆】2025年最終日ウークイは9月6日!ご先祖様のお見送りや、お供え物
近年増えた、分家の「家拝み」
コロナ禍を経て、沖縄の旧盆に訪問できない分家が、それぞれに位牌を仕立てる「位牌分け」も見受けるようになりました。
全国的には遺骨を分ける「分骨」が一般的ですが、本州でも一部地域で位牌分けの風習を見受けます。
沖縄に多い方法は、御位牌のみを分ける位牌分けが多い傾向です。
特に頻繁にお墓参りをしない沖縄では、「お墓と位牌は繋がっている」との考え方があるため、御位牌を通して供養する分家も見受けるようになりました。
まとめ:沖縄の旧盆でナカビは挨拶回りです

初日のウンケー(御迎え)・最終日のウークイ(御見送り)に挟まれた、沖縄の旧盆ナカビは、ご先祖様を囲んで穏やかに過ごす1日です。
お仏壇のない分家では、約千円~2千円ほどの手軽な手土産を持参し、ご先祖様や故人を祀るムチスク(本家)を訪れ、お仏壇に手を合わせ、お仏壇を囲んで時を過ごします。
一方お仏壇のある家では、家族の食事と一緒に朝ごはん・昼ごはん・夜ごはん、そしておやつをお供えする1日です。
お仏壇へ供えたお食事は、少し経ったらお供え物を下げる「ウサンデー」を行い、下げたお供え物は家族でいただきます。