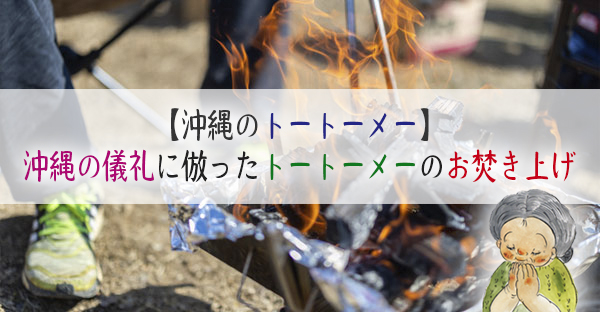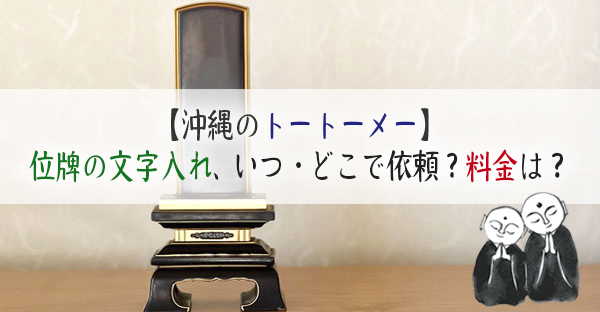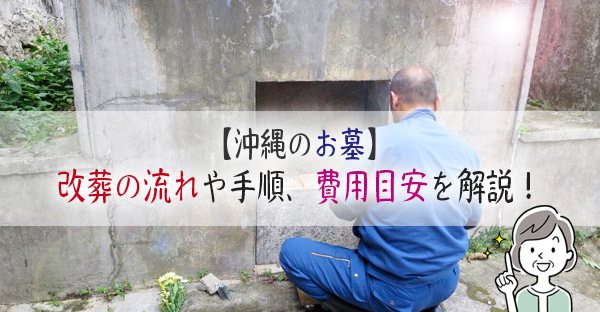お世話が大変・継承者がいないなどの理由で、お仏壇を閉じる「仏壇じまい」が進む沖縄では、トートーメーのお焚き上げに関する相談が多いです。
沖縄ではトートーメータブーを恐れ、お焚き上げを躊躇する声もありますが、地域によって昔から、沖縄の儀礼に倣いトートーメーを弔い上げ、お焚き上げをしてきました。
・沖縄のトートーメーを処分する方法は?
・トートーメーの祟りが怖い
・沖縄の儀礼でトートーメーのお焚き上げがしたい
・僧侶やユタに頼まない方法はある?
・自分達でお焚き上げがしたい
今回は仏壇じまいに伴い、沖縄でトートーメーのお焚き上げを検討している人へ向け、僧侶やユタさんに依頼せず、家で行う昔ながらの方法を解説します。
沖縄でトートーメーのお焚き上げとは

●沖縄ではトートーメーを弔い上げ、お焚き上げをすることで、ご先祖様の魂は我のない家を守護する「カミ(神)」「祖霊」となります
昔ながらの沖縄ではトートーメーのお焚き上げは、弔い上げのスーコー(焼香)となるサンジュウサンニンチ(三十三年忌)が一般的でしたが、継承者問題が深刻化する現代の沖縄では、「繰り上げスーコー(焼香)」により、早く済ませる家が増えました。
・ご先祖様の我が無くなり祖霊となる
・トートーメータブーが無くなる
・スーコー(焼香)が無くなる
沖縄ではトートーメーのお焚き上げにより、我が無くなった家の守護神としての存在を、「祖霊」とも「カミ(神)」とも言います。
それぞれに個がないので、家を守護するひとつの集合体のような存在です。
ご先祖様の我が無くなるため、物事の良し悪しを人の感情で判断しなくなります。
その昔は「亡くなってから七代以降」と言われましたが、現代の沖縄では、トートーメーがお焚き上げされ、煙とともにウティン(御天)へ昇天することで、祖霊・カミ(神)になると考えられるようになりました。
・沖縄の先祖代々位牌「トートーメー」とは?そもそも家を守護する「祖霊信仰」ってなに?
トートーメーを処分する方法は?
●現代の沖縄では儀礼に倣ったトートーメーのお焚き上げの他、永代供養などの選択肢も増えました
今回は沖縄の儀礼に倣ったトートーメーのお焚き上げについて解説していますが、現代の沖縄では寺院や民間霊園も増え、沖縄の儀礼以外にもさまざまなトートーメーの処分方法が増えています。
[1]沖縄の儀礼によるお焚き上げ
●マブイ(魂)を抜くヌジファー(魂抜)
・ユタさんに依頼する
・家で行う
[2]寺院・神社によるお焚き上げ
●ご住職や神主による閉眼供養(お性魂抜き)
・寺院や神社に相談する
[3]位牌堂でトートーメーの永代供養
●ご住職などによる閉眼供養(読経供養)
・位牌堂を設けた霊園に相談する
・寺院のご住職に相談する
…この他、子どもが大きくなり継承する可能性など、いつか改めて祀る予定がある場合、沖縄ではトートーメーをお焚き上げせず、寺院や霊園で一時的に預かってくれる施設もあるでしょう。
ただし家で行う(自分達で行う)、沖縄の儀礼に倣ったトートーメーのお焚き上げの選択以外では、相応の料金(約3万円ほど~)を支払います。
・沖縄のトートーメーでは4つのタブーが継承問題に繋がっている!問題を解決する方法は?
沖縄の儀礼に倣った、トートーメーのお焚き上げ

●墓前にトートーメーを持っていき、名前を削って焚きます
基本的にはシジュウクンチ(四十九日)に行う仮位牌のシライフェー(白木位牌)や、トートーメーを新調する際の、新旧交代の儀礼と同じですが、お焚き上げ後の灰の扱いやお供え物の有無などがそれぞれ変わるでしょう。
昔ながらの儀礼では墓前で行ってきましたが、自宅の庭でも問題はありません。
※近年では屋外でのゴミ等焼却を禁止する自治体が増えました。
野外でお焚き上げする際、自治体の条例などに問題がないか確認をしてから行うようにしてください。
●持ち物
・トートーメー
・ナイフ
・マッチやチャッカマンなど
・灰を入れる容器
●お焚き上げの手順
[1]名前の部分をナイフなどで削る
[2]削った部分を墓前で焼却する
[3]続けて位牌札、位牌立てを燃やす
[4]燃え尽きた灰のなかから、指で3回つまむ
[5]容器などに取り分けておく
[6]残りの灰を庭や家周辺の土地に埋める
沖縄の儀礼に倣ったトートーメーのお焚き上げでは、
「新しいイフェー(位牌)をご用意いたしましたので、どうぞ移ってください。」
と、現代の言葉で良いのでお伝えしてから進めると、なお良いです。
ヒヌカンへのご報告
●また沖縄でヒヌカンを祀る家は、トートーメーのお焚き上げに限らず、儀礼(御願)を行う日の朝にご報告します
ヒヌカンは家を守護する最高位の神として、(以前は)女性が中心に担ってきました。
(トートーメーは男性が担うものとされています。)
ヒヌカンはこの世の神々様との繋ぎの役割を果たしてくださるため、沖縄では墓前でトートーメーのお焚き上げをするにあたり、祖霊やお墓を守るヒジャイヌガミ(左の神)様へご挨拶をして、許可を取ってくれるでしょう。
「本日はトートーメーのお焚き上げをする日です。
どうぞ無事に済ませることができますように…、ウートゥートゥー。」
このような内容をご報告すれば、こちらも現代の言葉で問題はありません。
ヒヌカンへお焚き上げを行う事情を話せば、祖霊やお墓のご先祖様も、事情を理解してくれます。
トートーメータブーを恐れる場合

●ウグァンブスク(御願不足)やタブーによる、トートーメーの祟りを恐れる場合には、ユンヂチ(閏月)やタナバタ(七夕)に行うと良いです
地域や門中によって習わしはさまざまですので、日取りを選んだからと言ってトートーメーをお焚き上げすること自体に反対する親族はいるかもしれません。
けれども少しでもタブーを恐れたり、お焚き上げの手順に不安があり、拝みが足りない「ウグァンブスク(御願不足)」を恐れるのであれば、「ヒナーシ(日無し)」と呼ばれる日取りを選ぶと、より安心です。
●ヒナーシ(日無し)とは、神様の世界で暦がない「日が無い」日取りを差します。
この「ヒナーシ(日無し)」は一年に一度、旧暦七月七日のタナバタ(七夕)がありますが、この他にも、旧暦と新暦のズレを調整するため、旧暦の一か月が二度訪れるユンヂチ(閏月)もヒナーシ(日無し)です。
・沖縄のタナバタ(七夕)にお仏壇事が多いのはなぜ?新調や交換に良い日取り
ヒナーシ(日無し)の日程
●ユンヂチ(閏月)自体は旧暦一か月のみですが、現代の沖縄ではユンヂチ(閏月)を含めた一年に行います
本来は同じ月が二度繰り返され、二回目の月が暦のないヒナーシ(日無し)のユンヂチ(閏月)とされますが、現代の沖縄ではユンヂチ(閏月)がある旧暦の一年間を、ヒナーシ(日無し)と考えるようになりました。
①タナバタ(七夕)…2022年は8月4日(木)
②ユンヂチ(閏月)…2023年1月22日~2024年2月9日(旧暦1月1日~12月30日)
その昔は、ウグァンブスク(御願不足)がないようにユタさんなどに儀礼を依頼する家も多くありましたが、依頼するには料金が掛かりますし、料金もユタさんの言い値ですので、予算立てができません。
家付きのユタさんがほとんどいなくなった現代では、家族のみで儀礼を行うか、僧侶に読経供養を依頼(約3万円ほど/1回~)する家が多いでしょう。
・「ユンヂチ」とは?2023年1月22日~2024年2月9日が沖縄でお墓事に良い理由
新しいトートーメー
●新しいイフェー(位牌)に魂を移す儀礼を行います
沖縄の儀礼に倣ったトートーメーのお焚き上げは以上ですが、なかには新しいイフェーと交換する家もありますよね。
このような場合は、新しいイフェー(位牌)に魂を入れて初めて、ご先祖様を祀るトートーメーになります。
[1]トートーメーのお焚き上げで残した灰を三つまみ用意
[2]ウコール(香炉)の灰に混ぜる
[3]お線香はジュウニフンウコー(十二本御香)を供える
・日本線香…十二本、もしくは四本
・ヒラウコー(沖縄線香)…タヒラ(二枚)
[4]御願の言葉を掛ける
「新しいトートーメーに移っていただき、ありがとうございます」
[5]新しいトートーメーに名前を書く
このように現代の沖縄では僧侶による読経供養により魂を入れる「開眼供養」が多いですが、沖縄の儀礼でも魂入れは可能です。
・沖縄で古いトートーメーを、新しく買い替えたい!タブーもリセットする買い替え方とは?
最後に
以上が沖縄の儀礼に倣った、自分達で行うトートーメーのお焚き上げの仕方です。
確かにセジ(霊力)が高いとされるユタさんノロさんや、僧侶による読経供養でトートーメーの処分ができたら、安心かもしれません。
けれどもどのような御縁かも分からない位牌がある、そんなに予算を掛ける余裕がない、信頼できる依頼先がない、などの事情で、できれば自分達でお焚き上げをしたい人も多いです。
●もしもお焚き上げに充分なスペースがない場合、名前を削った削りカスだけを焚き上げ、位牌立てなどは塩を振り浄化して捨てても構いません
この場合、位牌立ては半紙など白い紙に包むと良いでしょう。
(新聞紙に包み、その上から半紙に包む家も多いです。)
・沖縄のトートーメーには種類がある?永代脇位牌やアジカイグァンス(預かり位牌)とは?
まとめ
沖縄の儀礼に倣ったトートーメーのお焚き上げ
●お焚き上げをすると…、
・ご先祖様の我が無くなり祖霊となる
・トートーメータブーが無くなる
・スーコー(焼香)が無くなる●お焚き上げの手順
<墓前もしくは家の庭で行う>
・名前の部分をナイフなどで削る
・削った部分を墓前で焼却する
・続けて位牌札、位牌立てを燃やす
・燃え尽きた灰のなかから、指で3回つまむ
・容器などに取り分けておく
・残りの灰を庭や家周辺の土地に埋める●お焚き上げの朝
・ヒヌカンへご報告する●お焚き上げの日取り
(「祟り」が気になる場合)
・タナバタ(七夕)
・ユンヂチ(閏月)●新しく仕立てる場合
・焚いた灰をウコール(香炉)に入れる
※一般的には僧侶による開眼供養●スペースが充分にない場合
・削った名前部分のみをお焚き上げ
・位牌立てなどは塩を振り浄化
・浄化した位牌立てを半紙で包む
(新聞紙で包んでから半紙の家もある)