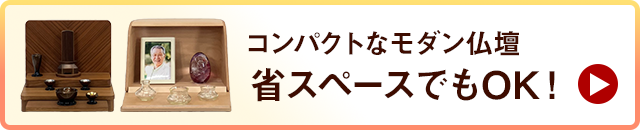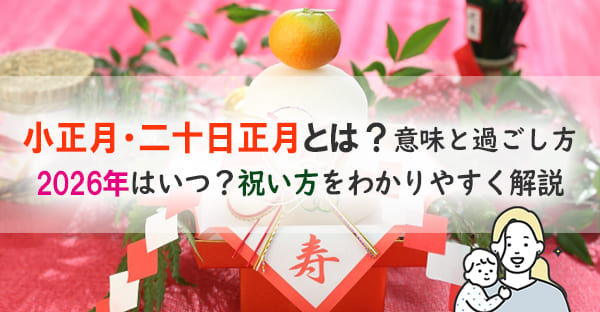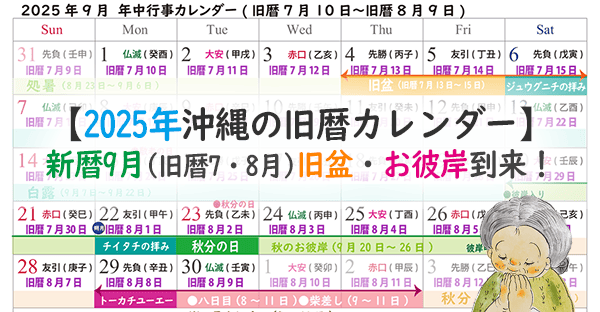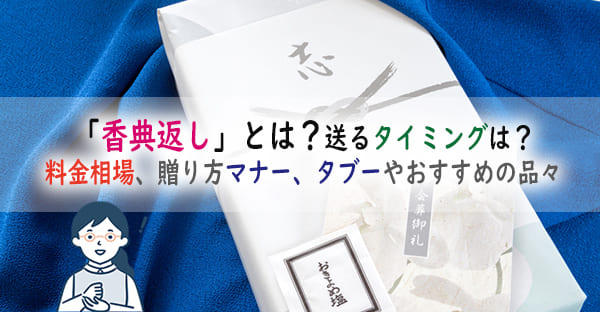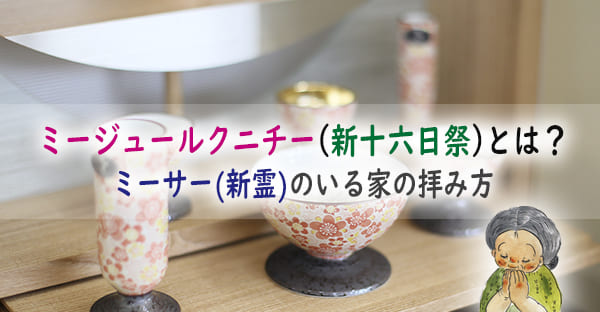年末年始に身内が亡くなった場合、葬儀や火葬の日程に戸惑う人は少なくありません。
2025年度も、火葬場や斎場の休業日、葬儀社の対応日程は自治体や施設によって異なります。
また、すでに年賀状を出していた場合や、忌中で年越しを迎える場合の対応にも注意が必要です。
本記事では、年末年始の葬儀はいつまで・いつからできるのか、公営・民営施設の違いや火葬場の正月休み、全国と沖縄の風習の違いまで詳しく解説。
後半では、年末年始の訃報対応・寒中見舞いの文例・忌中の過ごし方も紹介しています。
【2025年度版】年末年始の葬儀はいつまでできる?
◇一般的に年末年始の葬儀は避けて執り行います
民間の葬儀社の多くは365日24時間営業が一般的ですが、年末年始の葬儀で配慮すべきは参列者のスケジュール、そして火葬場の年末年始休みです。
民間企業が運営する葬儀社や斎場は年末年始の葬儀にも対応する業者がありますが、基本的に公営斎場や火葬場は、年末年始の葬儀には対応せず、休業しています。
①公営火葬場・斎場
◇公営火葬場・斎場の休業日…2025年12月30日~2026年1月3日
自治体によっても異なりますが公営火葬場・斎場での年末年始の休業日は、一般的に正月三が日です。三が日が過ぎると通常営業へ戻る火葬場や斎場が多い傾向です。
ただし近年では火葬場がひっ迫していることも多いため、休業日前の2025年12月28日・12月29日だったからと言って年内に火葬が必ずできるとも限りません。
②民営火葬場・斎場
◇民営火葬場・斎場の休業日…2026年1月1日(元旦)
ただし沖縄では旧暦7月15日に休業する民営火葬場・斎場は少なくありません。ただ旧暦7月15日ですから年末年始にはあたりませんね。2026年の旧暦7月15日は8月27日(木)です。
③葬儀社
現代は365日24時間受け付ける民間の葬儀社が多いです。年末年始に家族が亡くなった場合にも電話受付・対応をしてくれる葬儀社が多いので心強いでしょう。
民営の火葬場や斎場も1月1日元旦以外の日程であれば、年末年始の火葬や葬儀に対応する業者が増えています。
沖縄県の斎場・火葬場は?

沖縄県内の斎場・火葬場での年末年始の休業日は施設によって異なります。下記は一例となるので参考にしてください。
| <年末年始の葬儀はできる?> | |
| ●南斎場 | |
| [住所] | 沖縄県豊見城市字豊見城925 |
| [時間] | 8:30~17:15 |
| [休業日] | ・1月1日 ・旧暦7月15日 ・及び管理上必要と認める日(台風等) |
| [HP] | https://www.okinawa-nanbu.jp/minami/ |
| ●金武町火葬場 | |
| [住所] | 沖縄県国頭郡金武町字金武6166-2 |
| [時間] | 24時間 |
| [休業日] | ・1月1日 ・1月2日 |
※こちらは2025年度の情報です。営業日・営業時間が変更されることもあるので、事前に確認をしてください。
他、沖縄には公営・民営ともに多くの火葬場があります。問い合わせても良いでしょうし、葬儀社に相談してみると良いでしょう。
ただ全国的に公営の火葬場や斎場には年末年始休みがあり、多くは12月30日~1月3日です。火葬場・斎場が使えない場合は、ご遺体安置をして営業日まで待つことになるので、ご注意ください。
【2025年度版】年末年始の葬儀:公営と民営で何が違う?
◇公営と民営では、主に料金が違います。
一般的に公営の火葬場や斎場は使用料が安い傾向にあるため、公営施設で年末年始に火葬や葬儀を行うならば、12月29日まで・1月4日以降の日程になるでしょう。
一方で民営の葬儀費用は公営施設と比べると高くなる傾向ですが、ご遺族の要望に細かく対応してくれるなど、サービスが行き届いています。
①公営施設の費用相場
公営火葬場は自治体が税金などで運営しているため、故人・ご遺族が自治体の管轄する地域に住んでいる場合は割安で利用できる点がメリットです。地域の人々にも広く認知され、宗旨宗派を問わず利用できます。
<公営施設の費用相場>
・火葬場…約8,000円~
・斎場…約6,000円~
また公営の火葬場では、条件によって無料になることもあります。ただし施設使用料のみによる費用相場です。
火葬場が年末年始でお休み、ひっ迫している場合は自宅やご遺体の安置施設で火葬を待つことになります。
②民営施設の費用相場
民営企業や葬儀社・寺院が運営する火葬場や斎場は、県内各地にあるためアクセス環境が良く、施設やサービスが充実している点が特徴的です。施設数が多いため、火葬場の予約が取りやすいでしょう。
<民営施設の費用相場>
・火葬場…約30,000円~
・斎場…約10,000円~
民営施設でも一般的には宗旨宗派を問わず利用できます。斎場では大人数の葬儀にも対応する施設が多く、葬儀社とも提携している火葬場・斎場が多いです。葬儀社選び・斎場選びがワンステップで済みます。
【2025年度版】年末年始の葬儀:全国と沖縄の違い
◇年末年始の葬儀では、ご遺体の安置をどうするかが問題になります。
現代はご遺体安置の環境がより整いやすく長い期間にも対応できますが、それでも一般的には7日間までが目安です。
さらに安置室を借りる場合は1日1日に対して費用もかかり自宅安置では安置環境が充分に整わないため、期間はより短くなるでしょう。この点で全国と沖縄では年末年始の葬儀に対して、風習の違いがあります。
①全国的な風習
全国的には葬儀後の火葬が一般的です。そのため斎場が休みだとご遺体のまま安置して、年始の営業日を待つことになります。
全国的には、火葬場は友引きを休みとする施設が多いですが、沖縄県内では友引に執り行う葬儀も少なくありません。
<全国的な葬儀の風習>
・葬儀後の火葬が多い
・友引を避ける
また全国的な年末年始の葬儀では六曜の確認も必要です。日々の吉凶を占う暦注「六曜」により配慮する全国的な風習では、六曜「友引」は、良い意味でも悪い意味でも「友を引く」暦とされます。
結婚式など慶事で友を引くことは良いのですが、弔事では「生きている人々があの世に引かれる」とされ、年末年始に関係なく葬儀や火葬を、友引に行うことを避けてきました。
全国的には、このような事情から火葬場も友引に休みを取る施設が多いので、注意が必要です。
②沖縄の風習
沖縄では火葬を済ませた後に葬儀を執り行う「骨葬」が一般的です。暦注「友引」でも葬儀を執り行うご遺族は少なくありません。
正月早々に葬儀を執り行うには参列者へ配慮をしなければなりません。この点、沖縄では骨葬が一般的ですから、火葬を先に済ませて落ち着いた頃に葬儀を行う日程調整もできます。
<沖縄の葬儀の風習>
・葬儀前の火葬「骨葬」が多い
・友引の葬儀も多い
年末年始2025年12月31日~2026年1月3日までの4日間は、火葬場や斎場の営業時間はもちろんですが、何より参列者の負担が大きいです。
特に沖縄では一般の故人でも100人以上の参列者が弔問する一般葬も少なくありません。火葬のみを先に済ませて、松の内(松七日)が明けた1月8日以降の葬儀を検討しても良いでしょう。
【2025年度版】年末年始の葬儀形式
◇年末年始の葬儀は、密葬の方法もあります
何らかの事情で年末年始に葬儀を執り行いたいのであれば、故人とごく近しい身内のみで行う葬儀を選ぶのも一案です。
現代では家族のみで執り行う「家族葬」や、火葬場で済ませる「直葬」も注目されていますが、家族葬や直葬では、知人友人が別れを告げる場がありません。
一方「密葬」を選ぶことで、年末年始に身内のみで葬儀を済ませた後に落ち着いた頃に本葬を設けることで、一般の人々が葬儀に参列する機会があります。
①家族葬(直葬含む)
「家族葬」はご遺族や身内のみで執り行う葬儀です。多くても約30人前後までとなるため、年末年始の葬儀でも進めやすいでしょう。
参列者が少ない分だけ金銭的にも安く収まります。一方で家族葬では葬儀後に訃報を知らせる流れが多いため、参列しなかった知人友人に別れの場が設けられていません。
後から故人との別れをしようと、年末年始の葬儀後に自宅への弔問が増える可能性もあります。個別に弔問客への対応を行うことも増えるでしょう。
②密葬
「密葬」は先にご遺族や身内のみで火葬・葬儀を済ませた後、落ち着いた頃に「お別れの会」「偲ぶ会」などの別れの場「本葬」を設ける形式です。
ご遺族は年末年始に葬儀を済ませ、友人知人にも広く別れの場があります。
誰もが故人との別れの場を与えられる反面、葬儀が2回執り行われるので、その分だけ葬儀の準備や労力が増える点はデメリットです。葬儀費用もより掛かります。
③骨葬(沖縄の一般葬)
前述したように「骨葬」は火葬のみを先に済ませる葬儀形式です。火葬のみ先に済ませるため、ご遺体安置の日数が少なく済みます。
安置室の施設によっても異なりますが、ご遺体安置の費用相場は1日あたり約5千円~3万円ほどです。ご臨終当日に通夜、翌日の葬儀が基本ですので、1日目のご遺体安置は無料になる施設が多いでしょう。
自宅でご遺体を安置したとしてもドライアイス代がかかります。費用も安く抑えられ、ご遺族にとって助かる葬儀形式ですが、一般参列者は葬儀でご遺体を前に別れができません。
④全国的な一般葬
全国的な一般層ではご遺体を前に葬儀を執り行います。ご遺体を前に別れができる点がメリットですが、こと年末年始の葬儀となるとご遺体安置の日数が心配です。
ご遺体安置の費用がかかることはもちろん、年末年始で慌ただしいなかで葬儀を執り行わなければなりません。
沖縄では年末年始の葬儀ではなくても、葬儀の日の午前中に火葬を済ませ、ご遺骨の形で祭壇を設ける「骨葬」が一般的です。
【2025年度版】年末年始の葬儀日程は?
2025年12月29日のご逝去であれば、年内の葬儀も可能です。1月1日(元旦)のご逝去では1月2日のお通夜が一般的でしょう。
民間の葬儀社は24時間265日営業の業者が多く、民営の火葬場では1月1日(元旦)のみを休業とする施設が多いため、12月29日のご逝去であれば年内の葬儀もできます。
①年末のご逝去
年末年始の葬儀で理解しておきたいことは、火葬までのご遺体安置時間です。ご遺体の葬送についての法律「墓地、埋火葬に関する法律」では、ご臨終から24時間経つまで火葬が許可されていません。
<2025年12月29日のご逝去:葬儀日程>
・お通夜…12月30日
・火葬、葬儀…12月31日
この法律は蘇生の可能性が考慮された時代の名残りです。そのため12月30日を過ぎてからのご逝去では、年内の火葬・葬儀が難しくなるでしょう。
[参照]
・厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」
②年始のご逝去
民間の葬儀社は24時間365日受け付けてくれるので、1月1日(元旦)のご逝去では2026年1月2日のお通夜日程も可能です。火葬や告別式・葬儀は2026年1月3日が一般的な日程となります。
ただし年末年始の葬儀いずれの日程も、火葬場や斎場など施設の予約状況がひっ迫していない場合です。予約状況がひっ迫しているならば、直近の空きを待つことになります。
年内の予約がいっぱいであれば、2026年12月29日のご逝去であっても翌年に持ち越される可能性はあるでしょう。
③年末年始の葬儀、火葬場はひっ迫している?
◇全国的に年末年始の火葬場は混雑する傾向です
火葬や葬儀スケジュールは火葬場や斎場の予約がポイントですが、実際に年末年始の火葬場や葬儀会場は、混雑していることが多いでしょう。
コロナ禍でも問題になりましたが、火葬の順番を待つ可能性もあります。火葬さえ終われば、落ち着いた頃に本葬やお別れ会に向けて、ゆっくり準備を進めることも可能です。
けれども火葬場がひっ迫していた場合は、ご遺体を安置する必要があります。ご遺体の腐敗を防いで美しく安置するためには、適切な環境や処置が必要です。
【2025年度版】年末年始の葬儀までご遺体安置
◇年末年始に葬儀までご遺体を長く安置する場合、処置が必要です
ご遺体を長く安置するには、ご遺体を美しく保つ温度に保たなければなりません。
数日であればドライアイスや室温への配慮で、ご遺体を美しく保つこともできるでしょう。
けれども近年では年末年始に火葬場がひっ迫する年もありました。
約7日を超えるご遺体の安置であれば、防腐処置や消毒の処置を施す「エンバーミング」も検討しなければなりません。
①ご遺体安置の環境
ご遺体の安置には涼しい環境が不可欠です。自宅でご遺体安置を試みるのであれば、室温18℃以下になるよう常に冷房を効かせて過ごします。
ドライアイスの準備も必要になるでしょう。ドライアイスはスーパーやコンビニで調達できるものではありません。葬儀社に相談して準備をしてもらいましょう。ベッドや体に充分なドライアイスを挟みます。
自宅安置ではこの状態で最長約3日~5日ほど保ちます。ただし状況にもよるでしょう。安置室でご遺体安置をした場合、最長約7日ほどが目安です。
②エンバーミング
「エンバーミング」とは、ご遺体の腐敗を防いで生前の姿に近づける科学的処置です。ご遺族や葬儀社スタッフではなく、エンバーミングの専門家「エンバーマー」に処置を行ってもらいます。
エンバーミングはご遺体をより長く衛生的に保つことを目的としていますが、ご遺体の損傷なども生前に近い姿へ戻す場合もあるでしょう。
<エンバーミングの内容>
●約10日~30日ほど保つ
・ご遺体の消毒
・内臓の残存物を取り除く
・血液などの体液の排出
・ご遺体の防腐処置
・化粧を施す
海外では認知されていますが日本では火葬を行うため、あまり浸透していません。エンバーミングは費用が掛かるうえ、家族は立ち会うことができません。ご遺体を預かり、数日(2日ほど)掛かることもあります。
【2025年度版】年末年始の葬儀まで、ご遺体安置の費用相場
◇ご遺体を安置する場合、ドライアイスや安置室使用料が追加されます
全国的な葬儀のように、ご遺体を葬儀まで安置することを優先する家族は少ないですが、年末年始の葬儀でご遺体を前にお別れを告げる場合、安置日数によって葬儀費用も大きく変わります。
①ドライアイス
ドライアイスは交換が必要になるので、1日当たりで算出します。目安として約8千円~となるでしょう。年末年始の葬儀までに7日間ご遺体安置したとして、ドライアイスは約5万6千円の計算です。
自宅で安置するとしてもドライアイスは必要です。またご遺体を安置した部屋は、常に18℃以下に保たねばなりません。年末年始は真冬ですが、室内だと温かな部屋も多くあるでしょう。
火葬場の予約状況に空きがある場合、冷房の電気料金やドライアイス費用を考えると、年末に骨葬や密葬を済ませる選択が多い傾向です。
②安置室使用料
年末年始の葬儀まで日数がある場合、一般的に葬儀社が紹介する安置施設を利用します。安置施設を探すこともできますが、病院の霊安室は利用時間が限られているので、時間内に探さなければなりません。
安置施設のグレードや運営母体により費用相場は異なりますが、相場として1日あたり約1万円~3万円が目安です。
平均的には約1万円ほどになるでしょう。年末年始の葬儀まで7日間の遺体安置をしたとして約7万円の計算です。
③エンバーミング
長期間のご遺体安置が求められる場合、エンバーミングを検討するご遺族もいます。エンバーミングの費用相場は約15万円~25万円ほどです。またエンバーミングを依頼する先によっては、ご遺体の搬送費(往復)などもかかります。
この他、ご遺体安置や搬送に関する費用相場については、下記コラムも併せてご参照ください。
[ご遺体の搬送、安置費用など]
・沖縄で葬儀までにかかる費用は?家族が亡くなったら葬儀に費用がかかる10項目と体験談
【2025年度版】年末年始の葬儀:手続きや支払いは?
年末年始の火葬や葬儀では、現金を早めに準備すると安心です。
年末年始の火葬や葬儀は、火葬場や斎場の予約だけではなく、行政や金融機関窓口の受付時間も影響しいます。
火葬場では使用料が現金支払いになる施設も多く、クレジットカードなどの使用ができないケースもあるなか、年末年始のATMは通常利用時間よりも短縮する金融機関も多いためです。
①行政手続き
家族が亡くなると病院から死亡届を受け取り、役所窓口に提出しなければなりません。死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。この火葬許可証がなければ火葬はできないためです。
役所窓口の年末年始の休業日は2025年12月29日~1月3日なので、年末年始に死亡届を提出する場合には時間外窓口を利用しましょう。
②年末年始の葬儀費用
年末年始には葬儀費用の引き出しも気になるところですよね。現在はコンビニATMなど、年末年始も利用できるサービスがあるでしょう。
ただ積立貯金からの引き出しなど窓口での受付を必要とする時は、12月31日~1月3日までお休みの金融機関が多いため、確認をしてください。
また年末年始は日曜祝日扱いになっているATMが多いです。準備できる時に現金を用意して年末年始の葬儀に臨みましょう。
【2025年度版】年末年始の葬儀で現金が必要なシーン
参列者からいただいた香典で清算することも多い葬儀費用は、年末年始に執り行ったとしても、葬儀から7日間後ほどを目安に後払いも可能な業者が多いです。
けれども年末年始の葬儀にあたり、現金での支払いが求められる場面もあります。現金の引き出しが難しいかどうかも踏まえた日程調整も重要です。
①お布施
読経供養のお礼として僧侶へ包むお布施も基本的に現金で包みます。しばしば葬儀社による葬儀費用にお布施まで含まれるプランもありますが、一般的には葬儀費用とは別です。
<お布施を包む費用目安>
・読経料…約3万円/1回
・御膳料…約1万円ほど~
・御車代…約5千円ほど~
年末年始でも葬儀の前や後、僧侶の控室で感謝の言葉とともにお渡ししましょう。お布施の包み方にもマナーがあるので、下記コラムも併せてご参照ください。
[お布施の包み方マナー]
・沖縄の法要でお布施を包む。僧侶へ渡す時の準備やマナーとは
②戒名料
全国的には家族が亡くなると、僧侶に戒名を付けていただきます。戒名(かいみょう)は本来、お釈迦様の弟子になった証としていただく名前です。
けれども故人に対して名付けることが多いでしょう。戒名にはランクがあるので約3万円~50万円以上と費用幅があります。
<戒名料の費用目安>
・戒名料…約3万円~50万円
ただ全国的には檀家制度があり、寺院墓地では戒名を付けないとお墓に埋葬できない事情もありました。
一方で檀家制度のない沖縄では、位牌に生きてる時の名前「俗名(ぞくみょう)」を記載してきました。このような歴史から、そもそも戒名を付けない沖縄の家も多いでしょう。
戒名はあくまでもお釈迦様の弟子としての名前なので、無宗教であれば必ずしも付ける必要はありません。
[戒名について]
・沖縄で法要に包むお布施の金額目安。沖縄で戒名まで依頼する?
③世話役へのお礼
年末年始の葬儀で親戚や友人知人へお手伝いを依頼した場合、謝礼としてポチ袋に現金を包んでお渡しします。通夜や葬儀での受付係・駐車場係・世話役などです。
一般的にはポチ袋や厚手の白封筒に「寸志」「志」「御礼」などの表書きで、1人あたり約3千円~5千円を目安に包みます。
「世話役」とはお手伝いをまとめる立場です。世話役を依頼した相手には、約1万円~3万円を目安に多めに包みましょう。
④火葬場の利用料
年末年始の火葬場料金は現金支払いが多いです。公営の火葬場で費用目安は約6千円(公営)ほど、火葬場によっても費用は異なるでしょう。
火葬場料金の支払いは後払いができません。火葬場で対応可能であれば、クレジットカードや葬儀ローンでの決済も良いでしょう。年末年始の葬儀では、事前に確認をすると安心です。
【2025年度版】年末年始の葬儀の流れ
◇年末年始であっても、基本的な葬儀の流れは変わりません
基本的に年末年始の葬儀も、通常の流れと変わりはありません。
病院で故人を看取ったら、病院の霊安室をお借りできる時間内で葬儀社を探し、2~3社を比較検討して連絡を取ります。
病院では少ない霊安室で、亡くなる人も多い場所なので、霊安室を利用できる時間は長くて24時間以内、短いと3時間以内で霊安室を出なければならないこともあります。
①葬儀社へ連絡をする
ご家族が亡くなって最初にすることは葬儀社選びです。病院で亡くなると院内の霊安室へとご遺体は運ばれますが、霊安室を利用できる時間はごく限られています。
余裕があれば24時間の利用もあり得ますが、ひっ迫している場合は3時間ほどの間にご遺体を搬送しなければならないケースもあるほどです。
まず葬儀社に連絡をして、ご遺体の搬送依頼を行いましょう。取り合えずご遺体の搬送だけを依頼することもできますが、同じ葬儀社でご遺体安置まで依頼できれば助かります。
②訃報を知らせる
ご家族が亡くなったら、葬儀社探しと並行して近親者への連絡を行います。ご家族にまず連絡をして、手伝ってもらうと心強いです。
年末年始の葬儀では密葬・家族葬など、すぐに知らせない選択もあります。葬儀を済ませた後で訃報ハガキなどで事後報告をする方法です。
檀家制度が根付いていない沖縄では少ないですが菩提寺があれば、まず菩提寺に連絡をしましょう。通夜に行う枕経、通夜や葬儀での読経供養は、菩提寺のご住職に依頼するためです。
③ご遺体の安置 ・自宅
一般的には葬儀社の安置室を利用します。自宅安置でも葬儀社に相談をして、ドライアイスなどを準備してもらいましょう。
自宅安置ならば、自宅に迎える前にご遺体を安置する布団、シーツなども確認します。葬儀社が準備してくれることが多いですが、そうでない場合は準備が必要です。
④葬儀社との打ち合わせ
ご遺体の搬送が終わったら葬儀社との打ち合わせです。棺桶から祭壇までそれぞれにグレードがあり葬儀費用は幅が広いので、最初に予算を決めてから打ち合わせに望みます。
また年末年始の葬儀で気になる事柄は、火葬場の予約状況ですよね。この状況によって安置費用がどれほどになるかが分かります。
さらに斎場の予約状況の確認をして、僧侶の手配をしながら日程調整を行います。喪主が高齢な場合などは施主を立てても良いです。葬儀社との打ち合わせは複数で望んでも、問題はありません。
[葬儀社との打ち合わせ]
・葬儀社の打ち合わせで確認しておくことは?連絡するのはいつ?服装・打ち合わせ時間は?
⑤喪服の準備
年末年始に身内のみで葬儀を執り行う場合、喪服も早く確認しておきます。喪服がない場合、年末年始は商業施設が休業していることも少なくありません。
葬儀は突然訪れる為、日ごろから喪服一式を揃えて置く対策がベストですが、2025年12月28日・29日頃の訃報で喪服がない場合、空いている時期に早急に準備すべきです。
喪服が準備できない場合は、喪服レンタルも検討します。貸衣装店にも喪服はありますが年末年始の葬儀で空いていない場合は、葬儀場でも喪服レンタルサービスを提供していることがあります。
[葬儀の服装マナー]
・葬儀や通夜に参列する服装・喪服マナーとは?女性と男性・子どもや夏場のジャケットは?
⑤行政手続き
故人を看取ったお医者様から「死亡診断書」を受け取ります。「死亡届」は、この死亡診断書と一体になっているので必要事項を記入しましょう。
死亡届の提出は亡くなってから7日以内ですが、死亡届を提出すると役所から発行される「火葬許可証」がなければ火葬ができないため、一般的には数日以内に提出します。
死亡届の提出は葬儀社スタッフに委託することも可能です。忙しい時には相談してみると良いでしょう。
⑤僧侶の手配
お通夜や葬儀にあたり僧侶の手配も併せて行います。菩提寺があればご住職に依頼しますが、菩提寺がない家では葬儀社に相談しても良いでしょう。
この他、現代ではインターネットによる僧侶派遣サイトもあります。葬儀派遣費用が約3万円~と安い価格帯が期待できますが、信頼面で気になる場合は葬儀社からの紹介が安心です。
【2025年度】年末年始の葬儀での注意点
◇年末年始にご遺体を安置する場合、面会できない施設もあります
年末年始にご遺体を安置する場合、特に公営だと年末年始の休業中はご遺族であっても面会できない施設も多いです。
できるだけ最後の時間を共に過ごしたい場合には、エンバーミングなどご遺体の処置をしっかりと取りながら、自宅安置を検討すると良いでしょう。
下記に年末年始に葬儀をする際の注意点をまとめます。
①安置室の環境を確認
◇安置室の利用が数日になる場合は、1日あたりの安置室利用料を確認しましょう。
火葬場がひっ迫している状況下では、ご遺体安置が丁寧になされていない可能性もあります。契約時に安置環境を確認できると安心ですね。
安置室を利用している間は面会ができる施設が一般的です。利用期間の面会時間も確認します。
②施設の予約状況
◇年末年始の葬儀は混雑することもあります。
特にコロナ到来以降、2025年においても火葬場がひっ迫しやすい状況が続いています。まずは火葬場と斎場の予約状況を確認して、今後の通夜・葬儀日程を調整しましょう。
ご遺体の安置室も混雑していることがあります。葬儀社が提供する安置室ばかりではありませんが、自宅での安置になる可能性も視野に入れながら検討するケースがあることも否めません。
③現金を準備
年末年始の葬儀ではお布施や寸志など必要な現金を把握して、早い段階で現金を準備しておきます。大きなお金を崩すにも手間暇がかかるため、千円・5千円・1万円単位で揃えておくと安心です。
ただし通夜や葬儀で包む現金に小銭は必要ありません。最も小さな単位で千円です。ポチ袋や厚手の白封筒も併せて多めに準備をしておくと、人数にズレが生じても対応できます。
④日程調整
年末年始の通夜や葬儀は日程調整が最も難しいところです。僧侶の手配と葬儀の司会者、仕出し料理などの準備も進めなければなりません。
葬儀社が年末年始の葬儀に対応してくれるならば、ある程度はお任せしてしまうと、ワンステップになるのでご遺族の負担が少なくて済みます。
⑤訃報の範囲
会社や学校がお休みになる、お祝いムードの年末年始のなかで執り行う葬儀です。知らせる相手への配慮としても、年末年始に訃報を知らせるべき人をご遺族で決めておきましょう。
密葬・家族葬などごく身内のみで執り行う葬儀であれば、ほとんどの人に対して訃報は事後報告となるでしょう。
[葬儀までに行うこと]
・葬儀・お葬式とは?いつ行う?沖縄でお通夜は?家族が亡くなって葬儀までに行うこととは
⑥商業施設の営業時間
商業施設が閉まることの多い年末年始の葬儀では、喪服の準備やお布施や寸志を入れる封筒の準備はすぐにでも済ませておきます。
年末年始の火葬や葬儀で知っておくと良いことは「故人の逝去後、24時間経ってからでなければ火葬ができない」と言う点です。
そのため2025年12月31日に家族が亡くなった場合、この法律から最短でも翌2026年1月1日(元旦)の火葬や葬儀となる計算ですが、2026年1月1日(元旦)は、民営も含めてほとんどの施設が休業日となります。
年末年始に葬儀案内や訃報を出しにくい
◇年末年始の訃報は身内のみとし、落ち着いてから訃報を出しても良いでしょう
年末年始の葬儀は見受けますが、いずれも家族葬や密葬、直葬などで、故人と近しい身内のみでの葬儀がほとんどです。
「年末年始の訃報は伝えにくい」との声がありますが、必要な人のみに訃報を届け、残る人々は全て済ませてから、後日訃報を送っても問題はありません。
①事前に知らせるが身内のみ
「年末年始ですので 身内のみで葬儀を執り行いたいと思います」などの文言で、葬儀前に訃報を知らせつつ、通夜や葬儀への参加を辞退する方法もあります。
併せてお返しが負担になるとして、「なお御香典 御供花等につきましてもご辞退申し上げます」通夜や葬儀会場への供花・供物を辞退するご遺族も増えました。
年末年始の葬儀を済ませた後ご自宅に弔問客が頻繁に訪れないよう、弔問辞退の一文を添えることも可能です。
②後日知らせる
「誠に勝手ではございますが 年末年始により近親者のみで葬儀を執り行いました」などの文言で、年末年始の通夜や葬儀の後に事後報告を行うケースもあります。
訃報を後日知った相手は、自宅への弔問や香典・供花の郵送を検討するでしょう。
余裕があれば受け付けた後、四十九日法要後に香典返しをお送りすれば良いのですが、自宅の弔問が途絶えずに家族が対応に疲れてしまうケースもあります。
故人とお別れをしたい人が大勢いると予想される場合には密葬とし、年末年始が過ぎて落ち着いてから本葬を執り行うと良いでしょう。
【2025年度版】忌中の年越しで法要はどうなる?
◇沖縄では繰り上げ法要により、年内に四十九日法要まで行う家族が多いです。
神道に近い祖霊信仰が根付く沖縄では、特に忌中の年越しを忌む傾向にあります。そこで年内に葬儀を執り行う場合、その場で四十九日法要まで、「繰り上げ法要」を行う選択が多いです。
①繰り上げ法要とは
「繰り上げ法要」とは、本来別の日に行う法要を葬儀の日などに一緒に執り行うことです。一般的には僧侶による読経供養が行われます。
●繰り上げ法要は、例えば「繰り上げ初七日」「繰り上げナンカスーコー(週忌法要)」「繰り上げ四十九日法要」などです。繰り上げた法要の分だけ読経供養を行います。
繰り上げ四十九日法要まで済ませることで、忌中の法要を全て終えることにはなりますが、家族を亡くした身内は忌中として年末年始のお祝いを控えて、「死の穢れ」を広げぬよう身を慎み過ごします。
【2025年度版】年末年始の葬儀|年賀状を出していたら?
◇配達前であれば「郵便物の取り戻し請求」ができます
年末に身内が亡くなり、すでに年賀状を出していた場合、できるだけ早く郵便局へ行き「郵便物の取り戻し請求」を行うと良いでしょう。
投函地域の郵便局で年賀状が止まっていれば、無料で年賀状の取り戻しができます。年賀状代金は返金されませんが、手数料5円/1枚で他の官製ハガキや切手などと変換はできるでしょう。
①2025年12月上旬の訃報
2025年12月上旬にご家族が亡くなったら、年賀状は出さずに急ぎ喪中ハガキを送りましょう。郵便局の年賀状受け付けは毎年12月15日~です。
2025年12月15日に間に合えば年賀状は控え、少しでも早く喪中ハガキを出します。受け取った相手も年賀状が届かぬよう配慮してくれるでしょう。
②2025年12月中旬の場合
喪中ハガキの到着目安が2025年12月15日を過ぎてしまいそうな場合、喪中ハガキは出さなくても良いでしょう。けれども年賀状の郵送も控えます。
年賀状をいただいたら、年明けの松の内が明けた翌日2026年1月8日~2月3日頃を目安に、毎年「寒中御見舞い」を送って、訃報と年賀状欠礼の言葉を添えます。
毎年2月3日頃は立春です。寒中御見舞いは寒い時期のご挨拶なので、年明け~立春までが送るタイミングです。
③年賀状を出してしまった
年末年始、すでに年賀状を出してしまってからご家族の訃報に触れた場合、投函地の集配局にまだあれば無料で引き取りができます。間に合いそうなら急いで回収をしましょう。
●投函地を出発している年賀状は、配達郵便局へ「年賀状の取り戻し請求」を行うことができます。
ただし取り戻し請求には手数料が1枚につき420円かかるでしょう。それ以外の郵便局に請求した時には、1枚あたり手数料580円です。
この「年賀状の取り戻し請求」については知らない人も多いです。
年賀状を出してしまった後に身内が亡くなったケースでは、12月中旬の場合と同じく、年明けの「寒中見舞い」や訃報ハガキで知らせる人もいるでしょう。
[参考]
・郵便局「Q申し込みをした後にキャンセルすることはできますか?」
【2025年度版】年末年始の葬儀:寒中見舞いの文例
◇年末年始の訃報を、年明けに知らせる際はお詫びの言葉を添えます。
年末年始の訃報を年明けに寒中見舞いで知らせる場合、訃報が遅れたことへのお詫びの一文を添えると良いでしょう。下記がその一例です。
①寒中見舞いの文例
「寒中御見舞い申し上げます。
ご丁寧なお年賀のご挨拶をいただきありがとうございました。
皆さまご健勝でお過ごしとのこと、お慶び申し上げます。
旧年〇月に母○○が○○歳で他界いたしましたため、
新年のご挨拶を遠慮させていただきました。
本来であれば旧年中にご挨拶を申し上げないといけないところ、
遅くなり大変失礼をいたしました。
本年も皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。
令和8年1月
○○ ○○(氏名)」
②寒中見舞いの注意点
寒中見舞いとは言え訃報ですので、お祝い事である年賀ハガキは使用せず、私製ハガキもしくは官製ハガキを使用しましょう。
また寒中見舞いを送る時期は、次の立春の前日までです。
毎年少しずつ暦は異なりますが、2025年は2月5日が立春なので前日は2月4日。1月中に寒中見舞いを出すことをおすすめします。
まとめ:年末年始の葬儀は、火葬場の予約を確認します
年末年始は、火葬場や斎場の休業日、参列者の予定などにより葬儀日程の調整が難しくなります。
特に公営施設は12月30日~1月3日まで休業となることが多いため、まずは火葬場・斎場の予約状況を早めに確認しましょう。
2025年~2026年度も、年末年始の葬儀では家族葬・密葬・骨葬など、身内中心の形式を選ぶ人が増えています。
また、法律上「亡くなってから24時間は火葬ができない」点も忘れずに、余裕をもった日程調整を行うことが大切です。
急な訃報の際も、落ち着いて葬儀社へ相談し、年越しを穏やかに迎える準備を整えましょう。

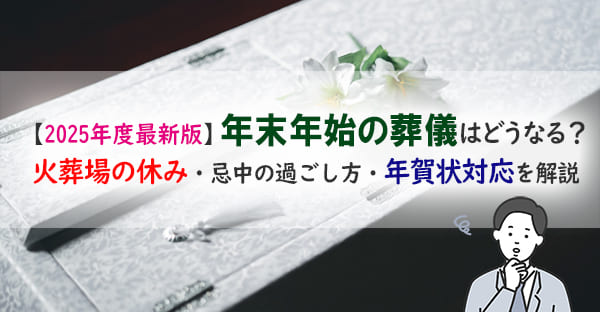

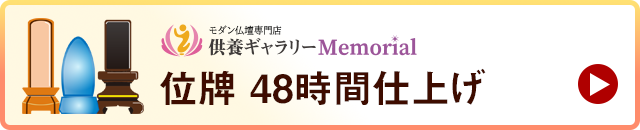
![[1]ペット火葬とは?](https://www.ryuukyuu.co.jp/memorial2019/wp-content/uploads/2022/04/pixta_63382971_S.jpg)