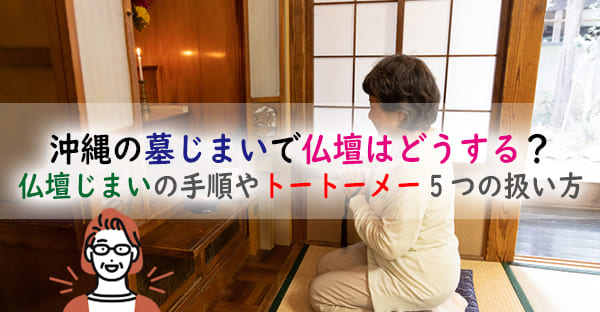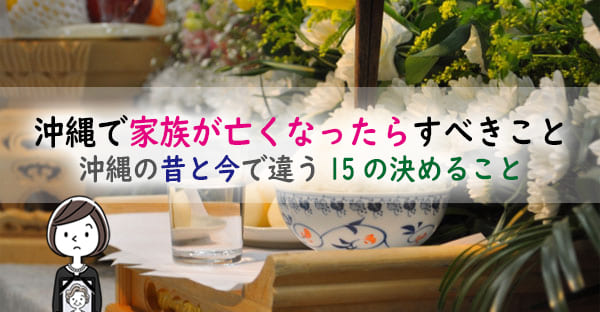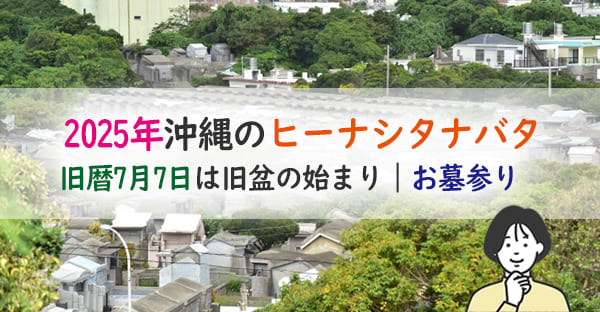・墓じまい、仏壇じまいとは?
・墓じまいをしたら、仏壇はどうする?
・仏壇じまいで、トートーメーはどうする?
墓じまい、仏壇じまいとは、それぞれお墓や仏壇を閉じることです。
お墓は墓石を撤去し更地とし、仏壇は処分します。
この時、位牌は魂の宿る礼拝の対象なので、遺骨と同じく供養が必要です。
特に沖縄では先祖代々位牌「トートーメー」の扱いには慎重な人が多いでしょう。
本記事を読むことで、墓じまいや仏壇じまいとはなにか?墓じまいをした後、仏壇をどうするかや、仏壇に祀るトートーメーをどのように対処するか、5つの対策が分かります。
沖縄の墓じまい、仏壇じまいとは?

◇墓じまい、仏壇じまいとは、現存のお墓や仏壇を閉じることです
「墓じまい」「仏壇じまい」の言葉が広がりつつありますが、「墓じまい」とは、今までのお墓を完全に撤去・解体し区画の使用権を返すことで、特に終活の広がりとともに、全国的にも知られるようになりました。
とは言っても、もちろん埋葬された遺骨を取り出し勝手に移動することはできませんので、注意をしてください。
また沖縄は先祖代々位牌「トートーメー」のタブーによる継承問題に悩む家が多いです。
そのため墓じまい以上に「仏壇じまい」が注目されていますが、こちらは行政手続きは必要ありません。
①沖縄で仏壇じまいが進まない理由は?
◇沖縄の先祖代々位牌「トートーメー」にはタブーがあるからです
お墓の継承問題や墓じまいは、全国的な課題でもありますが、先祖代々位牌「トートーメー」の継承問題は、沖縄ならではの課題とも言えます。
全国的にも先祖代々を祀る「繰り出し位牌」はありますが、墓じまいの後に菩提寺など寺院に相談をして、ご位牌のお焚き上げにより仏壇をしまう家は多いです。
けれども沖縄では菩提寺を持つ家は少なく、お墓も個人名義の個人墓地に建つものが、今も残っています。
けれども沖縄には独自の祖霊信仰が根付き、沖縄の人々にとって先祖代々位牌「トートーメー」は、家の一族を守護する「カミ(神)」とされてきました。
全国的には仏壇の中心にご本尊が祀られる一方、沖縄で仏壇の中心はご位牌です。
それだけ沖縄ではご位牌やトートーメーをしまうことに、抵抗感を覚える人々も少なくありません。
②沖縄は墓じまいの仕方は?
◇役所で「改葬許可申請」を行います
「墓じまい」は民間から生まれた造語で、既存のお墓からご遺骨を取り出して他の墓所へ移動する行為は、行政手続き上「改葬(かいそう)」です。
墓じまいでは、お墓に納骨されているご遺骨を取り出して、墓石を撤去した後、墓地を整地する流れですので、お墓からご遺骨を取り出すにあたり改葬手続きが必要になります。
改葬手続きや、沖縄で行う墓じまいの手順については、後ほど詳しく解説していますので、どうぞ最後までお読みください。
墓じまいの後、仏壇はどうする?

◇墓じまい後、必ず仏壇じまいをする必要はありません
「墓じまいをすると仏壇じまいをしなければならないの?」などの質問もありますが、基本的にお墓と仏壇は別の供養方法ですので、墓じまいをしたからと言って、必ず仏壇じまいをする訳ではありません。
・仏壇はそのまま残す
・手元供養にする
・仏壇をコンパクトにする
・仏壇じまいをする
…などの方法があります。
「手元供養」とは、遺骨を自宅で祀り日々供養する方法です。
墓じまいで取り出した遺骨をメンテナンスした後、自宅に祀って供養します。
もともとはごく身内の遺骨を手元供養にしましたが、最近ではお墓の管理や維持を軽減するため、自宅の仏壇に遺骨を収蔵する「自宅墓」も増えました。
ただ近年では沖縄でも、若い世代はもちろん、トートーメーの継承問題に悩む高齢者を中心に、墓じまいと仏壇じまいをセットで進めるケースが急増しています。
①沖縄のトートーメー継承問題
◇沖縄ではお墓以上に、トートーメー継承が深刻化しています
檀家制度のない祖霊信仰が根付く沖縄で、先祖代々位牌「トートーメー」は、家を守護するカミ(神)そのものであることはお伝えしました。
そのため沖縄では今、お墓以上にトートーメーの継承問題に悩む高齢者が増えています。
さらに「カミ(神)」の存在であるトートーメーは、「むやみに扱うと祟りがある」との伝承を恐れる人が今もいます。
ただ、そんな沖縄のトートーメーも、ご遺骨と同様に、きちんと供養して対処すれば、仏壇じまいができるでしょう。
それでは下記より、墓じまい後の仏壇じまいにおいて、トートーメー4つの供養方法をご紹介します。
・沖縄のトートーメーとは?タブーで増える沖縄のトートーメー継承問題を解決する方法とは
沖縄で墓じまいの後、仏壇じまいの仕方

◇仏壇じまいの前に「閉眼供養」を行います
「閉眼供養」は「魂抜き」「お性根抜き」「精霊抜き」などとも呼ばれ、お墓や位牌など、故人や神仏の魂が宿っているとされる仏具・神具などから、魂を抜いてただの「物」にする儀式です。
閉眼供養は仏教に倣った儀式なので、僧侶に読経供養をしていただき、参加者はお焼香をもって供養します。
魂を込める「開眼供養」と「閉眼供養」は対の儀式となるため、新しく仕立てた時に開眼供養を施している仏具・神具は、処分前に閉眼供養が必要です。
①僧侶を手配する
◇僧侶を手配し、親族へご案内をします
現代の沖縄で仏壇の閉眼供養は仏式が一般的です。
そのため親族が参列しやすようにスケジュール調整をしたら、僧侶を手配します。
近隣の寺院のご住職に依頼する他、石材業者、仏壇を引き取ってもらう仏壇仏具店などに相談をすると、僧侶を紹介してくれるでしょう。
また近年では、インターネットによる僧侶派遣も見受けます。
②仏壇の引き取りを手配する
◇仏壇仏具店などへ、仏壇の引き取りを依頼します
仏壇の閉眼供養を終えた後、ご位牌やトートーメーは何らかの形で供養をしますが、仏壇はご位牌を祀るための「箱」ですので、粗大ゴミとして捨てることは可能です。
ただ特に沖縄仏壇は大きく、家族のみでは移動も大変なうえ、粗大ゴミとして出すにも分解など手間暇が大変でしょう。
一般的に仏壇を処分する時は、仏壇仏具店などに相談をして引き取ってもらいます。
仏壇引き取りの費用目安は約2万円~ですが、新しい仏壇を購入した場合は、無料で引き取ってくれる仏壇仏具店もあるので、確認をしてみてはいかがでしょうか。
③参列者へご案内をする
◇家族・親族へ閉眼供養のご案内をします
閉眼供養の日程が決まったら、親族へ閉眼供養のスケジュールをご案内しましょう。
特に、毎年旧盆やシーミー(清明祭)に集まる親族、移住していてご無沙汰になっていても、旧盆にお中元を毎年送ってくれる親族へは、ご案内をかけます。
電話やSNSでご案内するのも良いですが、法要のご案内ハガキを郵送するのが一般的です。
閉眼法要の服装は一般的に、畏まったお出かけ着ほどの「平服」ですので、「当日は平服で起こしください」のひと言を添えると丁寧でしょう。
④供花・供物を供える
◇閉眼法要のお供え物「五供」を準備します
閉眼法要のお供え物に決まり事はありませんが、仏壇へ供える供物の基本「五供(ごく・ごくう)」を揃えると良いでしょう。
五供とは、お水・お花・食べ物・お線香・ロウソクです。
仏前に供える供花や供物は、約2千円~5千円ほどでおさまるでしょう。
特にお線香は閉眼供養で集まった人々が供えるため、多めに準備しておきます。
⑤家と仏壇の掃除をする
◇僧侶・参列者を迎えるため、家や仏壇の掃除をします
閉眼供養は仏前法要ですので、仏間に僧侶をお呼びし、集まった親族でお線香を上げるため、お客様を迎え入れる準備が必要です。
また閉眼法要の後、仏壇は引き取られますが、だからこそ、仏壇掃除も丁寧に行うと良いでしょう。
仏壇は上から下へ順番に、埃ハタキで埃を払った後、乾いた布で乾拭きをします。
「これからお掃除させていただきます」とひと言伝えても、より丁寧でしょう。
⑥会食を設けるか決める
◇閉眼供養の後、会食の場を設ける場合、手配をします
仏壇の閉眼供養の後、参列いただいたお礼として会食の場を設ける施主も多いです。
会食の場を設けるならば、会場や料理を手配しなければなりません。
ただ沖縄では、閉眼供養の後に会食の場を設ける選択は、それほど多くはないでしょう。
また約500円~2千円ほどの仕出し弁当を人数分用意して、当日のお帰り時に配る、などの方法もあります。
⑦お布施を準備する
◇僧侶へ包むお金「お布施」を準備します
閉眼供養では僧侶へ読経供養を依頼するため、そのお礼としてお布施の準備も大切です。
お布施は1回の読経供養に付き、約3万円~5万円が相場ですが、お布施は本来「徳行」と呼ばれる仏教の道なので、金額は決まっていません。
また僧侶に自宅まで出張いただいているので、「御車代」の表書きで、タクシー代金を目安に約3千円~5千円ほどを、別封筒に包みます。
この他、閉眼供養の後に会食の場を設けたものの、僧侶が欠席される際には「御膳代」として、食事代を目安に約3千円~1万円を目安に、こちらも別封筒で準備しましょう。
・沖縄の法要でお布施を包む。僧侶へ渡す時の準備やマナーとは
⑧閉眼供養を行う
◇閉眼供養当日は、僧侶の指示に従います
当日は朝から僧侶をお迎えし、参列者をお迎えした後に閉眼供養が始まるでしょう。
葬儀や四十九日法要では喪主(施主)挨拶がありますが、閉眼供養では、それほど参列者が多いものでない限りは、施主挨拶のない席が多い傾向です。
僧侶が読経供養を始めたら僧侶の指示に従ったタイミングで、施主から順番にお線香を上げて終了です。
墓じまい後、仏壇の閉眼供養に多い質問

墓じまい後、仏壇じまいも併せて進める時には、お墓と同様に仏壇も閉眼供養を行い魂を抜いた後、仏壇を処分します。
ただ「仏壇じまいをする」と言っても、仏壇や位牌、トートーメーの一切をしまう家もあれば、トートーメーから個別の位牌に変える、位牌のみを祀る、コンパクトな仏壇へ交換するなど、その目的はさまざまです。
墓じまい後、仏壇じまいの多様な選択肢に反応して、さまざまな疑問や相談、質問が増えたため、下記ではそのいくつかを解説します。
①閉眼供養は自宅で行わなければダメ?
◇基本は自宅ですが、位牌のみの閉眼供養のケースもあります
一般的に墓じまいの後、仏壇の閉眼供養は仏前で執り行うため、自宅で執り行う流れが一般的です。
特に沖縄では「トートーメーは家から出してはならない」との伝承が残る家もあるため、「閉眼供養が終わり魂を抜くまでは、トートーメーを移動できない」と考える人もいます。
ただ閉眼供養の対象は位牌やトートーメーです。
仏壇はもともと位牌やトートーメーを祀る「箱」なので、タブーさえ気にならなければ、トートーメーや位牌のみを取り出して、別の場所で閉眼供養を行うこともできます。
②閉眼供養の服装は?
◇畏まったお出かけ着「平服」です
「平服(へいふく)」とは普段着を指しますが、墓じまいや仏壇じまいで使われる「平服」は、落ち着いた色合いでまとめた畏まったお出かけ着を着用します。
ただ施主においては、準喪服を着用する人もいるでしょう。
参加者は濃紺やダークグレー、深緑などの落ち着いた色の無地でまとめたお出かけ着程度の平服で参列し、香典は必要ありません。
法要などの弔事における「平服」について、どのような服装が適切か、詳しくは下記コラムも併せてご参照ください。
・【イラスト解説】墓じまいの服装は平服・喪服どっち?服装マナーや持ち物、香典はいる?
③仏壇を新しく交換したい時は?
◇新旧の仏壇を並べて、閉眼供養・開眼供養を行います
墓じまいの後、仏壇や位牌を新しく交換する家族も多いです。
従来の大きな仏壇を、暮らしやインテリアにマッチしたコンパクトな仏壇に交換します。
昔は仏間を要したり、押し入れを潰して大きな沖縄仏壇を入れましたが、現代ではリビングの棚上にも置けるような、コンパクトな棚上仏壇も販売されています。
新しい仏壇と交換したい場合、僧侶に閉眼供養・開眼供養を同時に依頼する流れです。
新旧の仏壇を並べて、僧侶に読経供養を依頼した後、古い仏壇のみを業者に引き取ってもらいます。
「開眼供養」とは、仏壇など礼拝の対象に魂を込めることです。
閉眼供養と開眼供養を依頼するため、お布施も1.5~2倍の金額を目安にして、約5万円~10万円ほど包みます。
・【沖縄の七夕】仏壇の購入や買い替えに良いタイミング、日にちとは?買い替えの供養は?
墓じまい後の仏壇:位牌はどうする?

◇「位牌を残したいか?」で判断します
墓じまいの後、仏壇じまいの閉眼供養まで済ませていたならば、位牌やトートーメーは家から出すことができるでしょう。
ただ仏壇じまいで一度トートーメータブーをリセットしたとして、位牌やトートーメーのみを祀るケースもありました。
もちろん仏壇ごと残すことも可能ですので、墓じまい後は仏壇や位牌、トートーメーを、「どこまで残したいか?」「いつまで残したいか?」で扱い方を判断します。
「いつまで残したいか」は、子や孫の代まで残すかどうか?を考えると良いでしょう。
・【沖縄のお墓】沖縄で今のお墓を霊園へ移す「改葬」。経験者が語る5つのトラブル体験談
①仏壇・位牌ともに残す
◇墓じまいをしても、仏壇を残して構いません
墓じまいをしたからといって、仏壇の維持管理・継承に問題がなければ、そのまま残しておいても問題はないでしょう。
墓じまいの後に仏壇・位牌(トートーメー)を処分することに迷うなら、扱いを決めるタイミングまで残しておき、ゆっくりと決める家族も多いです。
ただお墓と同じように、位牌やトートーメーには魂が入っているので、次の代の継承やお世話をする人々と相談をする必要はあります。
②トートーメーのみ残す
◇トートーメーのみを預ける、祀る選択もあります
引っ越しなどで仏壇を置くだけの充分なスペースがない場合、仏壇は処分してトートーメーのみを残す選択も多いです。
小さなステージ(祭壇)にトートーメーを祀る家族もいますし、個別の位牌であればベッドサイドやリビングに位牌のみを祀る家族もいます。
また位牌堂などで「位牌預かり」を依頼し、トートーメーを一時的に預けて残す選択も多いです。
③個別の位牌のみ残す
◇トートーメーのみを処分する方法です
先祖代々位牌「トートーメー」は、家や地域によって違いはありますが、さまざまなトートーメータブーが現代まで言い伝えられています。
現代では緩くなってきたものの、やはりタブーに触れる行為は避けたいですよね。
「弟や女性は継承できない」
「家の敷地から外へ出してはいけない」
「父方の血を引く者しか継承できない」
このような継承問題が深刻化するトートーメーは供養して処分し、個人の魂のみが宿る個別の位牌「カライフェー(唐位牌)」のみを祀ることで、トートーメータブーをリセットする選択も多いです。
④全て処分する
◇位牌と仏壇の全てを処分する方法です
墓じまいの後、自宅の仏壇やトートーメー、ご位牌を全て供養して処分します。
実家の建て替えや引っ越しなどで、仏壇を置くスペースがなくなる家族の他、両親が亡くなってから住む人のいない実家に置いている仏壇などにも多い選択です。
築年数が古い実家は固定資産税はもちろん、庭の手入れや定期的な掃除など、維持するだけでも費用がかさむため、相続時に実家をたたむことも多いですが、トートーメーも閉眼供養してから、丁重に処分すると良いでしょう。
・沖縄で相続した実家とお仏壇じまい☆空き家にするなら売却した方が良い理由
⑤手元供養にする
◇手元供養として遺骨を祀る方法です
墓じまいの後、仏壇やトートーメーは処分しますが、墓じまいで取り出した身内のご遺骨をメンテナンスして祀り、手元供養にします。
現代の沖縄では一般的に、ご遺骨をパウダー状に粉骨して小さくまとめるでしょう。
この場合、墓じまい後に亡くなった家族のご遺骨も、自宅で祀り供養する選択も多く、自宅で複数のご遺骨を納めて供養する「自宅墓」も登場しました。
個別の位牌「カライフェー(唐位牌)」は、処分する家族もいますし、骨壺と一緒に祀り残す家族もいます。
沖縄で墓じまい後、仏壇や位牌を残す注意点

◇トートーメーは後々まで継承者が必要です
イフェー(位牌)はお墓とは違い、そのまま残しても管理する料金も発生しません。
ただ、先祖代々位牌であるトートーメーにはさまざまなタブーがあります。
そのため、残しておくと将来的に、継承者問題が残る可能性もあるでしょう。
トートーメーをお世話する人がいなくなると、そのトートーメーは「ヒジュルグァンス(冷たい位牌)」として忌まれる風習があるので、注意が必要です。
①ヒジュルグァンスとは
◇お世話をする人をなくした位牌です
「ヒジュルグァンス」とは沖縄の言葉で「冷たい位牌」を意味し、継承者のいない先祖代々位牌「トートーメー」を指します。
例えば、お世話をしていた人が亡くなり、後継者がいないまま放置されてしまったトートーメーなどです。
また地域や家によっては「トートーメーは家の敷地から出してはいけない」との考え方もあるため、ヒジュルグァンスが空き家に放置されたまま、売却できない空き家も見受けます。
ヒジュルグァンスを避けるためには、手元に残す期限を設けて、今後の供養の仕方を改めて検討するなどの対策が必要です。
②アジカイグァンスとは
◇継承者以外の人へ預けられた位牌です
「アジカイグァンス」は沖縄の言葉で「預かり位牌」を意味し、本来は継承者の立場でない人が、一時的に預かることを指します。
例えば、長男がトートーメーを継承することはできないものの、将来的に孫(長男の嫡子)が継承する可能性がある時、その家の次男や娘が一時的に預かる形です。
ただ、アジカイグァンスのまま何代もお世話をした結果、本来はどこへ引き渡すべきトートーメーなのかも分からなくなっているものもあります。
将来的に子や孫に負担をかけないためにも、アジカイグァンスも避けた方が良さそうです。
・沖縄の先祖代々位牌「トートーメー」とは?そもそも家を守護する「祖霊信仰」ってなに?
沖縄で墓じまいの後、仏壇や位牌4つの処分方法

◇沖縄でトートーメーや位牌は供養をして処分します
沖縄ではカミ(神)として祖霊信仰の対象となるトートーメーは、魂の宿るものですので、処分にあたり丁重な供養が必要です。
閉眼供養により魂は抜けますが、それでも、塩をかけて破棄するような種類の祭具ではありません。
そのためご遺骨と同じように扱い、霊園や寺院など、信頼のできる場所へ相談をして、供養の後に処分をしましょう。
①仏壇仏具店に引き取ってもらう
◇仏壇仏具店に処分を依頼します
新しい仏壇を購入して買い替えたり、トートーメーから個別の位牌「カライフェー(唐位牌)」へ変えた場合などは、相談をすると引き取ってくれる仏壇仏具店が多いです。
仏壇仏具店では引き取った後、提携している位牌の供養塔で供養したり、お焚き上げによる供養の後に処分します。
②お焚き上げ
◇寺院や神社でお焚き上げをしてもらいます
墓じまいの後、仏壇は処分して、トートーメーは「お焚き上げ」を選ぶ方法です。
もともと昔から沖縄では、三十三回忌をもって弔い上げとし、トートーメーに祀られている故人の位牌札は、墓前でお焚き上げをされてきました。
お焚き上げは供養をして燃やし、煙を通して魂を天へ帰す儀式です。
寺院や神社で相談しますが、閉眼供養を依頼しているならば、僧侶に相談してみても良いでしょう。
③ヌジファー(抜魂)
◇ユタさんにヌジファー(抜魂)を依頼します
家付きのユタさんがいらっしゃる家族であれば、「ヌジファー(抜魂)」の儀礼を依頼する方法もあるでしょう。
ただ、現代ではユタさんが付く家もほとんどありません。
またヌジファー(抜魂)まで依頼できる、信頼できるユタさんを探すことも難しいです。
この他、昔の沖縄ではヌジファー(抜魂)の儀式を、自分達で行う家が多くありました。
ただ今では、沖縄の墓じまいと同様、僧侶に魂抜きをお願いする家が多いです。
・沖縄で古いトートーメーを、新しく買い替えたい!タブーもリセットする買い替え方とは?
④位牌の一時預かり
◇「位牌堂」ではトートーメーを一定期間、預かってくれます
「今、継承者はいなくても子どものなかから、トートーメーを継承する子が現れるかもしれない」と考える人もいますよね。
すぐにトートーメーやカライフェーの扱いを決断できない場合には、一時的に霊園や寺院などで「一時預かり」をしてもらう選択肢もあります。
| <トートーメーの一時預かりの一例> | |
| [費用目安] | ・約3万円~5万円ほど/年間 (1位の料金目安です) |
| [期間] | ・約1年~15年(平均3年~5年) ・契約更新あり |
| [内容] | ・個別スペースを提供(位牌の安置用) ・定期的な合同供養 ・個別の参拝ができる …など |
位牌の一時預かりサービスの多くが、個別のスペースを提供してもらい保管するため、多くの施設では預けた後の参拝も可能です。
また遺骨とトートーメーを一緒に保管することができる納骨堂もあります。
墓じまい後に、仏壇と位牌も整理するのであれば、遺骨の永代供養を依頼する霊園や墓地に、一緒に相談してみると良いでしょう。
・沖縄県メモリアル整備協会「ご遺骨、お位牌の一時預かり」
⑤位牌の永代供養
◇位牌の永代供養です
霊園や寺院墓地で「位牌供養塔」「位牌堂」など、位牌を供養する施設がある場合、墓じまいで取り出した遺骨と同じく、位牌も永代供養塔で永代供養ができるでしょう。
一般的に霊園や寺院墓地などの墓地内に位牌供養塔を設けていることが多いです。
墓じまい後の仏壇の整理であれば、一緒に相談するとスムーズに進みます。
| <トートーメー永代供養の一例> | |
| [費用目安] | ・約3万円~5万円/1位牌 (一度の支払いです) |
| [流れ] | ①閉眼供養 ②お焚き上げ ③位牌供養塔(永代供養) ④定期的な合同法要 |
| [その他] | ⑤石碑に名前を彫刻など (別途料金あり) |
墓じまい後に仏壇を処分するとして、トートーメーを永代供養にする場合には、最初の支払いのみですので、後々継続的な費用は掛かりません。
一例では、トートーメーはお焚き上げをした後、位牌供養塔で供養あれ、その後は他の位牌とともに合同供養が定期的に行われます。
なかには供養をした故人の名前を記載する石碑を設置した施設もあるので、家族が望むならば名前を石碑に彫刻することもできるでしょう。
・位牌永代供養
墓じまい後、仏壇を処分する費用相場
◇仏壇を処分する際の費用目安は、約1万円~8万円ほどです
仏壇は位牌であるトートーメーを残すための箱ですので、自分達で粗大ゴミとして処分しても問題はありませんが、あまり気持ちの良いものではありませんよね。
そこで一般的には仏壇仏具店に引き取りを依頼する家が多いでしょう。
仏壇仏具店では、魂を抜く閉眼供養を施した後に処分されます。
①自分で処分する
◇粗大ゴミの処分費用として、約千円~1万円です
自分で仏壇を処分する場合は、仏壇は箱ですので粗大ゴミとして捨てることもあります。
この場合、大きな仏壇は粗大ゴミとして処理されるので約千円~1万円が費用相場です。
ただし大きな仏壇になると解体作業も必要になるでしょう。
仏壇の解体を業者に依頼する場合は、解体費用が約1万円~3万円を目安にかかります。
自分で処分する時には仏壇に塩を振りかけ、清めてから処分すると良いでしょう。
②仏壇仏具店に依頼する
◇仏壇仏具店に引き取ってもらう費用相場は、約2万円~8万円です
仏壇仏具店でも相談をすると、古い仏壇を引き取ってくれます。
トートーメーや個別の位牌カライフェー(唐位牌)も引き取り、供養・処分してくれる仏壇仏具店もあるので、一緒に依頼できて助かるでしょう。
僧侶と提携している仏壇仏具店が多いため、閉眼供養を依頼できる僧侶の紹介も期待できます。
③処分業者に依頼
◇処分業者の費用相場は、約1万円~3万円です
広くは丁寧に供養し処分してくれる仏壇仏具店に引き取ってもらう選択肢が多いですが、仏壇は物ですので処分業者に依頼することもできます。
ただ処分業者はあくまでも物として処分しますので、トートーメーや位牌を依頼した場合にも供養はされません。
トートーメーや位牌のみを残す選択での仏壇処分では、より手頃な価格で依頼できます。
墓じまいの手順
◇墓じまいは、行政手続きが必要です
墓じまいでは遺骨を取り出してから墓石を撤去するため、人の遺骨を取り出すにあたり、「改葬許可申請」の手続きをしなければなりません。
改葬許可申請を行い「改葬許可証」を入手したら、遺骨の取り出しを依頼する石材業者や、新しい納骨先の墓地管理者(霊園など)に提出します。
自治体により改葬許可申請の形式が異なりますので、最初にお墓がある自治体のHPで確認、もしくは電話で確認をするとスムーズです。
また沖縄には少ないですが、寺院墓地にお墓がある場合は「菩提寺」となり、関係性にも配慮が必要なので、早い段階で墓じまいの相談をすると良いでしょう。
①遺骨の納骨先を決める
◇「受入許可証」を受け取ります
改葬許可申請では、取り出した遺骨の新しい納骨先を記載する欄があるので、先に納骨先を決めておくと行政手続きがスムーズでしょう。
改葬許可申請書に、納骨先の墓地管理者による捺印が必要な自治体もありますし、納骨先から遺骨を受け入れる証明の書類「受入許可証」を発行してもらい、提出する自治体もあります。
取り出した遺骨の新しい納骨先には、永代供養墓(合祀墓)や納骨堂などがあります。
それぞれの費用目安など、詳しくは後述しますので、どうぞ最後までお読みください。
②現存の墓地管理者に報告
◇「埋葬証明書」を入手します
改葬許可申請では、既存の墓地に遺骨が埋葬されている証明の書類「埋葬証明書」の提出が求められます。
そのため霊園や寺院墓地など、墓地管理者が管理する墓地にお墓がある場合、墓地管理者へ墓じまいの相談・報告をして、埋葬証明書を発行してもらいましょう。
一方、沖縄には個人墓地が多いですが、これは「みなし墓地」となり、本来は知事が認める墓地に遺骨が埋葬しなければなりません。
そのため自治体に相談をして、どのように進めれば良いか、倣いましょう。
一般的には墓地の名義人である墓主の捺印やサイン、お墓の地図が求められます。
・個人墓地の墓じまいとは?無許可墓地の問題点とは?墓じまい後の個人墓地は売却できる?
③改葬許可申請を行う
◇「改葬許可証」を発行してもらいます
受入許可証と埋葬証明書を提出して、お墓がある自治体の役所で改葬許可申請を進めることで、お墓からご遺骨を出す許可証「改葬許可証」を発行してもらいましょう。
改葬許可証を霊園や石材業者へ提出することで、お墓から遺骨を取り出します。
改葬許可証がなければ石材業者も受け付けができないので、注意をしてください。
④閉眼供養
◇閉眼供養をしてから遺骨を取り出します
一般的に仏教に倣い供養を行うため、僧侶を手配して閉眼供養を依頼し、お墓から魂を抜いた後に遺骨を取り出す流れです。
閉眼供養は約30分~1時間ほどで終了します。
お布施は1回の読経供養に付き、約3万円~5万円ほどを目安として包んでください。
また閉眼供養は親族を呼び広く執り行うこともできますが、墓じまいでは家族のみでラフに進めるケースが少なくありません。
⑤遺骨の取り出し
◇墓石業者へ依頼して遺骨を取り出します
閉眼供養と同日に墓石業者にも依頼し、閉眼供養の後、すぐに遺骨を取り出す流れです。
お墓の開閉は自分達でもできますが、墓石は重く怪我や転倒リスクがあるでしょう。
一般的にご遺骨の取り出しは、石材業者へ依頼する家族が多いです。
遺骨の取り出し費用の目安は1人あたり約1万円~3万円ほど、墓じまいにあたり、石材業者に内部調査を依頼することで、お墓に納骨されている遺骨の柱数が分かるので、予算計画も立てやすいでしょう。
⑥墓石の撤去
◇墓石の撤去、墓地の整理を行います
石材業者に依頼して墓石の撤去、及び墓地の整地を行った後、墓地管理者へ返還です。
個人墓地に建つお墓でも、墓地を整地して墓地の廃止手続きを行うことで、土地として販売ができます。
墓石の撤去、墓地の整地費用は、霊園などに建つコンパクトなお墓であれば、約15万円~20万円ほどで依頼できますが、個人墓地には大きな墓地やお墓もありますよね。
大きさやお墓の状況によって費用も異なるため、見積もりを出してもらいましょう。
・墓じまいにかかる費用はどれくらい?内訳や安く抑えるポイント、払えない時の対処法
⑦遺骨の埋葬
◇納骨式を行います
遺骨を取り出した当日、そのまま新しい納骨先へと納骨する流れが多いです。
また納骨では、仏教に倣い「納骨式」を執り行う家族も多いでしょう。
また長くお墓に納骨されていた遺骨は、骨壺に水が溜まっていたり、遺骨にカビが生えているなど、衛生状態が悪いものがあります。
納骨堂など個別に遺骨を安置し供養する場合、納骨前に遺骨の洗浄や乾燥などのメンテナンスを行うこともあるでしょう。
・遺骨にカビが生えた時の対処法!手元供養で役立つ5つのカビ対策、古い遺骨はどうする?
墓じまい後、遺骨の納骨先は?

◇墓じまい後の遺骨は、永代供養が多いです
「永代供養(えいたいくよう)」とは、本来の継承者である、子どもや孫などの家族に代わり、霊園などの施設管理者が、永代に渡って遺骨を供養してくれることを指します。
ただし永代供養は形のないサービスなので、遺骨の管理や供養方法はさまざまです。
いずれにしても永代供養を選ぶことで、継承者問題が解消されます。
もしくは遺骨を土に戻す海洋散骨などの「自然葬」、自宅で遺骨を供養する「手元供養」なども選択肢のひとつです。
①永代供養墓(合祀墓)
永代供養墓(合祀墓)は、ひとつの場所に他の遺骨と一緒に合祀される遺骨供養の方法となり、遺骨1柱で約3万円~15万円ほどのプランが多い、遺骨供養のなかでは最も安い方法です。
ただし最初から他の遺骨とともに合祀されるため、一度納骨すると、後から再び取り出すことができません。
・【2024年最新ランキング】沖縄でおすすめの永代供養墓トップ13件、口コミも紹介!
・永代供養、納骨堂「おきなわ霊廟」
②納骨堂
納骨堂は遺骨が個別に収蔵できるスペースが提供された屋内施設です。
そのため将来的に遺骨をお墓に埋葬したい、移動する予定がある家族には助かります。
ただ納骨堂も永代供養が付いているので、個別に安置される期間があります。
更新なく、契約した個別安置期間が過ぎると、霊園や施設内の永代供養墓(合祀墓)に合祀される仕組みです。
施設により3年間・10年間・17年間とさまざまなので、契約時に確認をしましょう。
また個別安置期間に公共スペースの維持管理費「年間管理料」がかかるかも確認をすると安心です。
③一般墓
沖縄では個人墓地が多く永代供養を付けることはできませんでした。
けれども墓地管理者が墓地を管理する、霊園や寺院墓地などでは、現代は永代供養を付けることができます。
墓石代とは別に、永代供養を付ける費用は約40万円ほどが目安です。
永代供養を付けることで、将来的に継承者が不在になった時にも、無縁墓になる心配がありません。
ただお墓を建てるため定期的なメンテナンスは必要です。
また公共スペースの維持管理費として、毎年の年間管理料が約5千円~2万円ほどを目安にかかります。
・沖縄の霊園で、お墓を建てる費用は平均的にどれくらい?安くお墓を建てるポイントとは?
・沖縄メモリアル整備協会「メモリアルパークのご案内」
④自然葬
樹木葬や海洋散骨を代表する、遺骨を自然に還す自然葬もあります。
自然葬型の樹木葬では、遺骨を骨壺から取り出して土に埋葬し、長い時間をかけて土へ還す仕組みです。
また沖縄で人気が高い海洋散骨は、遺骨をパウダー状の粉末に粉骨して海に撒きます。
自分達で散骨しても問題はないのですが、自治体によっては散骨を禁止する区域を設けたり、近所迷惑になるトラブルもあるので、一般的には散骨業者へ依頼します。
・永代供養・海洋散骨「美ら海」
沖縄で墓じまい後、仏壇じまいをした体験談

亡くなった娘の位牌を残し、仏壇じまいを行った康子さん(83歳・仮名)の体験談です。
沖縄では女性が実家で祀られる時、台所に小さな祭壇を設ける「サギブチダン(下げ仏壇)」の習慣がある地域もありますが、康子さんの家ではご先祖様と脇に娘の位牌が祀られていました。
・儀礼ではなく、娘を偲びたい
・娘を身近に感じたい
娘の位牌が先祖代々の仏壇に祀られることは有難いのですが、喪失感に悩む康子さんにとって「より身近に娘を感じる、自由な供養がしたい」と思ったことが、仏壇じまいのきっかけです。
①娘とともに墓じまい
◇夫が亡くなり、墓じまいを決断します
夫は門中墓の墓主でしたが本州へ移住する親族が増えたことで、門中墓から抜ける人々が多く、年度ごとに交代で管理をしてきた門中墓の負担が大きくなっていました。
また古い門中墓で定期的な掃除はもちろん、修理修繕などの維持管理費も負担がかかり、娘の静香さんと相談した結果、墓じまいを行います。
自宅には大きな仏壇と先祖代々位牌「トートーメー」が祀られていましたが、夫の名前札も入ることから、仏壇はそのまま残すことにしました。
・沖縄のお墓「門中墓」から抜けるには?次男・三男は門中墓に入れない?納骨後の独立は?
②トートーメーのお世話
◇旧盆やスーコー(焼香)も施主として行いました
トートーメーを祀るウフヤー(本家)として、旧盆には親族を迎え入れ、祀るトートーメーの年忌法要「ニンチスーコー(年忌焼香)」も執り行う康子さんでしたが、高齢になり、体力的な負担が大きく感じるようになります。
親族も高齢になり参加が難しくなったり、亡くなる親族も増えるなか、少しずつスーコー(焼香)の規模は小さくなりました。
・沖縄の「スーコー」とは?独自の御願文化を持つ沖縄では、どのように故人を供養するの?
③乳がんになった娘
◇娘の静香さんが、ある朝、亡くなっていました
康子さんは夫を亡くしてから、独身の静香さんと2人暮らしをしていました。
ある朝、珍しく起床しない静香さんの部屋を訪れると、布団に寝たまま亡くなっていたのです。
警察署の解剖の結果、末期の乳がんだったことが分かります。
けれども康子さんは、静香さんが病院に行った様子もなく、もちろん本人からも乳がんの相談は受けていません。
・沖縄で身内が亡くなったら、まず何をする?ご遺体搬送~葬儀まで10の手続きと費用目安
④強い喪失感
◇突然のことで、喪失感や後悔に苛まれました
解剖医のお医者さんは「本人が気づかない訳がない」と言いますが、「なぜ、娘は病院へ行かなかったのか」その真意は本人にしか分かりません。
高齢になった康子さんの暮らしを日々サポートしてくれた、在りし日の静香さんを思うと、大切な家族を失った強いショックや喪失感「グリーフ」に苛まれました。
・沖縄で喪失を乗り越えるグリーフケア☆無意識に訪れる症状と乗り越え方
⑤娘のカライフェー(唐位牌)
◇娘の静香さんは、個別の位牌「カライフェー(唐位牌)」を仕立てます
夫は先祖代々位牌「トートーメー」に名前札があり、康子さんもいずれは夫の下に名前札が祀られる予定です。
一方独身だった娘の静香さんは、個別の位牌「カライフェー(唐位牌)」を仕立て、トートーメーの脇に祀りました。
現代の戸建て住宅なので、昔ながらの平屋にある沖縄仏壇ではありませんが、押し入れをひとつ潰して仕立てた大きな仏壇です。
そこで、ご先祖様が宿るトートーメーの脇に小さく、静香さんのカライフェー(唐位牌)を祀り、今までの先祖供養と同じように、日々お世話をしていました。
・そもそも位牌とは?本当に必要?お仏壇なし位牌はどうする?位牌の代わりになる仏具は?
⑥儀礼で供養をしているような…
トートーメーとともに、夫や娘の供養を毎日続けても、康子さんの喪失感はより募るばかりです。
今まで通り日々のお茶やご飯のお世話、旧暦行事にはお供え物をして、スーコー(焼香)も小規模ながら欠かさず行ってきましたが、気持ちが晴れないまま3年が経ちます。
だんだんと康子さんは引きこもり状態になり、うつ症状に悩まされるようになりました。
⑦娘を供養したい
ある日、康子さんはトートーメーと娘の位牌が安置された沖縄仏壇を眺めながら「私は娘の供養がしたい、形式的な供養の儀礼がしたい訳ではない」と思います。
確かに康子さんは、家のトートーメーを真面目にお世話してきました。
けれども長年長男嫁として義務を全うする気持ちの方が強く、カミ(神)・ご先祖様に感謝を捧げる儀礼に近い感覚です。
けれども夫と娘と言う、大切な家族を亡くした時、カミ(神)やご先祖様に対してではなく、「夫や娘の魂を供養したい」と願っている自分に気づいたと言います。
⑧トートーメーのお世話が負担
また娘を亡くして以降、康子さんはトートーメーのお世話をする気力が無くなった、とも感じていました。
娘の位牌を祀って弔いたい一方で、旧盆に夫の兄弟など、親族が我が家へ集まったり、義理の両親がしてきたような、ご先祖様への行事をすることは、正直億劫でもあったと言います。
「ただ、娘の位牌を眺めていたかった」
そう感じた康子さんは、義理の妹(夫の妹)へ気持ちを吐露したところ、義理の妹から「位牌の永代供養」があることを聞きました。
⑨仏壇じまい
康子さんは、夫と娘の位牌のみを残した仏壇じまいを決断します。
トートーメーには夫の位牌札が入っていましたが、これを娘の位牌と同じカライフェー(唐位牌)に仕立て直し、トートーメーを位牌堂で永代供養しました。
そして大きな沖縄仏壇を閉眼供養し処分します。
①夫の位牌を新しく仕立てる
②トートーメーを永代供養
③仏壇の閉眼供養
④仏壇を引き取ってもらう
⑤夫と娘の位牌のみ祀る
周囲に聞くと「仏壇は塩を振って燃えるゴミや粗大ゴミとして出しても良い」と言い、「気になるなら墓前でお焚き上げしたらいいよ」ともアドバイスをもらいます。
ただ康子さんは83歳の高齢で、個人で火を扱うことへの不安や「このようなもので良いのかな?」との不安がありました。
⑩閉眼供養はした方が安心
結局、康子さんは僧侶を手配して閉眼供養を行い、魂を抜いてから処分します。
僧侶は、夫や娘の位牌を仕立てた仏壇仏具店で紹介していただきました。
僧侶へのお布施は3万円、仏壇仏具店のスタッフに尋ねた金額を包みましたが、この他、御車代として5千円も別に用意しています。
⑪夫や娘をイメージした小さな祭壇
最初はリビングの棚上に夫と娘の位牌のみを祀り、花立て・香炉・燭台の仏具「三具足」を並べていました。
けれども日々、夫や娘の位牌のお世話をして話しかけるうち、二人のイメージに合わせた小さな仏壇を仕立てたいと考え、仏壇仏具店に足を運びます。
①上置き型仏壇…約18万円
②仏具セット…約3万7千円
——————————–
●合計…約21万7千円
実は康子さんは夫の名前札をカライフェー(唐位牌)を仕立て直した時、二柱が丁度収まるほどの、小さな祭壇も発見していました。
最初は仏壇じまいで残した仏具を利用していましたが、夫や娘の位牌に合わせた可愛い仏具も購入し、リビングの康子さんがいつもいる場所に配置しています。
まとめ:沖縄では墓じまい後の仏壇じまいが増えています

家族や親族が日本全国、世界へと移住するケースも増え、家族や親族単位でのお墓の維持管理体制が崩れることで、墓主ひとりにお墓の維持管理への負担がのしかかるようになりました。
さらに墓主の高齢化、継承者の不在で、個人墓地に建つ沖縄のお墓は継承者問題が深刻化しています。
この流れから墓じまいが増えていますが、かつては仏壇じまいまで進めるケースは、今ほど多くはありませんでした。
けれども仏壇やトートーメーを残したままの空き家が増え、相続した子どもや孫も、空き家、しいてはトートーメーの扱いに困っているとの相談も増えています。
沖縄では墓じまいとともに、仏壇じまいも検討することも大切なのかもしれません。