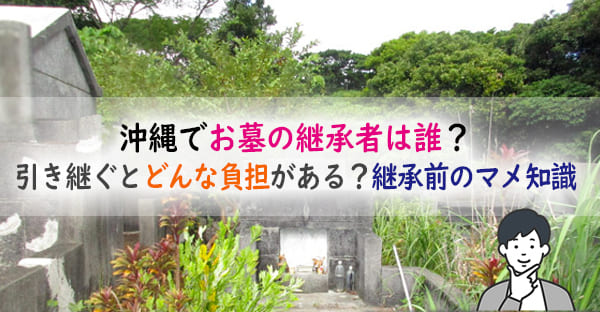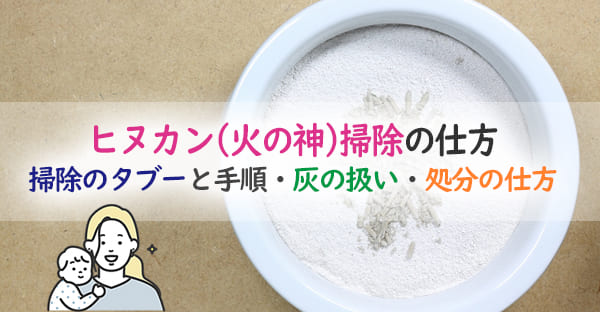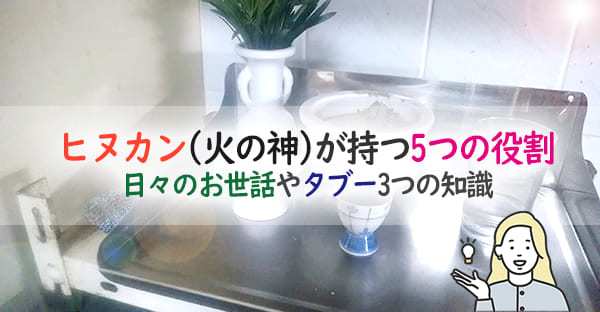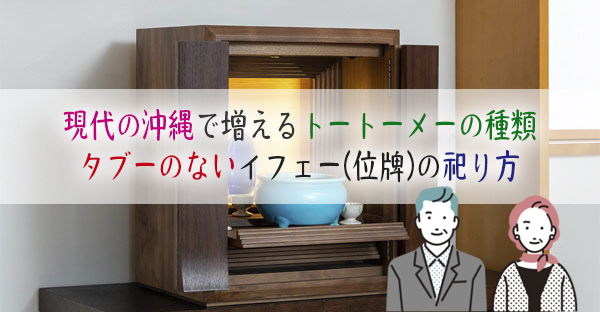「沖縄でお墓を継承する人は誰?」
「沖縄でお墓の継承は放棄できない?」
「お墓の継承ができない時はどうすればいい?」
沖縄ではお墓の継承者がいない「お墓の継承問題」が深刻化しています。けれども墓主不在のままお墓を放置すると無縁墓になってしまうでしょう。沖縄県では無縁墓の放置問題が起きています。
本記事を読むことで沖縄独自のお墓継承にまつわる歴史とともに、沖縄でお墓を継承をする人は誰か?が分かります。どのような負担がかかるのか?
どうしてもお墓の継承ができない時の対処法もご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。
沖縄でお墓継承を巡る歴史
全国的には先祖代々墓を継承しますが、沖縄では「門中墓」が一般的です。「門中(むんちゅう)」とは父方血族を指し、「門中墓(むんちゅうばか)」は父方血族とその妻が入るお墓です。
沖縄でお墓継承を巡る歴史には、本州とは違う3つの特徴があります。琉球王朝時代・アメリカ統治時代・長期に渡る旧民法の適用です。
・沖縄のお墓が大きいのは、昔の風習にあった!他県と違う5つの風習、お墓参りルールとは
①琉球王朝時代
沖縄は独自の琉球王朝の歴史を辿っています。日本の江戸時代まで琉球王朝は日本の鹿児島藩と中国に両属して、独自の貿易「琉球貿易」を行ってきました。
琉球が沖縄県となったのは1871年(明治4年)の廃藩置県以降です。そのため本州で根付く「檀家制度」が根付いていません。
「檀家制度」とは戸籍代わりに民衆が寺院に属する制度で、江戸時代には「寺請制度」と呼ばれていました。民衆は寺院に属することで身分証明「寺請証文」を得たため、全国的には誰もがいずれかの寺院に属していたのです。
民衆は特定の寺院の「檀家(だんか)」となり、亡くなると寺院が運営する寺院墓地にお墓を建てて埋葬してきました。
檀家制度は江戸幕府とともに無くなりましたが、今も寺院墓地に建つ先祖代々墓は残っています。対して沖縄ではそもそも檀家制度がなく、寺院墓地もほとんどありません。
②アメリカ統治時代
戦後の1945年(昭和20年)~1975年(昭和47年)まで27年間にわたるアメリカ統治時代を経て、1975年5月15日に本土復帰を果たしました。
アメリカ統治時代の沖縄では、比較的自由にお墓を建てています。個人墓地にコンクリート墓の大きな門中墓が一般的です。そして門中の人々で定期的にお金を集める「模合(もあい)」により、お墓の維持管理を行ってきました。
この歴史は沖縄で、公営墓地の整備・民間霊園や寺院墓地の参入が遅れた遠因です。人々の暮らしがグローバルになった現代の沖縄では、墓主不在で廃墟と化したお墓問題が深刻化しています。
③旧民法の適用
1898年(明治31年)から施行された旧民法には、一家の家長が亡くなると長男が全財産を相続する権利を持つ「家督制度」がありました。
家督制度は一家の家長は全財産を相続する代わりに、お墓・仏壇などの祭祀財産を継承し守り、家長として家族を扶養する義務を負う制度です。
本州ではこの家督制度を含む旧民法が戦後の1947年(昭和22年)に廃止されました。けれども沖縄では旧民法が1956年(昭和31年)まで適用されています。つまり家督制度も1956年(昭和31年)まで残っていたのです。
沖縄でお墓を継承するのは誰?
日本でお墓や仏壇(位牌)など、ご先祖様を供養するための財産を法的に「祭祀財産(さいしざいさん)」と言います。祭祀財産を継承する人は「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」です。
祭祀財産は継承するものであり相続財産ではないので、継承しても相続税がかかりません。けれども祭祀財産を継承すると、お墓を守る責任と負担が生じます。
また家督制度のない現法律では、祭祀財産を継承したからと言って相続財産が増える訳でもありません。そのためお墓・仏壇などの祭祀継承者不在のまま、無縁墓・無縁仏になる問題が深刻化しています。
・【沖縄の終活】相続税が掛からない財産は?生前購入で預貯金を減らす
①遺言書で指定された人
祭祀継承者を決めるにあたり最も優先されることは故人の遺志です。法的効力がある遺言書に祭祀継承者の指定がある場合、最も優先されます。
遺言書に日付・署名・押印がなかったり、自筆証書遺言を自筆で書いていないなど、法的効力を欠く・無効となる可能性もあるでしょう。
・【沖縄の相続】自筆証書遺言が無効にならない5つのチェックポイント
・【沖縄の相続】公正証書遺言でも無効に?有効を保つ5つのポイント
②相続人間で決定
遺言書がない・遺言書に記載がなかった場合、続いては法定相続人間での話し合いで祭祀継承者を決定します。相続発生にあたり、財産分割の話し合いが法廷相続人間で行われます。
財産分割が決定すると「遺産分割協議書」を行政へ提出しますが、一般的に祭祀財産は相続財産とは別の扱いになるため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
ただし墓主が墓地の名義人である「個人墓地」では、継承にあたり名義変更が必要です。相続税はかからないものの、手続き上は一般的な不動産財産と同じ扱いで処理します。
・【沖縄のおひとりさま終活】相続人になる人と優先順位を知っておく
③慣習による決定
沖縄のお墓は父方の血族が入る「門中墓」が、本州の先祖代々墓にあたります。門中墓を代々守る「ムートゥーヤー(本家)」の嫡男が継承するとされてきました。
女系家族の場合、本州では婿養子によるお墓の継承もありますが、沖縄では父方血族から継承者を選ぶ風習がありました。本州よりもお墓の継承者候補が限られ、悩む墓主が増えています。
お墓の継承者が決まらないまま墓主が亡くなり、墓主不在のまま放置された無縁墓が廃墟と化し、街の景観を阻害するとして自治体により撤去される事例も起きました。
④家庭裁判所で決定
相続人間での話し合いや慣習によって祭祀継承者が決まらなかった場合は家庭裁判所に持ち越されます。
被相続人(故人)の最後の住まいを管轄する家庭裁判所へ「祭祀継承者指定の調停、または審判」を申し立てる流れです。家庭裁判所では被相続人(故人)と相続人の関係性などを基に決定します。
ちなみに家庭裁判所による祭祀継承者の決定は放棄できません。相続放棄をしても祭祀継承者としての責任は残りますので、ご注意ください。
⑤相続人ではなくても良い
実は祭祀継承者は、法的には特に法定相続人である必要はありません。例えば内縁の妻や親しい友人へお墓の継承を託すこともできます。
墓地管理者がいる霊園・墓地にお墓が建つ場合、近年では「友墓」と呼ばれる友人同士で建てたお墓も見受けるでしょう。お墓の関係者が納得するならば問題はありません。
ただしお墓の継承者は親族に限ることを規約に設けた霊園・墓地もあります。特に寺院墓地では信仰から、継承者を3親等までを条件とすることも多いです。霊園・墓地にお墓を建てる場合は、お墓の継承に関する規定を確認しましょう。
沖縄でお墓を継承する流れは?
霊園・墓地に建つお墓は墓地管理者が所有しています。墓主は墓地管理者から墓地区画を永代に渡り使用する権利「永代使用権」を購入する仕組みです。
一方、沖縄で根付く個人墓地の所有者は墓主です。そのため行政手続き上は一般的な土地と同じように、名義変更などの手続きを行います。
①個人墓地の継承手続き
沖縄の個人墓地は名義人が墓主になるので、一般的な土地の名義変更と同じ手続きです。名義変更は法務局で行います。
生前の継承であれば墓主が生きていますが、墓主が亡くなった後は一般的な相続財産と同じ手続きを踏まなければなりません。遺産分割協議書が名義変更手続きに求められます。
・戸籍事項証明書
・遺産分割協議書
遺産分割協議書には相続人全員が捺印をします。遺産分割協議を済ませなければお墓の継承手続きも進まないでしょう。遺産分割協議はトラブルがなければ10ヵ月までが期限です。
沖縄では個人墓地の継承は相続財産と同じ扱いですが、扱いは祭祀財産になります。名義変更後も、墓地登録を済ませている土地の継承に相続税はかかりません。
・沖縄県「墓地等に関すること」
②霊園・墓地の継承手続き
沖縄で霊園・墓地に建つお墓の継承手続きの詳細は、墓地管理者によって異なります。一般的には、被相続人(故人)と相続人の関係性が分かる書類の提出が求められるでしょう。
まずは墓地管理者に墓主が亡くなった旨を伝えて、必要書類を確認します。基本的には墓地管理者の指示に従い手続きを進めると良いでしょう。
・被継承者(故人)の戸籍謄本(除籍謄本)
・継承者の住民票(本籍記載・世帯全員)
・認印
・永代使用許可証
・契約書
・名義変更手数料
沖縄の霊園・墓地でのお墓継承にあたり、名義変更手数料がかかることがあります。施設により異なりますが、手数料の費用相場は約1,500円~5千円ほどが目安です。
また墓地区画を永代に渡り使用する権利「永代使用許可証」を紛失している場合は、再発行を行います。再発行料として約8千円~1万円ほどの支払いを求められることがあるので、確認してから手続きを進めましょう。
③生前に行う個人墓地の継承手続き
沖縄の個人墓地に建つお墓は、しばしば生前に継承手続きを済ませることがあります。相続が発生した後では遺産分割協議書が必要になるため、手続きが複雑になるためです。自治体により異なりますが、必要書類には下記のようなものがあります。
・墳墓地使用権承継許可申請書
・墓主と承継者の関係性が分かる書類(戸籍謄本など)
・承継者の特別住民票抄本(不要な自治体もあり)
・使用権承継同意書(墓主・継承者の記名・捺印)
・印鑑(認印可)
・顔写真付きの身分証明書
生前に個人墓地の継承手続きを行いたい場合は、お墓が建つ地域を管轄する自治体の役所窓口で確認を取りましょう。
・那覇市「識名霊園墓地地区 承継手続きについて」
沖縄でお墓を継承した時の負担
沖縄の個人墓地であっても、お墓を継承するにあたり相続税はかかりません。けれども沖縄でお墓の継承をすると、墓主としての責任が伴います。
また沖縄ではお墓とともに先祖代々位牌「トートーメー」の継承が必要です。祖霊信仰が根付く沖縄では、トートーメーを中心にご先祖様を祀ってきました。
ムートゥーヤー(宗家・本家)として、シーミー(清明祭)やジュールクニチー(十六日祭)、旧盆などのご先祖様を供養する年中行事を進めなければなりません。
・沖縄のトートーメーとは?タブーで増える沖縄のトートーメー継承問題を解決する方法とは
①経済的負担
沖縄でお墓を継承した後は、定期的なお墓のメンテナンスや清掃費用がかかります。また老朽化したお墓の修理修繕費用も念頭におかなければなりません。
沖縄では戦後にコンクリート墓が広がりましたが、現在のコンクリート墓がどこも老朽化が進んでいます。ヒビ割れなどの補修を毎年続けてきたために、建て替えを決めるお墓も増えました。
また細かい内容ですが、シーミー(清明祭)や旧盆など年中行事では、供物や花の費用もかかります。定期的なお墓掃除を代行業者に託す場合は、掃除費用もかかるでしょう。
霊園・墓地に建つお墓を継承した場合は、共有スペース・設備の維持管理費として毎年「年間管理料」を支払います。費用相場は約5千円~2万円です。
②時間的負担
沖縄の個人墓地に建つお墓を継承した場合、広い墓地区画を定期的に清掃しなければなりません。特に夏場には雑草が茂るため、雑草の除去は不可欠です。
沖縄ではお墓の継承に伴い、現在は使用していない古いご先祖様が眠るお墓「アジシー墓(按司墓)」をも継承することがあります。アジシー墓(按司墓)は辺境地に建つものも多く、墓地のメンテナンスは時間的・体力的な負担があるでしょう。
またアジシー墓(按司墓)を継承した墓主は、シーミー(清明祭)前に家族でお墓参りに行く風習があります。
・沖縄のお墓参り行事シーミー(清明祭)、2024年はいつ?お供え物や拝み方まで解説!
③精神的負担
祖霊信仰が根付く沖縄のお墓を継承することは、精神的な負担も伴います。
特にお墓とともに継承する先祖代々位牌「トートーメー」は、扱い方や次代への継承に対してトートーメータブーがありました。
お墓を閉じる「墓じまい」や霊園へ引っ越す「改葬(かいそう)」の決定権は墓主にありますが、家族・親族の反対意見や苦情にも対応・調整しなければなりません。
④法的責任
沖縄で個人墓地のお墓を継承する場合、墓地の名義は墓主です。墓地管理者がいる霊園・墓地にお墓を改葬したとしても、墓地を永代に渡り使用する「墓地使用権」の管理責任が伴います。
個人墓地では近隣のお墓への配慮が必要ですし、霊園・墓地では利用に際し規約を順守しなければなりません。墓主以外の家族・親族がお墓参りに行った場合にも、そこで起きたトラブルに関しては墓主の管理責任が問われるでしょう。
⑤将来的な課題
墓主が高齢になると次世代の継承者を探さなければなりません。けれども人々の暮らしがグローバル化した現代では、次世代の継承者を見つけることさえ困難です。
墓石を建てるお墓は定期的なお墓掃除・メンテナンスを必要とするため、遠方に住んでいるとお墓の維持管理が困難になります。
お墓掃除代行業者は登場しましたが、依頼するとそれだけコストもかかるでしょう。特に沖縄の個人墓地は墓主自身が名義人なので、全てを一人で担わなければなりません。
また墓主自身が高齢になると、定期的なお墓掃除・メンテナンスが困難になります。辺境地にあればお墓参りさえ大変になるでしょう。
・沖縄で深刻化するお墓問題とは?本州と違う特徴や、墓主が抱える5つの問題や対策を解説
沖縄でお墓の継承者がいない時はどうする?
沖縄でお墓の継承者がいない場合、墓じまいの選択肢があります。特に沖縄の個人墓地は墓主不在のまま放置してしまうと、行きつく先は無縁墓です。
墓じまいでは、お墓に眠っていたご遺骨を取り出して永代供養をします。「永代供養」とは霊園などの墓地管理者がご家族に代わり、ご遺骨を永代に渡って管理・供養をするサービスです。
①永代供養の注意点
永代供養はご遺骨を永代に渡り管理・供養をしてくれますが、永代に渡って「個別で」管理してくれる訳ではありません。
この、ご遺骨が個別に安置される期間が「個別安置期間」です。ただし合祀後も共有の墓標に向かってお墓参りはできるでしょう。
②個別安置期間はどれくらい?
個別安置期間は、永代供養プランや霊園・墓地によって異なります。継承型の永代供養では、ご遺骨の弔い上げと同じ25年・33年・50年などの長い個別安置期間もあるでしょう。
お墓を閉じてご遺骨を墓地管理者へお任せするため、その後はお墓継承の責任から解放されます。ご遺骨の管理や供養はお任せしながら、思い立った時にお墓参りに行くことができるでしょう。
②墓主不在のまま放置するとどうなる?
現在では墓主が分からないまま荒廃した無縁墓の問題が沖縄で深刻化しています。無縁墓を撤去する自治体もありますが、充分な予算がないまま放置される事例もあるでしょう。
墓じまいは一度、お墓を継承して決定権を得なければなりません。墓主として自治体の役所窓口で「改葬許可申請」を行い、墓じまいを進めましょう。
・墓じまいを進める9つの流れとは?ステップごとの費用目安やかかる日数、墓石や遺骨は?
お墓を継承できない時、具体的な方法は?
永代供養は形のないサービスなので、あらゆる形態に付加することが可能です。霊園・墓地に建つお墓であれば、一般墓(個別墓)に永代供養を付けることもできるでしょう。
永代供養プランを選ぶポイントは、ご遺骨の個別安置期間です。個別安置期間が長いに越したことはありませんが、長ければ長いほど費用も高くなります。
①お墓に永代供養を付ける
お墓に永代供養を付けることで、次世代の継承者が見つからなくても無縁墓になりません。ただし墓石が建つため、定期的なお墓掃除やメンテナンスは必要です。
霊園・墓地にお墓を建てる費用相場は約100万円~350万円です。墓地区画やお墓の大きさ・デザイン・墓石のグレードなどで費用が大幅に変わるでしょう。
永代供養は霊園などの墓地管理者が提供するサービスなので、当然ながら墓地管理者が運営する霊園・墓地にお墓が建っていなければなりません。個人墓地に建つお墓であれば、霊園・墓地への改葬が必要です。
②室内墓所・納骨堂
「納骨堂」は屋内施設にご遺骨を収蔵する施設です。ロッカー型・仏壇型などさまざまな形態があります。個別安置期間も3年・7年・15年など施設によりさまざまです。
「室内墓所」は屋内施設にご家族のご遺骨を収蔵できる施設となり、ご夫婦2人・ご家族4人~8人など複数のご遺骨を一緒に収蔵できます。また個別安置期間が33年・50年と長期・更新ができるプランが特徴です。
沖縄の室内墓所はお参りに行くと、お墓がある個別ブースに案内されます。ご遺骨が自動的に運ばれてくる「ビル型(自動搬送型)納骨堂」と同じ仕組みです。法要施設を設け、予約をすると法要室にご遺骨が運ばれてくる室内墓所もあるでしょう。
③自宅墓・手元供養
ご遺骨は自宅で祀る「手元供養」もできます。ご遺骨をそのまま祀ることもできますが、現代ではご遺骨をパウダー状に粉骨して、可愛い骨壺にコンパクトにまとめる人が多いです。
手元供養は祭壇にご遺骨を祀る方法と、ペンダントトップなどのアクセサリーに粉骨したご遺骨を納めて、一緒に持ち歩く方法があります。
「自宅墓」とは複数のご遺骨を納めた仏壇型のお墓です。ブック型の骨箱に、粉骨したご遺骨を真空パックにして納めます。
④永代供養墓
「永代供養墓」はご遺骨を不特定多数の他のご遺骨と一緒に、ひとつの場所に埋葬する「合祀墓」です。ただ合祀するのではなく、永代に渡り合同で供養します。
一般墓に永代供養を付けたお墓も永代供養墓と呼ぶこともありますが、一般的には合祀永代供養墓です。永代供養プランのなかでも最も割安で利用できるでしょう。
永代供養墓の費用相場は約3万円~40万円、平均的には約5万円~15万円ほどです。ただし一度ご遺骨を埋葬すると、二度と個別に取り出すことができません。
・沖縄の永代供養墓はどんなお墓?費用相場は?他の「永代供養」と何が違うかも詳しく解説
・【2024年最新ランキング】沖縄でおすすめの永代供養墓トップ11件、口コミも紹介!
⑤樹木葬・散骨
樹木葬や散骨も、沖縄でお墓の継承者がいない時に検討できる方法です。散骨には里山散骨・海洋散骨・空葬・宇宙葬などがあります。特に沖縄では海洋散骨が選ばれる傾向です。
樹木葬・散骨は永代供養ではなく、ご遺骨を自然に還す「自然葬」のひとつとなります。ただし霊園に特別区画を設けたガーデニング型樹木葬(庭園型樹木葬)は永代供養プランとして提供する施設もあるでしょう。
散骨も厚生労働省により約2mm以下のパウダー状にご遺骨を粉骨することが推奨されています。散骨は個人でもできますが自治体により禁止区域があったり、周辺住民からの苦情も起こり得るため、専門業者へ依頼する流れが一般的です。
沖縄でお墓の継承者がいない時の相談窓口
沖縄でお墓の継承者がいない悩みは、いっそのこと相談窓口で相談してしまう方法もあります。墓じまいから取り出したご遺骨の新しい納骨先まで、ワンステップで相談できる点がメリットです。
霊園・墓地管理者が運営する相談窓口の他、葬祭業界に精通したスタッフがサポートしてくれるため心強いでしょう。
①墓じまい相談
墓じまい相談は霊園・墓地管理者が運営するサロンが多いです。石材業者が運営する墓じまい相談会もあるでしょう。
最初にお墓の内部調査を行い、お墓に眠るご遺骨の柱数や状態を把握してから、具体的な墓じまいプランを提供してくれます。沖縄では火葬を済ませていないご遺骨が出てくることも多々あるため、再火葬まで相談できて便利です。
全ての費用をまとめた「墓じまい・改葬サポートパック」なども見受けます。まずは現状の問題を相談してみてはいかがでしょうか。
・お墓の引越しサポートパック(墓じまい)
②終活相談
「終活」とは相続・お墓の継承・葬儀・死後事務手続きなど、人生の終末への準備を自分で進めることです。
沖縄では次世代のお墓の継承者が見つからずに、終活相談に訪れる人も多くいます。高齢になり定期的なお墓掃除やメンテナンスなどの維持管理が困難になった時もきっかけになるでしょう。
終活相談ではお墓事のみならず、自分亡き後の葬儀・相続・死後事務手続きなど全般に渡る相談ができます。身寄りがない場合は、自分亡き後に誰がご遺骨を埋葬してくれるのか?などの悩みも解消できるでしょう。
・メモリアル終活支援センター
③仏壇じまい相談
沖縄ではお墓とともに仏壇の継承問題も深刻ですよね。先祖代々位牌「トートーメー」にはタブーが今日まで言い伝えられ、むやみに処分することは憚られます。
沖縄で墓じまいとともに仏壇じまいをしたい場合は、仏壇じまいに精通した仏壇・仏具店へ相談してみると良いでしょう。トートーメーやご位牌の永代供養など、安心して任せられる処分方法などを紹介してくれます。
仏壇じまいにあたり魂を抜く閉眼供養も行いますよね。僧侶の手配や、閉眼供養後の仏壇処分も相談できるでしょう。
・供養ギャラリー南風原店
・沖縄の墓じまいで、位牌や仏壇はどうする?仏壇じまいの手順やトートーメー5つの扱い方
まとめ:沖縄でお墓の継承者がいない場合、墓じまいがあります
沖縄でお墓の継承者は父方血族の嫡男が良いとされますが、現代では次世代の継承者がいない「お墓の継承者問題」が深刻です。
そのため現代の沖縄では嫡男にこだわらず、次男以降・娘がお墓を継承するケースも増えました。それでもお墓の継承者問題は解消されていません。家庭裁判所でお墓の継承者が決定されると、相続財産とは違い放棄はできないでしょう。
沖縄でお墓の継承ができない時には、墓じまいの選択肢があります。一度お墓を継承して名義変更を済ませてから、墓じまい・改葬(お墓の引越し)を検討する流れです。
いずれにしても、ひとりで抱え込むことなく家族・親族や専門業者へどんどん相談をして、積極的に問題を解消することをおすすめします。
・【2024年度最新版】沖縄でおすすめの納骨堂・永代供養墓10選!特徴、費用相場は?